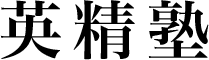コラム
⑩質か量か?~教育における帰納法と演繹法~
心臓内科医三角和雄氏の「量のないところに質はない」からインスピレーションを受けた、この質と量という観点からの思索に欠かせない思考法として、演繹法と帰納法に常々帰着しては、離れたたり、その関係性の終着点が、今回になります。
そもそも、表層的に、演繹法は、ある核を起点として、内発的に、事実の世界を広めて行こう、その事実を確かなもの(真理)にする、内から外へ、そうした知のプロセスです。一方、帰納法は、数多くある事例、データ、知見、諸問題から外圧的に、ある真理に到達しようとする、外から内への知的営為でもある。薬の治験にも似ている、いや、それこそが帰納法の正道でもあろう。こうした演繹法と帰納法というパラダイムを、初等・中等・高等教育に当てはめて考えてみると、教育というものの、教え方、生徒への対峙の仕方などなど、従来にはない興味深い側面が浮かび上がってもくる。
この二つの手法、小学校、中学校、高校、そして大学との兼ね合いで、私見を述べると以下のように思えてならない。私的な理想形でもある。
小学校では、帰納法(初等編)を、中学と高校では、演繹法を、そして大学では、帰納法(高等編)を、それぞれを強烈に意識して、教師や講師は、現場に臨まねばならぬということでもある。生徒自身は、そうした思考プロセスには無自覚、いや、無頓着である。だからこそ、指導者側は、逆に、それを強烈に自覚する必要がある。
たとえば、小学生低学年において、当用漢字を、鉛筆とジャポニカ学習帳で、書いて、書いて、丸暗記した。そして、高学年にあると、その漢字の仕組み、訓読み、音読み、そして、漢字の部首(ヘンやツクリなど)などを、まるで、小学生の英会話主体から中学生の英文法主体へとスライドするように、指導する経緯と似てもいよう。
小学校の少年少女など、思春期以前の、従順な、身体とともに脳細胞が活性化する成長期には、理屈もへったくりもなく、家庭内の、厳しい躾けの如きに、丸暗記をさせる。外部から内部へと知識を集約させる、濃密化する行為が難なくできてしまう、そのプロセスは、初期的帰納法として定義してもいいように思われる。掛け算九九や小数・分数の計算、百ます計算など、まるで、動物の調教・訓練の如く習得させる。この過程は、数や量などものともせず、国算理社など、知識を詰め込んでもゆける大切な時期である。国語でいえば、濫読期間である。小説や物語を中心に、なんでも読み漁る行為、これが肝要である。大人になると、一般的には、そうした読書は、無理、いや、非合理的ともなる。自我や趣向が確立してしまうからだ。特に、小説などは、十代で読まなければならない。それも思春期の感受性豊かな時期が最適なのだ。悪くはないが、いっぱしの大人になって、古典、名作などを読んでも、感受性など育ちもしない。「早く読まないと大人になっちゃう!」という新潮社のコピーがあったが、それを言い当てている。
勿論、算数に関しては、中学受験の難関校などでは、こうした手法では、太刀打ちできない。考える難問が多数だされる、それゆえ、サピックや日能研などは、知的、考える授業をさせてはいるが、こうしたことが可能なのは、あくまで、小学生の1~2割前後の秀才以上でもあろうか。そうしたケースはここでは除外する。彼らは、既に、メンタルとして中学生の脳髄の持ち主に入っているのである。
次に、中学と高校に関しである。この思春期前後の少年少女は、初期的帰納法を拒絶する気質が芽生え始める。脳にも毛が生えてくる!(笑)それゆえ、納得、理解できない内容のものは、心理的、生理的に受け付け難くなる。知的脳内反抗期とも命名しても身体的現象である。歴史でいう所の、点としての歴史、事件、戦、出来事、そして人物の丸暗記から、歴史の流れ、事象の因果関係、そうしたものを下敷きにしなければ、中等教育の歴史、大学受験の歴史には太刀打ちできぬように、教室の当事者たちに、理路整然と説明する義務が生じる。これは、本質的な英文法というものとも一脈通じる。英文法を適当に、中途半端に教えると、英語嫌いな中学生が生まれる理由と歴史丸暗記は、似てもいる。それができる中高生は、まだ、学びの精神年齢が小学生並みでもある証拠だ。
中学、そして、高校ともなれば、小学校以上に、やること、やるべきこと、興味関心など、そして時間に追われる、さらに精神の成長といったものが絡んで、多くの量、数をこなし、その教科を得意なもの、自信のあるもの、そうした科目に変貌・向上させる自発精神(やる気)というものが希薄とり、脆弱化してくる。いわゆる、学びのコスパ、省エネ勉強法などに、姑息にも意識が向くのである。最小限の努力で、最大限の効果を!こうしたメンタリティーが台頭してくる。自助努力へ向かう学びの心が、非学習の方向へと靡いてゆく。
そこでです。教師であれ、講師であれ、ここで、帰納法から演繹法への革命、すなわち、小学生に算数では、XYが禁じ手、使用不可であった時代から、むしを抽象的なXYといった記号や公式を、積極的に使用する世界に瞠目し、数学が、算数以上に、面白く、好きになり、得意になったケースの如く、デカルトに由来する演繹法という、もっとも数学的な手法が、魅力的であること、彼らに悟らせることが、現場指導者の最大の責務なのだ。学びの真の効率性に気づかせるのである。ここにこそ、やる気という自覚、精神の成熟を有する秀才以上は、小学校から中学校へ脱皮もでき、更に学力の飛躍が望める実態がある。一方、準秀才以下は、これができない。そこで、“はしためとしての帰納法”で、その内容を盤石化してゆくプロセス、その教科への自信・確信に到達する核、本質、エッセンス、真理とやらを教え込む、そこからスタートする演繹法の快感を、教師は教え子に、何よりも先に味わわせてあげる。そして、限られた時間しかない、対面での貴重な時間を、それに集中する。凝縮された、濃密なる時間を提供し、内発的に、“帰納法をはしためとする演繹法”に気づかせるのである。実は、この日本で、塾や予備校が絶滅せず、むしろ繁栄している最大の理由はそこに存する。
弊塾では、学校が週5時間の授業で進む内容を、週一回の授業で教え込む。それを、学校での授業を利用し、つまりは、帰納法として、その本質を確実なものとする手法で、学校の授業を復習の場にしなさいとアドバイスしている。聞くところによると、英語に関しては、令和の学校現場では、ほとんど話したり、聞いたり、一切英文の、文法主体の読み書きの行為がない、いや少ないともいう。これって、教育の放棄、教えない教育、教えない塾という美名のもと、学校・塾の存在理由の希薄化であり、責任放棄に値する行為である。巷でいう、教えない教育とは、ある意味で、<自由と規律>とを抱懐するメンタルを有する、一種“エリート教育”なのだ。エリート公立校麹町中学で成功した、“学校の当たり前をやめた”の手法は、標準校以下では、むしろ、逆効果なのである。
つまりは、中等教育の、教えの原理原則とは、演繹法の味を覚えさせ、小学生とは異なる、内発的帰納法(中級編)を行おうとする気質を陶冶することにある。それは、超一流の肉、野菜、魚などを、子供に経験させて、食の嫌い、苦手を克服させる家庭教育にも似ている。中学と高校の学び・教えの理念とは、教師が、演繹法を使いこなせる、いや、その快感を生徒に経験させる、しかも、その本質を伝授することができ、さらに、その科目の面白さを覚醒させ、その学びの効率性、時に、コスパの快感から、能動的帰納法(高等編)へと脱却させることに、今日の教師の任務は存すると信じている。
特に、中等教育、それも私立校の、学校立て直し、下世話な表現だが、生徒が学びを面白いと自覚し、そこから、英数国理社といった学力を向上させる、その結果、大学進学実績が伸びる経緯は、現場教師が、その教科の本質を教授し、そして、生徒自身が演繹法という武器を駆使し、能動的に帰納法へと精神が歩み始めることへ誘導することにしかないと思うのだが、如何だろうか?
余談ながら、「業績は体質の結果である」(鈴木敏文)、これを忘れて、工藤勇一氏は、創英という神奈川県の中高一貫校の改革に失敗したと言ってもいい。白河藩主松平定信が、自藩の改革に成功したとしても、江戸幕府の改革には成功しなかった事例に似てもいる。成功事例とは、その時代、その事案、その状況でのみ、一種、僥倖が加担してもくれた“幸運”なのである。その“幸運”的成功例を、巷の、多くの教育者は、それを金科玉条の如くに、教祖のように、吹聴して、“カリスマ”なる。よく教育の成功事例として、吉田松陰やクラーク博士を取りあげるが、彼の成功事例は、幕末から明治初期だったからであり、その手法は、参考程度にとどめておいて、現代では通用しない、いや、換骨奪胎して、参考程度で、独自の手法を編み出されねばならぬ。
ビリギャルの成功例で有名になり、それをダシに伸びている(?)坪田塾、自身の参考書成功体験が売りで急拡大している(?)武田塾、そして、麹町中学の改革成功で名がとどろき売れっ子講演者(教育改革アドヴァイザー?)となった工藤勇一、彼らに贈る言葉である。「成功は一日で捨て去れ」(柳井正)その成功を捨て去ると、彼らは食ってはいけない。教育とビジネスとの差さでもある。次回は、初等、中等、そして高等教育における、内発的帰納法、つまりは、良き帰納法とやらに言及してみたい。
そもそも、表層的に、演繹法は、ある核を起点として、内発的に、事実の世界を広めて行こう、その事実を確かなもの(真理)にする、内から外へ、そうした知のプロセスです。一方、帰納法は、数多くある事例、データ、知見、諸問題から外圧的に、ある真理に到達しようとする、外から内への知的営為でもある。薬の治験にも似ている、いや、それこそが帰納法の正道でもあろう。こうした演繹法と帰納法というパラダイムを、初等・中等・高等教育に当てはめて考えてみると、教育というものの、教え方、生徒への対峙の仕方などなど、従来にはない興味深い側面が浮かび上がってもくる。
この二つの手法、小学校、中学校、高校、そして大学との兼ね合いで、私見を述べると以下のように思えてならない。私的な理想形でもある。
小学校では、帰納法(初等編)を、中学と高校では、演繹法を、そして大学では、帰納法(高等編)を、それぞれを強烈に意識して、教師や講師は、現場に臨まねばならぬということでもある。生徒自身は、そうした思考プロセスには無自覚、いや、無頓着である。だからこそ、指導者側は、逆に、それを強烈に自覚する必要がある。
たとえば、小学生低学年において、当用漢字を、鉛筆とジャポニカ学習帳で、書いて、書いて、丸暗記した。そして、高学年にあると、その漢字の仕組み、訓読み、音読み、そして、漢字の部首(ヘンやツクリなど)などを、まるで、小学生の英会話主体から中学生の英文法主体へとスライドするように、指導する経緯と似てもいよう。
小学校の少年少女など、思春期以前の、従順な、身体とともに脳細胞が活性化する成長期には、理屈もへったくりもなく、家庭内の、厳しい躾けの如きに、丸暗記をさせる。外部から内部へと知識を集約させる、濃密化する行為が難なくできてしまう、そのプロセスは、初期的帰納法として定義してもいいように思われる。掛け算九九や小数・分数の計算、百ます計算など、まるで、動物の調教・訓練の如く習得させる。この過程は、数や量などものともせず、国算理社など、知識を詰め込んでもゆける大切な時期である。国語でいえば、濫読期間である。小説や物語を中心に、なんでも読み漁る行為、これが肝要である。大人になると、一般的には、そうした読書は、無理、いや、非合理的ともなる。自我や趣向が確立してしまうからだ。特に、小説などは、十代で読まなければならない。それも思春期の感受性豊かな時期が最適なのだ。悪くはないが、いっぱしの大人になって、古典、名作などを読んでも、感受性など育ちもしない。「早く読まないと大人になっちゃう!」という新潮社のコピーがあったが、それを言い当てている。
勿論、算数に関しては、中学受験の難関校などでは、こうした手法では、太刀打ちできない。考える難問が多数だされる、それゆえ、サピックや日能研などは、知的、考える授業をさせてはいるが、こうしたことが可能なのは、あくまで、小学生の1~2割前後の秀才以上でもあろうか。そうしたケースはここでは除外する。彼らは、既に、メンタルとして中学生の脳髄の持ち主に入っているのである。
次に、中学と高校に関しである。この思春期前後の少年少女は、初期的帰納法を拒絶する気質が芽生え始める。脳にも毛が生えてくる!(笑)それゆえ、納得、理解できない内容のものは、心理的、生理的に受け付け難くなる。知的脳内反抗期とも命名しても身体的現象である。歴史でいう所の、点としての歴史、事件、戦、出来事、そして人物の丸暗記から、歴史の流れ、事象の因果関係、そうしたものを下敷きにしなければ、中等教育の歴史、大学受験の歴史には太刀打ちできぬように、教室の当事者たちに、理路整然と説明する義務が生じる。これは、本質的な英文法というものとも一脈通じる。英文法を適当に、中途半端に教えると、英語嫌いな中学生が生まれる理由と歴史丸暗記は、似てもいる。それができる中高生は、まだ、学びの精神年齢が小学生並みでもある証拠だ。
中学、そして、高校ともなれば、小学校以上に、やること、やるべきこと、興味関心など、そして時間に追われる、さらに精神の成長といったものが絡んで、多くの量、数をこなし、その教科を得意なもの、自信のあるもの、そうした科目に変貌・向上させる自発精神(やる気)というものが希薄とり、脆弱化してくる。いわゆる、学びのコスパ、省エネ勉強法などに、姑息にも意識が向くのである。最小限の努力で、最大限の効果を!こうしたメンタリティーが台頭してくる。自助努力へ向かう学びの心が、非学習の方向へと靡いてゆく。
そこでです。教師であれ、講師であれ、ここで、帰納法から演繹法への革命、すなわち、小学生に算数では、XYが禁じ手、使用不可であった時代から、むしを抽象的なXYといった記号や公式を、積極的に使用する世界に瞠目し、数学が、算数以上に、面白く、好きになり、得意になったケースの如く、デカルトに由来する演繹法という、もっとも数学的な手法が、魅力的であること、彼らに悟らせることが、現場指導者の最大の責務なのだ。学びの真の効率性に気づかせるのである。ここにこそ、やる気という自覚、精神の成熟を有する秀才以上は、小学校から中学校へ脱皮もでき、更に学力の飛躍が望める実態がある。一方、準秀才以下は、これができない。そこで、“はしためとしての帰納法”で、その内容を盤石化してゆくプロセス、その教科への自信・確信に到達する核、本質、エッセンス、真理とやらを教え込む、そこからスタートする演繹法の快感を、教師は教え子に、何よりも先に味わわせてあげる。そして、限られた時間しかない、対面での貴重な時間を、それに集中する。凝縮された、濃密なる時間を提供し、内発的に、“帰納法をはしためとする演繹法”に気づかせるのである。実は、この日本で、塾や予備校が絶滅せず、むしろ繁栄している最大の理由はそこに存する。
弊塾では、学校が週5時間の授業で進む内容を、週一回の授業で教え込む。それを、学校での授業を利用し、つまりは、帰納法として、その本質を確実なものとする手法で、学校の授業を復習の場にしなさいとアドバイスしている。聞くところによると、英語に関しては、令和の学校現場では、ほとんど話したり、聞いたり、一切英文の、文法主体の読み書きの行為がない、いや少ないともいう。これって、教育の放棄、教えない教育、教えない塾という美名のもと、学校・塾の存在理由の希薄化であり、責任放棄に値する行為である。巷でいう、教えない教育とは、ある意味で、<自由と規律>とを抱懐するメンタルを有する、一種“エリート教育”なのだ。エリート公立校麹町中学で成功した、“学校の当たり前をやめた”の手法は、標準校以下では、むしろ、逆効果なのである。
つまりは、中等教育の、教えの原理原則とは、演繹法の味を覚えさせ、小学生とは異なる、内発的帰納法(中級編)を行おうとする気質を陶冶することにある。それは、超一流の肉、野菜、魚などを、子供に経験させて、食の嫌い、苦手を克服させる家庭教育にも似ている。中学と高校の学び・教えの理念とは、教師が、演繹法を使いこなせる、いや、その快感を生徒に経験させる、しかも、その本質を伝授することができ、さらに、その科目の面白さを覚醒させ、その学びの効率性、時に、コスパの快感から、能動的帰納法(高等編)へと脱却させることに、今日の教師の任務は存すると信じている。
特に、中等教育、それも私立校の、学校立て直し、下世話な表現だが、生徒が学びを面白いと自覚し、そこから、英数国理社といった学力を向上させる、その結果、大学進学実績が伸びる経緯は、現場教師が、その教科の本質を教授し、そして、生徒自身が演繹法という武器を駆使し、能動的に帰納法へと精神が歩み始めることへ誘導することにしかないと思うのだが、如何だろうか?
余談ながら、「業績は体質の結果である」(鈴木敏文)、これを忘れて、工藤勇一氏は、創英という神奈川県の中高一貫校の改革に失敗したと言ってもいい。白河藩主松平定信が、自藩の改革に成功したとしても、江戸幕府の改革には成功しなかった事例に似てもいる。成功事例とは、その時代、その事案、その状況でのみ、一種、僥倖が加担してもくれた“幸運”なのである。その“幸運”的成功例を、巷の、多くの教育者は、それを金科玉条の如くに、教祖のように、吹聴して、“カリスマ”なる。よく教育の成功事例として、吉田松陰やクラーク博士を取りあげるが、彼の成功事例は、幕末から明治初期だったからであり、その手法は、参考程度にとどめておいて、現代では通用しない、いや、換骨奪胎して、参考程度で、独自の手法を編み出されねばならぬ。
ビリギャルの成功例で有名になり、それをダシに伸びている(?)坪田塾、自身の参考書成功体験が売りで急拡大している(?)武田塾、そして、麹町中学の改革成功で名がとどろき売れっ子講演者(教育改革アドヴァイザー?)となった工藤勇一、彼らに贈る言葉である。「成功は一日で捨て去れ」(柳井正)その成功を捨て去ると、彼らは食ってはいけない。教育とビジネスとの差さでもある。次回は、初等、中等、そして高等教育における、内発的帰納法、つまりは、良き帰納法とやらに言及してみたい。