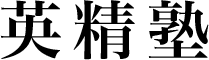コラム
数英国は、"三(っの)輪"の関係だ
前回、英語という科目は、中等教育において、特に、中学の段階で、数学と国語の中間子的役割を果たすと申しあげました。それは、もっと、具体的に、今回は、語ってみようかと思います。
世界で、最も有名なシンボルマーク、オリンピックの五輪のエンブレムがあります。上部が、三輪で、下部が、二輪ともなり、それが有機的に結びつくようにデザインされています。そうです、その上部の三輪を思い描いていただきたいのです。その三輪とは、左部に数学、右部に国語、そして中央に英語というように、それぞれ三つの輪が結びつている、そういう関係性が、実は、その生徒の精神、脳内で化学反応のような現象が、中等教育で生じるという、一種、仮説程度の学習的所見を私はもっているのであります。
小学校時代、それもサピックスや日能研などの進学塾で、算数は得意でも、国語が苦手、一方、国語は高得点が取れるのに、算数がいまいち、こうした生徒をよく見かけます。こうしたタイプの生徒は、実は、中学生の段階で、一つの処方箋があるように思われます。
あの三輪の左部の数学が、中学時代どんなに伸びても、小学校時代の国語の成績には、反映しません。一般的に結びつきません。これは、本コラムや弊著『反デジタル考』でさんざん私説を述べてきました。また、小学校時代、国語が出来ても、数の世界という算数への興味関心、そして意欲といった周辺要因がもととなり、算数への苦手意識が数学の成績不振へと連結するケースも珍しくはありません。左右の靴(数学と国語)のかたちんば現象を、中等教育で克服、軌道修正する秘儀的手法というものが、実は、英語という新教科にあるということを指摘している意見、また、書籍を私は見たことがありません。これから申し上げる説というものは、小学校の延長線、いわば、使える英語、コミュニケーション英語、英文法を二の次にする英語を推進する、文科省主義を固持する学校であればあるほど、私の定説は、当てはまりません。ご容赦ください。
また、逆の論も成立します。中学時代に、算数と国語が得意な生徒は、大方、その学校の方針、教師の当りハズレがないかぎり、あの三輪の規則通り、英語も得意になるものです。これは少々飛躍もありましょうが、漢籍が読めた江戸の蘭学者、漢文ができた明治初期の文豪や学者にも該当する事実であります。
例の、あの三輪を思い描いてください。左部の数学と右部の国語とを左右に持つ中央部の英語という科目とは、ある面で、数学とは、方程式、XやY、√といった記号を自由自在に使用できれば、数学の解へとたどり着けます。これは、小学校時代の四則演算とある程度のひらめき(センス≒感性)というものが必要だった算数と大きな違いであります。この点、英文法主体に教えるという事、誤解を生じやすいのですが、ある意味、発音は二の次、英文法に則り、英語が読めて、書けるという、いわば、外国語を学ぶ鉄則でもある文法という、違った次元における、言語における論理体系に覚醒させるのです。赤子から習得する母語には、こうした体験ルートはないものです。この英文法の論理性を下敷きに、英語が読めるという快感は、数学の母体ともなる算数とは違った、別種の論理性に通底しているという意識、それが、数学に自信を、数学を得意にする啓蒙的間接的教育手法でもあると思われるのです。第二外国語を習得する上での文法と算数の脱皮した新教科、数学における公式というものが、論理性で結びついているという自覚、それを持たせるには、中学にいける英語は、実は、数学という科目の強化で、強力なる援護射撃ともなる教科なのです。これは弊塾の臨床例ですが、早稲田の理工、東工大へ進む生徒は、発音やリスニングが苦手の生徒が多いということからも、いかに、彼らが目と頭で英語に接しているか、その根底には、規則性、論理性第一主義で英語を学ぼうとする、その生理的・心理的な気質の端緒がもあろうかと思われるのです。
次に、右部の国語であります。これも、小学校時代は、物語文主体の、論理性より感性を重視した読解から、中学になると、論説文主体の現代文へと姿を変えます。ここでも、英語が、特効薬ともなるのです。まず、文章、英文ですが、英単語をどれだけ覚えたか、また、英語にでてくる接続詞など、語彙を増やすと、ある程度は、英文を明解に読み込むことができるようになる、その事実を自覚させ、実は、文章とは、古今東西を問わず、読解とは、語彙の多さと論理性(接続語)に基づいて読むことが肝要だと気づかせることが、英語教師務めでもあるのです。この意味で、英語教師は、中等教育の準国語教師の役割を自覚しなければなりません。小学校時代、国語が中途半端にできる、いや、点数に波がある苦手意識を持つ生徒は、英語を通して、読解のいろはの入り口を、苦手教科国語からの脱皮のヒント悟ることができる。でも、英語から国語へ、これは、なかなか至難のわざでもある。数学から英語へ、そのように旨くはいかない<教科内に存する世知辛い現実>というものがあるのです。こうしたタイプは、医学部を含め、理科系では、国公立ではなく、私立の大学に進むものが大勢を占める、その症例の典型でもありましょうや。
以上のように、あの三輪の中央部に位置する英語という輪を持ち上げると、左部の数学、そして、右部の国語(現代文)という教科も、程度の差こそあれ、上昇する現象が生じるというのが、私の所見でもあるのです。
これは、実質、高校1年で始まる古文の授業においても、同様の確信があります。まず、英語、特に、英文法が苦手、好きではない生徒で、古文が得意だという生徒にまずお目にかかったことはありません。一方、古文が得意な生徒で、英語が苦手な生徒は、まず、その原因は、学校当局の、担当英語教師の、その資質、流儀に原因がある場合がほとんどです。つまり、古文が得意な生徒は、本来は、英語も得意、得意でなければならないと申し上げておきましょう。これは明治期の文豪、鷗外、漱石、藤村、谷崎、芥川などの類例は、暇がないほど、綺羅の如くであります。ここでも、やはり、限度のスターとラインは、母国語の成熟度、熟成度、それにあると言わねばなりません。小学校時代の、最重要科目、それが国語である所以です。小学校時代は、英語など、どうでもいいのです。その証拠として、中学受験では、超とつく進学校に限り、英語受験枠などないからです。
このように、実は、生徒はもちろん、教師でさえも、様々な教科、その全体的連関性・有機的結合性といったものに蒙昧なのであります。学校のそれぞれのクラスが間切りされて、ABCDといった4組に区分けされていると考えるより、大手企業の大きなフロアーのように、それぞれの部署が、吹き抜けのフロアーで、全体で、即、コミュニケーションがとれるような、学びの精神構造になっているのです。勉学指導、進路指導などで失敗し、進学実績がいまいち、理事長・校長が不満な中高一貫校の当事者は、この点に気づいていないと申しあげてもおきましょう。数学は数学の王道があり、国語は国語なり道筋があると、それぞれの教科教員は、そう思い込んでいる。まるで鎌倉仏教の、日蓮(題目)、親鸞(念仏)、道元(坐禅)など、それぞれの教派のドグマにとらわれ過ぎてもいる。その流派で、救われればいい、しかし、信仰、幸福論と学び、勉学、サイエンスとは違うのです。ここにも、リベラルアーツの水脈が根底に流れている点に気づいていないのです。
これは、場を新たにして、論ずるべきことですが、平成から叫ばれている理系ばなれ、数学嫌い、また、生まれてはすぐに消えてゆく若者ことばの跋扈などは、実は、英語教育から、英文法を軽視する、排除する、二の次にする、そうした英語教育が遠因にあると指摘する教育関係者は、一人もいません。この観点から、英数国にける中等教育という論文を書いても面白いものが生まれと思うのですが、如何でありましょうか。
結論を申しあげるとすれば、中等教育における、学校の教師・塾や予備校の講師の心的要諦(心構え)は、生徒に<英数国という教科>が、それぞれ独立した、まったく別物ではなく、“論理性という一本の串”で貫かれている<赤白緑の三色団子>のようなものだと自覚を促すことにあるのです。また、そうした指導者に巡り会えなくても、現場の成功者としての少年少女は、無意識ながら、その三教科は、ある法則性、ある定則性があり、それを学問の体系として、また、論理性として、当然彼らには、そうした概念などを脳裏に浮かびようもありませんが、それが、学びの快感、学びにおける自己の成長、学びにおけるモノゴトの観点の違いの驚きとして自覚されてくる者は、中等教育の勝者ともなるのであります。
世界で、最も有名なシンボルマーク、オリンピックの五輪のエンブレムがあります。上部が、三輪で、下部が、二輪ともなり、それが有機的に結びつくようにデザインされています。そうです、その上部の三輪を思い描いていただきたいのです。その三輪とは、左部に数学、右部に国語、そして中央に英語というように、それぞれ三つの輪が結びつている、そういう関係性が、実は、その生徒の精神、脳内で化学反応のような現象が、中等教育で生じるという、一種、仮説程度の学習的所見を私はもっているのであります。
小学校時代、それもサピックスや日能研などの進学塾で、算数は得意でも、国語が苦手、一方、国語は高得点が取れるのに、算数がいまいち、こうした生徒をよく見かけます。こうしたタイプの生徒は、実は、中学生の段階で、一つの処方箋があるように思われます。
あの三輪の左部の数学が、中学時代どんなに伸びても、小学校時代の国語の成績には、反映しません。一般的に結びつきません。これは、本コラムや弊著『反デジタル考』でさんざん私説を述べてきました。また、小学校時代、国語が出来ても、数の世界という算数への興味関心、そして意欲といった周辺要因がもととなり、算数への苦手意識が数学の成績不振へと連結するケースも珍しくはありません。左右の靴(数学と国語)のかたちんば現象を、中等教育で克服、軌道修正する秘儀的手法というものが、実は、英語という新教科にあるということを指摘している意見、また、書籍を私は見たことがありません。これから申し上げる説というものは、小学校の延長線、いわば、使える英語、コミュニケーション英語、英文法を二の次にする英語を推進する、文科省主義を固持する学校であればあるほど、私の定説は、当てはまりません。ご容赦ください。
また、逆の論も成立します。中学時代に、算数と国語が得意な生徒は、大方、その学校の方針、教師の当りハズレがないかぎり、あの三輪の規則通り、英語も得意になるものです。これは少々飛躍もありましょうが、漢籍が読めた江戸の蘭学者、漢文ができた明治初期の文豪や学者にも該当する事実であります。
例の、あの三輪を思い描いてください。左部の数学と右部の国語とを左右に持つ中央部の英語という科目とは、ある面で、数学とは、方程式、XやY、√といった記号を自由自在に使用できれば、数学の解へとたどり着けます。これは、小学校時代の四則演算とある程度のひらめき(センス≒感性)というものが必要だった算数と大きな違いであります。この点、英文法主体に教えるという事、誤解を生じやすいのですが、ある意味、発音は二の次、英文法に則り、英語が読めて、書けるという、いわば、外国語を学ぶ鉄則でもある文法という、違った次元における、言語における論理体系に覚醒させるのです。赤子から習得する母語には、こうした体験ルートはないものです。この英文法の論理性を下敷きに、英語が読めるという快感は、数学の母体ともなる算数とは違った、別種の論理性に通底しているという意識、それが、数学に自信を、数学を得意にする啓蒙的間接的教育手法でもあると思われるのです。第二外国語を習得する上での文法と算数の脱皮した新教科、数学における公式というものが、論理性で結びついているという自覚、それを持たせるには、中学にいける英語は、実は、数学という科目の強化で、強力なる援護射撃ともなる教科なのです。これは弊塾の臨床例ですが、早稲田の理工、東工大へ進む生徒は、発音やリスニングが苦手の生徒が多いということからも、いかに、彼らが目と頭で英語に接しているか、その根底には、規則性、論理性第一主義で英語を学ぼうとする、その生理的・心理的な気質の端緒がもあろうかと思われるのです。
次に、右部の国語であります。これも、小学校時代は、物語文主体の、論理性より感性を重視した読解から、中学になると、論説文主体の現代文へと姿を変えます。ここでも、英語が、特効薬ともなるのです。まず、文章、英文ですが、英単語をどれだけ覚えたか、また、英語にでてくる接続詞など、語彙を増やすと、ある程度は、英文を明解に読み込むことができるようになる、その事実を自覚させ、実は、文章とは、古今東西を問わず、読解とは、語彙の多さと論理性(接続語)に基づいて読むことが肝要だと気づかせることが、英語教師務めでもあるのです。この意味で、英語教師は、中等教育の準国語教師の役割を自覚しなければなりません。小学校時代、国語が中途半端にできる、いや、点数に波がある苦手意識を持つ生徒は、英語を通して、読解のいろはの入り口を、苦手教科国語からの脱皮のヒント悟ることができる。でも、英語から国語へ、これは、なかなか至難のわざでもある。数学から英語へ、そのように旨くはいかない<教科内に存する世知辛い現実>というものがあるのです。こうしたタイプは、医学部を含め、理科系では、国公立ではなく、私立の大学に進むものが大勢を占める、その症例の典型でもありましょうや。
以上のように、あの三輪の中央部に位置する英語という輪を持ち上げると、左部の数学、そして、右部の国語(現代文)という教科も、程度の差こそあれ、上昇する現象が生じるというのが、私の所見でもあるのです。
これは、実質、高校1年で始まる古文の授業においても、同様の確信があります。まず、英語、特に、英文法が苦手、好きではない生徒で、古文が得意だという生徒にまずお目にかかったことはありません。一方、古文が得意な生徒で、英語が苦手な生徒は、まず、その原因は、学校当局の、担当英語教師の、その資質、流儀に原因がある場合がほとんどです。つまり、古文が得意な生徒は、本来は、英語も得意、得意でなければならないと申し上げておきましょう。これは明治期の文豪、鷗外、漱石、藤村、谷崎、芥川などの類例は、暇がないほど、綺羅の如くであります。ここでも、やはり、限度のスターとラインは、母国語の成熟度、熟成度、それにあると言わねばなりません。小学校時代の、最重要科目、それが国語である所以です。小学校時代は、英語など、どうでもいいのです。その証拠として、中学受験では、超とつく進学校に限り、英語受験枠などないからです。
このように、実は、生徒はもちろん、教師でさえも、様々な教科、その全体的連関性・有機的結合性といったものに蒙昧なのであります。学校のそれぞれのクラスが間切りされて、ABCDといった4組に区分けされていると考えるより、大手企業の大きなフロアーのように、それぞれの部署が、吹き抜けのフロアーで、全体で、即、コミュニケーションがとれるような、学びの精神構造になっているのです。勉学指導、進路指導などで失敗し、進学実績がいまいち、理事長・校長が不満な中高一貫校の当事者は、この点に気づいていないと申しあげてもおきましょう。数学は数学の王道があり、国語は国語なり道筋があると、それぞれの教科教員は、そう思い込んでいる。まるで鎌倉仏教の、日蓮(題目)、親鸞(念仏)、道元(坐禅)など、それぞれの教派のドグマにとらわれ過ぎてもいる。その流派で、救われればいい、しかし、信仰、幸福論と学び、勉学、サイエンスとは違うのです。ここにも、リベラルアーツの水脈が根底に流れている点に気づいていないのです。
これは、場を新たにして、論ずるべきことですが、平成から叫ばれている理系ばなれ、数学嫌い、また、生まれてはすぐに消えてゆく若者ことばの跋扈などは、実は、英語教育から、英文法を軽視する、排除する、二の次にする、そうした英語教育が遠因にあると指摘する教育関係者は、一人もいません。この観点から、英数国にける中等教育という論文を書いても面白いものが生まれと思うのですが、如何でありましょうか。
結論を申しあげるとすれば、中等教育における、学校の教師・塾や予備校の講師の心的要諦(心構え)は、生徒に<英数国という教科>が、それぞれ独立した、まったく別物ではなく、“論理性という一本の串”で貫かれている<赤白緑の三色団子>のようなものだと自覚を促すことにあるのです。また、そうした指導者に巡り会えなくても、現場の成功者としての少年少女は、無意識ながら、その三教科は、ある法則性、ある定則性があり、それを学問の体系として、また、論理性として、当然彼らには、そうした概念などを脳裏に浮かびようもありませんが、それが、学びの快感、学びにおける自己の成長、学びにおけるモノゴトの観点の違いの驚きとして自覚されてくる者は、中等教育の勝者ともなるのであります。