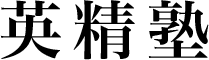コラム
科目の因果は廻る~国語と英語~
「風が吹けば桶屋が儲かる」的言説とも捉えられかねないが、一応は、自身の経験に基づく教育的私見を語ってみたい。
最近、算盤ブームが再来しているとテレ朝のワイドスクランブルという番組で報じていた。その理由は、中学受験に向けた予備段階の親の入念さからくるものだという。一般的に、中学受験組に関していえば、小学校4年生からサピックスや日能研などの進学塾に通い始める。その前に、絶対的、圧倒的な計算力を我が子に身に付けさせておこうとう目論見があるとのことだ。この観点で、佐藤亮子、佐藤ママなどは、4年生までに、通常の6年生のカリィキュラムを終了させておく、つまり、完璧な四則演算を習得させる、そして、4年から高度な応用問題、時には、中学数学を超先取りして、我が子を鍛えるルートとも、受験の登山ルートとしては、別だが、その窮境の武器、いわば、絶対的計算能力を算盤で我が子に、受験の基本的武器を身に付けさせようとするものだ。
国語でも、幼稚園まで、絵本や物語を読み聞かせ、小学校低学年で、本を読ませる習慣を身につけさせる、また、小学校の低学年で、漢字検定2級の域にまで指導する親も同様であろう。4年生からの中学受験の、知の筋トレならぬ、言語の海へのりだす準備体操といったところだろうか。
この、小学校低学年における、算盤と読書、これは、敢えて言えば前者の方が手っ取り早く、効果てきめん、即、計算力、算数の点数として跳ね返ってもくる、しかも、算盤教室内での、他の生徒との競い合い、また、慎重さを要する計算から育つ自己との格闘、そこから派生する集中力、克己心、こういったものが、その子の他の科目への好影響もハッキリしている。一方、国語は、読書をしたからといって、その好影響はもどかし、効果はグレーゾーンと思われがちである。つまり、効果が不確かと思う親が多い、よって、受験で大切な国算では、敢えて、算数の下ごしらえとしての算盤に世の親御さんが行き着くのは納得できる。
この算盤から、圧倒的な計算力、そして、そうした脳内電卓を確立し、小4からの中学受験の武器として、算数を得意科目へと誘導する親の心境は容易に想像できるのである。
この算数の勝者は、大方、数学の勝ち組になる確率が高いのは、その中学受験での、その算数へのプライドが、数学への矜持へと、受け継がれるケースは少なくないのである。そうでない場合は、算数という風土から抽象的概念でもある様々な記号や数式の意識の、自覚の薄い生徒とも言い得る。初等から中等への、科目風土への変化の対応のまずさである。これは、中学数学と高校数学との違いでも極端に露見する。高校からの数学放棄組である。やはり、社会や企業だけではなく、一個人の内面における、意識改革、メンタルの脱皮、新たな学びへの覚醒、こうしたものが、一人の人間のメンタルでも当てはまるのである。
国語に関しては、弊著『反デジタル考』でも、本コラムでも、散々語ってもきたが、国語という科目は、小学校以前の親なりの読み聞かせ体験、それにドッキングした小学校低学年から、出来れば高学年にわたる、自発的、前向きな読書量というものが、命運をわける。この成功組は、低学年から算盤をやらずとも、公文式の先取り講座を受けずとも、算数や理科、社会への学力のシナジー効果は絶大なのである。わざわざ名前を挙げるまでもないが、有名人としては、茂木健一郎、林修、山口真由、中野信子、三浦瑠璃など、特に、東大へと進む、天才から秀才の王道は、ましくこうした「小学校の国語経験が種となり、その後の様々な科目の葉とぞなりける」である。ここの、教育上の秘儀を、「小学校時代は、一に国語、二に国語、三、四がなくて、五に算数、英語、パソコン(プログラミング)、そんなのどうでもいい!」と数学者藤原正彦氏は、喝破していたのだ。この典型的な範例は、林修氏の小学校時代のエピソードを知れば得心するはずである。彼は、算盤も公文式もやってはいない。六年から中学受験を始め、一年で、愛知の名門東海中学校に合格する。
では、算数はそこそこ得意、国語は標準的、いや、苦手であって、私立の中高一貫校、進学校へ進んだ次の学びのフェーズにおける心得といったものを私は、声を大にして主張したいのである。茂木健一郎や林修のような、国語をベースとした、初等教育を歩んでこなかった準秀才以下の処方箋とやらである。
算数から数学へ、そして、物語中心の国語から評論文主体の現代文へ、学びの空間が、知的色彩が際立ってくる、論理的音色が鳴り響いてもくる、まるで、アフリカのサバンナからシベリアの極寒へ、動物が移動せざるをえなくなった窮境の状況にも学びにおいて類似する体験を12才の少年はする羽目となる。丁度、夏(小学校)から冬(中学校)へと秋を挟まず移行すれば、人間を含め生き物は体調不良となる。これが、中学時代の成績の落ち込み、伸び悩みの遠因なのである。この夏と冬の間に、秋という季節が介在して、動植物は変化への対応をし、生き延びてもゆく、この学びの変化、それも数学と現代文とを引き留めてもおく、“子は鎹(かすがい)”とも言われるように、“英語は数国という両親の鎹(かすがい)”ともいいえる真実なのだ。
これまで、数回にわたり、「英語は数学と国語の中間子だ!」にしろ、「英語は三輪の左右の輪をつなぎとめる真ん中の輪である!」にしろ、実は、“英語は、数国の鎹(かすがい)だ!”という私見による事実{※学者なりが調査研究してエビダンスがないから}を言いたかったわけである。
数学は、様々な記号や公式を多用することから論理性を、また、現代文は、様々な高度の漢字、そして、抽象的な概念を身に付けることで、これも論理性を、それぞれの二科目から、論理性というものを意識、無意識にかかわらず、習得し、それを強化できるものは、問題がない。大方、小学校時代、算数も国語もそれぞれ得意だった少年が、中学における数学と現代文とにドッキングしている恵まれた素質、また、幸運(学校や教師など)を持つものは、意外と少数派であると指摘する者は皆無である。ここなのだ、私が主張したい点は。
実は、英語という教科の、その根本的大切さは、この中等教育の命運をわける論理性、それに覚醒したメンタルの成長度、その鍵が人生で、母国語以外の英語という、違った言語体系を、12才から実感することにあるのだ。英語が喋れるだの、使える英語だの、それ以前の、言語による理性の覚醒にこそ、中学における英語の存在意義があるといいたにまでである。この中心が、英文法であることは言うまでもない。英文法なんて難しいことばかりに汲々としているから英語嫌いになるのだ、といった言説が、まかり通っているが、そうした種族の少年少女には、第二外国語など教える必要は、本来ないのである。
「やまとうたは、人の心を種としてよろずのことの葉とぞなれりける」(紀貫之:古今和歌集の序)、ではないが、「小学校は、国語を種としてよろずの科目の葉とぞなれりける」でもあり、「中学は、英語を種としてよろずの科目の葉とぞなれりける」でもある。論理の飛躍であろうか、極論であろうか、こここそが、「風が吹けば桶屋が儲かる」的言説と、私見が曲解される外貌をまとってもいる点でもあろう。
江戸時代の蘭学を概観するまでもなく、その種は、杉田玄白と前野良沢らのオランダ語の解読、そこから派生したオランダ語辞典(ハルマ和解)の誕生を概観するまでもない。
室町まででは、仏教をベースとした自然観・人生観、江戸の中期までは、儒学をベースとした社会観、そして、ターヘルアナトミアの翻訳を境に、オランダ語を起点とした科学観、こうした、日本民族の“知のエピステーメ(地層のようなもの)”は、三層構造で、積み上げられてもきた。その上層部の蘭学とその下部の漢籍の素養というものがあったればこそ、明治維新で、特に、英語を中心とした近代化を成し遂げた歴史的経歴は、丁度、小学校時代、中学校時代、そして、高校時代にそれぞれことばをベースとした精神形成が積み上げられて、大学という高等教育でも、花を、実をつける、そういった人間個人レベルでも該当する、言語の重積性というものが、いかに大切かが、歴史からもわかるというものである。余談であるが、明治近代化の最大功績者でもある伊藤博文などは、その武器は、その“種”は、長州ファイブとして英国に密航留学したこと、“英語”が、最大の要因であったことは論を待たない。福沢諭吉や新島襄も類例の典型であろう。
国家の歴史を微分すると、一人の人間の人生が、“教養という顕微鏡”から見えてくる。一方、一個人の生き様を積分すると、“教養という望遠鏡”を通して一国家の相貌が浮かび上がってもくる。この相関関係を、“鑑・鏡”という一文字で雄弁に語るは、あの徳川家康の枕頭の書でもあった『吾妻鑑』から遡ること『大鏡』まで挙げるまでもない。
最近、算盤ブームが再来しているとテレ朝のワイドスクランブルという番組で報じていた。その理由は、中学受験に向けた予備段階の親の入念さからくるものだという。一般的に、中学受験組に関していえば、小学校4年生からサピックスや日能研などの進学塾に通い始める。その前に、絶対的、圧倒的な計算力を我が子に身に付けさせておこうとう目論見があるとのことだ。この観点で、佐藤亮子、佐藤ママなどは、4年生までに、通常の6年生のカリィキュラムを終了させておく、つまり、完璧な四則演算を習得させる、そして、4年から高度な応用問題、時には、中学数学を超先取りして、我が子を鍛えるルートとも、受験の登山ルートとしては、別だが、その窮境の武器、いわば、絶対的計算能力を算盤で我が子に、受験の基本的武器を身に付けさせようとするものだ。
国語でも、幼稚園まで、絵本や物語を読み聞かせ、小学校低学年で、本を読ませる習慣を身につけさせる、また、小学校の低学年で、漢字検定2級の域にまで指導する親も同様であろう。4年生からの中学受験の、知の筋トレならぬ、言語の海へのりだす準備体操といったところだろうか。
この、小学校低学年における、算盤と読書、これは、敢えて言えば前者の方が手っ取り早く、効果てきめん、即、計算力、算数の点数として跳ね返ってもくる、しかも、算盤教室内での、他の生徒との競い合い、また、慎重さを要する計算から育つ自己との格闘、そこから派生する集中力、克己心、こういったものが、その子の他の科目への好影響もハッキリしている。一方、国語は、読書をしたからといって、その好影響はもどかし、効果はグレーゾーンと思われがちである。つまり、効果が不確かと思う親が多い、よって、受験で大切な国算では、敢えて、算数の下ごしらえとしての算盤に世の親御さんが行き着くのは納得できる。
この算盤から、圧倒的な計算力、そして、そうした脳内電卓を確立し、小4からの中学受験の武器として、算数を得意科目へと誘導する親の心境は容易に想像できるのである。
この算数の勝者は、大方、数学の勝ち組になる確率が高いのは、その中学受験での、その算数へのプライドが、数学への矜持へと、受け継がれるケースは少なくないのである。そうでない場合は、算数という風土から抽象的概念でもある様々な記号や数式の意識の、自覚の薄い生徒とも言い得る。初等から中等への、科目風土への変化の対応のまずさである。これは、中学数学と高校数学との違いでも極端に露見する。高校からの数学放棄組である。やはり、社会や企業だけではなく、一個人の内面における、意識改革、メンタルの脱皮、新たな学びへの覚醒、こうしたものが、一人の人間のメンタルでも当てはまるのである。
国語に関しては、弊著『反デジタル考』でも、本コラムでも、散々語ってもきたが、国語という科目は、小学校以前の親なりの読み聞かせ体験、それにドッキングした小学校低学年から、出来れば高学年にわたる、自発的、前向きな読書量というものが、命運をわける。この成功組は、低学年から算盤をやらずとも、公文式の先取り講座を受けずとも、算数や理科、社会への学力のシナジー効果は絶大なのである。わざわざ名前を挙げるまでもないが、有名人としては、茂木健一郎、林修、山口真由、中野信子、三浦瑠璃など、特に、東大へと進む、天才から秀才の王道は、ましくこうした「小学校の国語経験が種となり、その後の様々な科目の葉とぞなりける」である。ここの、教育上の秘儀を、「小学校時代は、一に国語、二に国語、三、四がなくて、五に算数、英語、パソコン(プログラミング)、そんなのどうでもいい!」と数学者藤原正彦氏は、喝破していたのだ。この典型的な範例は、林修氏の小学校時代のエピソードを知れば得心するはずである。彼は、算盤も公文式もやってはいない。六年から中学受験を始め、一年で、愛知の名門東海中学校に合格する。
では、算数はそこそこ得意、国語は標準的、いや、苦手であって、私立の中高一貫校、進学校へ進んだ次の学びのフェーズにおける心得といったものを私は、声を大にして主張したいのである。茂木健一郎や林修のような、国語をベースとした、初等教育を歩んでこなかった準秀才以下の処方箋とやらである。
算数から数学へ、そして、物語中心の国語から評論文主体の現代文へ、学びの空間が、知的色彩が際立ってくる、論理的音色が鳴り響いてもくる、まるで、アフリカのサバンナからシベリアの極寒へ、動物が移動せざるをえなくなった窮境の状況にも学びにおいて類似する体験を12才の少年はする羽目となる。丁度、夏(小学校)から冬(中学校)へと秋を挟まず移行すれば、人間を含め生き物は体調不良となる。これが、中学時代の成績の落ち込み、伸び悩みの遠因なのである。この夏と冬の間に、秋という季節が介在して、動植物は変化への対応をし、生き延びてもゆく、この学びの変化、それも数学と現代文とを引き留めてもおく、“子は鎹(かすがい)”とも言われるように、“英語は数国という両親の鎹(かすがい)”ともいいえる真実なのだ。
これまで、数回にわたり、「英語は数学と国語の中間子だ!」にしろ、「英語は三輪の左右の輪をつなぎとめる真ん中の輪である!」にしろ、実は、“英語は、数国の鎹(かすがい)だ!”という私見による事実{※学者なりが調査研究してエビダンスがないから}を言いたかったわけである。
数学は、様々な記号や公式を多用することから論理性を、また、現代文は、様々な高度の漢字、そして、抽象的な概念を身に付けることで、これも論理性を、それぞれの二科目から、論理性というものを意識、無意識にかかわらず、習得し、それを強化できるものは、問題がない。大方、小学校時代、算数も国語もそれぞれ得意だった少年が、中学における数学と現代文とにドッキングしている恵まれた素質、また、幸運(学校や教師など)を持つものは、意外と少数派であると指摘する者は皆無である。ここなのだ、私が主張したい点は。
実は、英語という教科の、その根本的大切さは、この中等教育の命運をわける論理性、それに覚醒したメンタルの成長度、その鍵が人生で、母国語以外の英語という、違った言語体系を、12才から実感することにあるのだ。英語が喋れるだの、使える英語だの、それ以前の、言語による理性の覚醒にこそ、中学における英語の存在意義があるといいたにまでである。この中心が、英文法であることは言うまでもない。英文法なんて難しいことばかりに汲々としているから英語嫌いになるのだ、といった言説が、まかり通っているが、そうした種族の少年少女には、第二外国語など教える必要は、本来ないのである。
「やまとうたは、人の心を種としてよろずのことの葉とぞなれりける」(紀貫之:古今和歌集の序)、ではないが、「小学校は、国語を種としてよろずの科目の葉とぞなれりける」でもあり、「中学は、英語を種としてよろずの科目の葉とぞなれりける」でもある。論理の飛躍であろうか、極論であろうか、こここそが、「風が吹けば桶屋が儲かる」的言説と、私見が曲解される外貌をまとってもいる点でもあろう。
江戸時代の蘭学を概観するまでもなく、その種は、杉田玄白と前野良沢らのオランダ語の解読、そこから派生したオランダ語辞典(ハルマ和解)の誕生を概観するまでもない。
室町まででは、仏教をベースとした自然観・人生観、江戸の中期までは、儒学をベースとした社会観、そして、ターヘルアナトミアの翻訳を境に、オランダ語を起点とした科学観、こうした、日本民族の“知のエピステーメ(地層のようなもの)”は、三層構造で、積み上げられてもきた。その上層部の蘭学とその下部の漢籍の素養というものがあったればこそ、明治維新で、特に、英語を中心とした近代化を成し遂げた歴史的経歴は、丁度、小学校時代、中学校時代、そして、高校時代にそれぞれことばをベースとした精神形成が積み上げられて、大学という高等教育でも、花を、実をつける、そういった人間個人レベルでも該当する、言語の重積性というものが、いかに大切かが、歴史からもわかるというものである。余談であるが、明治近代化の最大功績者でもある伊藤博文などは、その武器は、その“種”は、長州ファイブとして英国に密航留学したこと、“英語”が、最大の要因であったことは論を待たない。福沢諭吉や新島襄も類例の典型であろう。
国家の歴史を微分すると、一人の人間の人生が、“教養という顕微鏡”から見えてくる。一方、一個人の生き様を積分すると、“教養という望遠鏡”を通して一国家の相貌が浮かび上がってもくる。この相関関係を、“鑑・鏡”という一文字で雄弁に語るは、あの徳川家康の枕頭の書でもあった『吾妻鑑』から遡ること『大鏡』まで挙げるまでもない。