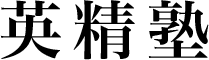コラム
便利・快適という自由は、真の自由を奪う
戦争と平和 対にしてよく語られるが、通常は平和の時代の中に、雨後の筍の如きに事故や災害として、不幸が起こると一般人は考えやすい。晴天が長く、時々雨が降るように考える。一方、東洋的、特に仏教的文脈でなのだが、通常、世は戦争であり、その合間合間に、幸福としての、ささやかな幸せという陽がさす如く、やってくるというものがある。それは、現代のガザ地区のパレスチナ人と幸運にも戦後80年、戦争をしらないできてた日本人の戦争観と平和観の違いともいえよう。
幸と不幸とは、背中合わせ、人生はあざなえる縄の如しともいう。ここに、何気ない日常の中に幸福があるとする、日々の日常への感謝の念、こうした価値観は、人生上の不如意に直面したり、挫折や失敗の状況下に置かれると、じんわりと心の底から沸き上がっても来る実感でもあろう。「今年も、家族が無事健康でありますように」という初詣で心中願うお願い事に、それは如実に表れてもいよう。
失敗は成功の母とはよく言われるが、不運は、不幸は、幸せの母でもあろうか、何も禅僧的教訓を述べているのではない。唯物論的観点から、唯心論に近い真実を語っているまでである。甘味処のお汁粉に添えられている塩昆布や柴漬け、料理後のスイーツである。甘いとショッパイの味覚的対照的快感でもある。三島由紀夫の「聖と猥のせめぎ合いから美が生まれる」とも言い得る真理である。今年の大河ドラマ『べらぼう』での登場自分の発言である。前政権田沼時代と現政権松平定信の配下の武士が老中に諫言するものである。「民は正しさのみでは生きてはゆけないのでございます。遊びを、楽しみを求めているのであります」これなども、甘いご時世としょっぱいを政(まつりごと)を、政治次元で上奏しているのである。
産業革命以降、サイエンスという語は、本来は、学問という意味であり、自然・社会・人文科学を包摂する用語でもあったものが、自然科学の専売特許用語、自然科学の代名詞、専有物ともなってきた。英文法用語の<完了形>というものに似ている。この“have+p.p.”という形態には、経験・継続・結果といった意味用法もあり、何も完了といったアスペクトだけに限らないのだ。また、ヨドバシカメラといいながら、カメラだけ販売している量販店ではない事実とも似ている。
これは、従来の文化を分母とし、文明を分子とする観念を、実証主義・合理主義・論理主義という理念で、逆転させてもきた。それは、天動説から地動説へのコペルニクス的転換ともいいうるもので、それに覚醒し、それに成功した列強が、19世紀の帝国主義の主役に躍り出たことでも明らかである。哲学は神学の下僕(はしため)とも言われた地位から、カントは、宗教から哲学を独立せしめた時から近代が、社会科学・人文科学も進化を遂げてもきた。それは、アングロサクソン民族が、英国から独立したアメリカの如きものでもあった。
特に、20世紀は文明が急激に発展した。21世紀は、まさしく、デジタルを“憲法”とした文明帝国の時代である。GAFAM帝国を概観するまでもなく、スマホ、いわゆるSNS社会が下部構造(プラットフォーム)ともなり、政治・経済というものを動かし、その国家、企業の命運を左右するまでになってきている。それは、自由、いや、便利・快適・効率性ともいっていい三概念である。これに背く、無視するは、市場退場、消滅の憂き目にあう時代でもあるということだ。その最先端は、生成AIでもあろうか?この神とも、皇帝ともいいえる文明の絶対者が、人間にあらゆる自由を授けてもきている昨今ではある。まるで古代ローマ帝国が、従来の多神教からキリスト教の一神教へと転換したように、デジタルの神に、全ての自由を与えられ、それで、その便利さ、快適さ、功利性というものが、自身の人生、生活というものを自由最優先と洗脳されかけているという実体なのである。古代ローマ帝国の市民をおとなしくさせておくモットー「パンとサーカス」これが、現代では、「ファーストフードとスマホ」でもあるのだ。こうした関係は、人間とペットの犬ともいいえる関係なのである。今年の文化功労者に選ばれ、将来的には、文化勲章も受賞されるであろうと予想もつく演劇家の野田秀樹の弁、「人が何かを受け止める順番は『感じる・考える・信じる』のはずなのに、最近は『考える』が抜け落ちて、『感じる・信じる』が直結しているのではないか」この鋭い指摘が、現代社会の時世を、東西を問わず、象徴しもいよう。この野田氏の文脈で言えば、文章、特に、小論文を書くとすれば、序論、本論、結論といった三段論法が、大学入試の小論文でいう、序論と結論でもOKという社会、入試問題の、奇妙奇天烈ともいえる模範的解答文であることに類する現況が到来しかけているのである。
現代は、科学、それもデジタルの恩恵により、中国やロシアといった独裁国を含み、ある意味、便利さ、快適さを錦の御旗として、どれほど“自由”というものを謳歌しているか、その“身体的自由さ”を人民、国民に与えさえすれば、精神的不自由さは、二の次でも構わない、少々目をつぶるという現実を習近平やプーチンが見抜いている現実だ。中国人にしろ、ロシア人にしろ、海外旅行は自由であるが、言論・思想統制という拘束(国家)からは自由(逃避)になれない。いや、トランプとて、狭義の意味で、同じやも知れない。「痩せたソクラテスより、肥った豚になれ」、この標語で、21世紀は政治が行われてもいる。それを電脳社会が、国民の外面から、内面から、がんじがらめにしている。数十年前、社員を捩って社畜という言葉が生まれたが、今や、国畜、いや、電畜の時代でもあろう。ここでであるが、ここに自由の対義語が不自由なのか、規律なのかという命題が浮上しもこよう。この命題は、「成功の反対は、失敗ではなく、妥協である」(木村政雄)の名言が浮上してもこよう。ここの観点から、次回、外面における危機、即ち、現代の地球温暖化には敏感なくせに、内面の危機、いわば、精神のデジタル化(0と1という二元論、また、白か黒かといった灰色という中庸を排除する空気)には無頓着な現代人について語ってもみたい。
幸と不幸とは、背中合わせ、人生はあざなえる縄の如しともいう。ここに、何気ない日常の中に幸福があるとする、日々の日常への感謝の念、こうした価値観は、人生上の不如意に直面したり、挫折や失敗の状況下に置かれると、じんわりと心の底から沸き上がっても来る実感でもあろう。「今年も、家族が無事健康でありますように」という初詣で心中願うお願い事に、それは如実に表れてもいよう。
失敗は成功の母とはよく言われるが、不運は、不幸は、幸せの母でもあろうか、何も禅僧的教訓を述べているのではない。唯物論的観点から、唯心論に近い真実を語っているまでである。甘味処のお汁粉に添えられている塩昆布や柴漬け、料理後のスイーツである。甘いとショッパイの味覚的対照的快感でもある。三島由紀夫の「聖と猥のせめぎ合いから美が生まれる」とも言い得る真理である。今年の大河ドラマ『べらぼう』での登場自分の発言である。前政権田沼時代と現政権松平定信の配下の武士が老中に諫言するものである。「民は正しさのみでは生きてはゆけないのでございます。遊びを、楽しみを求めているのであります」これなども、甘いご時世としょっぱいを政(まつりごと)を、政治次元で上奏しているのである。
産業革命以降、サイエンスという語は、本来は、学問という意味であり、自然・社会・人文科学を包摂する用語でもあったものが、自然科学の専売特許用語、自然科学の代名詞、専有物ともなってきた。英文法用語の<完了形>というものに似ている。この“have+p.p.”という形態には、経験・継続・結果といった意味用法もあり、何も完了といったアスペクトだけに限らないのだ。また、ヨドバシカメラといいながら、カメラだけ販売している量販店ではない事実とも似ている。
これは、従来の文化を分母とし、文明を分子とする観念を、実証主義・合理主義・論理主義という理念で、逆転させてもきた。それは、天動説から地動説へのコペルニクス的転換ともいいうるもので、それに覚醒し、それに成功した列強が、19世紀の帝国主義の主役に躍り出たことでも明らかである。哲学は神学の下僕(はしため)とも言われた地位から、カントは、宗教から哲学を独立せしめた時から近代が、社会科学・人文科学も進化を遂げてもきた。それは、アングロサクソン民族が、英国から独立したアメリカの如きものでもあった。
特に、20世紀は文明が急激に発展した。21世紀は、まさしく、デジタルを“憲法”とした文明帝国の時代である。GAFAM帝国を概観するまでもなく、スマホ、いわゆるSNS社会が下部構造(プラットフォーム)ともなり、政治・経済というものを動かし、その国家、企業の命運を左右するまでになってきている。それは、自由、いや、便利・快適・効率性ともいっていい三概念である。これに背く、無視するは、市場退場、消滅の憂き目にあう時代でもあるということだ。その最先端は、生成AIでもあろうか?この神とも、皇帝ともいいえる文明の絶対者が、人間にあらゆる自由を授けてもきている昨今ではある。まるで古代ローマ帝国が、従来の多神教からキリスト教の一神教へと転換したように、デジタルの神に、全ての自由を与えられ、それで、その便利さ、快適さ、功利性というものが、自身の人生、生活というものを自由最優先と洗脳されかけているという実体なのである。古代ローマ帝国の市民をおとなしくさせておくモットー「パンとサーカス」これが、現代では、「ファーストフードとスマホ」でもあるのだ。こうした関係は、人間とペットの犬ともいいえる関係なのである。今年の文化功労者に選ばれ、将来的には、文化勲章も受賞されるであろうと予想もつく演劇家の野田秀樹の弁、「人が何かを受け止める順番は『感じる・考える・信じる』のはずなのに、最近は『考える』が抜け落ちて、『感じる・信じる』が直結しているのではないか」この鋭い指摘が、現代社会の時世を、東西を問わず、象徴しもいよう。この野田氏の文脈で言えば、文章、特に、小論文を書くとすれば、序論、本論、結論といった三段論法が、大学入試の小論文でいう、序論と結論でもOKという社会、入試問題の、奇妙奇天烈ともいえる模範的解答文であることに類する現況が到来しかけているのである。
現代は、科学、それもデジタルの恩恵により、中国やロシアといった独裁国を含み、ある意味、便利さ、快適さを錦の御旗として、どれほど“自由”というものを謳歌しているか、その“身体的自由さ”を人民、国民に与えさえすれば、精神的不自由さは、二の次でも構わない、少々目をつぶるという現実を習近平やプーチンが見抜いている現実だ。中国人にしろ、ロシア人にしろ、海外旅行は自由であるが、言論・思想統制という拘束(国家)からは自由(逃避)になれない。いや、トランプとて、狭義の意味で、同じやも知れない。「痩せたソクラテスより、肥った豚になれ」、この標語で、21世紀は政治が行われてもいる。それを電脳社会が、国民の外面から、内面から、がんじがらめにしている。数十年前、社員を捩って社畜という言葉が生まれたが、今や、国畜、いや、電畜の時代でもあろう。ここでであるが、ここに自由の対義語が不自由なのか、規律なのかという命題が浮上しもこよう。この命題は、「成功の反対は、失敗ではなく、妥協である」(木村政雄)の名言が浮上してもこよう。ここの観点から、次回、外面における危機、即ち、現代の地球温暖化には敏感なくせに、内面の危機、いわば、精神のデジタル化(0と1という二元論、また、白か黒かといった灰色という中庸を排除する空気)には無頓着な現代人について語ってもみたい。