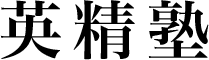コラム
"衣食足りて礼節を知る"&"小人閑居して不善をなす"
成功すると慢心になる、現状維持の守りに入る。自由を手に入れると放縦になる、分をわきまえなくなる。豊さを手に入れると、ものごとを上から目線ともなり、貧困の世界に疎遠ともなる。豊臣秀吉の晩年である。これらは、すべて、幸福の要素でもあり、その幸福の黄昏を警告する心得と自覚している者は、巡りくる不幸を、夜や冬のように考えるポジティブ思考を有している。また、再び昼や夏がくると諦観しもいる。人生はあざなえる縄の如しと、この言葉は集約していよう。
「人を見て法を説け」{オンライン授業やスマホ学習ではこれが叶わぬ!}とは、よく言ったものである。この言葉は、超進学校、標準校、問題校と、勉学の部類で括るならば、「学校の当たり前をやめた」は、後者二校では、あまり該当できない。生徒たちに自由を付与しても、その自由に自ら制限をかける規律というものを有する生徒が少ないからだ。この観点からすれば、自身に規律を持つ者、これが賢いメルクマールともなり、自身に規矩を有する者、これが偉い人物とも言い得る。これは、家庭においても、我が子にスマホやゲームを与えるべきか否か問題にも該当する。この点で、世の親御さんは、自身の子供を観る眼がいかに節穴の者が多いかの証明でもあろう。それは、その親自身が自らを、客観的に観る眼がないからでもある。
リビングでビールを飲みながら、野球中継を見て、我が子に「勉強しろ!」と言っても説得力はない。一方、親自身もテレビを消して、歴史小説などを静かに読む耽る傍らで「勉強しなさい!」と言えば、我が子も机に向かうというものだ。子は親の背を見て育つ典型的なケースである。
「衣食足りて礼節を知る」という格言と、「小人閑居して不善をなす」というものがあるが、この対極的な教訓は、社員、生徒、我が子に自由を与えて、それが吉と出るか、凶とでるか、その行方を占う上で、啓示的・暗示的である。
この<衣食>を<自由>に擬えてみよう、一方、<閑居>も<自由>と置き換えてみよう。すると、<自由>というものを身に付け、礼節を知るとは、その間に、規律という内発的理性という箍(たが)があってのことである。小人、いわば凡人、時に、愚者とは、これがない。この文脈で、ルソーは「子どもを不幸にするいちばん確実な方法はなにか、それをあなたは知っているだろうか。それは、いつでもなんでも手に入れられるようにしてやることだ」と語った真意が参考になる。ここに、自我が種ともなり、そこから発芽する規律という双葉すらない子どもに、その種を植え付けることも、いや、芽生えた段階で、その芽を雑草の如くに摘んでしまうバカ親への警告でもあろう。小人は、自由気ままにされた時、よくないことをしでかす、この「小人閑居して不善をなす」は、学校というトポスが、今や、学びの場ではなく、特に、小中の義務教育において、8時間から16時までの“託児所=日中によからぬことをしでかさないように繁華街から防衛する所”のような趣の場所になれさがった実状が、ものの見事に証明してもいよう。
糖尿病は、貧しい人に多いという言説を一昔耳にしたことがある。これなどは、一見すると、裕福層が、毎日、フレンチや鮨など高級料理を食しているせいで、むしろ彼らの方が多のでは?と疑問に思われるやもしれないが、現実は、そうではない。日本を含め先進国では、路上で餓死者はまず生まれない。よく、朝早く、工事現場に向かう肉体労働者が、コンビニでカップ麺と菓子パンを抱え、ワゴン車に乗り込む光景を目にする。また、昼時、またも、コンビニで菓子パンとカップ麺、もしくは、コンビニ弁当などを、工事現場で食す。晩は、居酒屋で焼酎やビールと焼き鳥なんぞを食する。また、家系ラーメンで満腹感を満たす。満腹感優先の食生活である。自己の空腹という不自由を蹴散らすのである。そのつけが、糖尿病として、我にふりかかってもくる。
また、欧米では、就職の面接で、肥満体質の人は、はねられるとも聞いた覚えがある。食生活における、自己管理ができていない人間とみなされるからだ。この点でも、孫正義や三木谷浩史などは、日ごろは、我々庶民同様、粗食であることは想像に難くない。健康管理からだ。ハリウッドセレブなども、ビーガンやベジタリアンが多いのもこうした事情から裏付けられる。
そうである。世のエスタブリッシュメントに限り、人も羨む成功、莫大な富、そうしたものを手にした者にかぎり、そこから派生する<自由>の諸刃の剣の怖さを認識しているのである。自由という豪華クルーザーに、規律という重し、それ相応の錨を装備してもいるのである。これがない凡人、愚者は、自由という大海原を彷徨い、台風の憂き目に遭い、難破座礁する、時に沈没する憂き目にあう。大海という自由の怖さを知らぬは、サルに近きホモサピエンスとも言い得よう。『ケータイを持ったサル』(2003年)や『スマホで馬鹿になる』(2014年)という本もあった。これは、世の半数以上の種族に該当する真実であろう。堀江貴文、落合陽一、ひろゆきなどは、こうした電子ツールには、飲み込まれず、超然として、デジタル器機に護身用の猛犬のように身辺警備させているに過ぎぬ。彼らを見て、デジタル居士となる。この三人をさかしらと幻想する者が、凡人であり、愚者でもある。大衆とは、オルテガにしろ、西部邁にしろ、こうした人種を指示しているである。先日逮捕された立花孝志やガーシーに扇動される大人たちでもある。
今や、多様性・個性優先で、生徒それぞれの教育が、デジタルツールもあいまって、花盛りである。しかし、こうした風潮は、一部の“お利口さん”には、該当するが、半数以上の少年少女には、適応しかねる方針・手法である。この点で、次回語ってみたいと思う。(つづく)
「人を見て法を説け」{オンライン授業やスマホ学習ではこれが叶わぬ!}とは、よく言ったものである。この言葉は、超進学校、標準校、問題校と、勉学の部類で括るならば、「学校の当たり前をやめた」は、後者二校では、あまり該当できない。生徒たちに自由を付与しても、その自由に自ら制限をかける規律というものを有する生徒が少ないからだ。この観点からすれば、自身に規律を持つ者、これが賢いメルクマールともなり、自身に規矩を有する者、これが偉い人物とも言い得る。これは、家庭においても、我が子にスマホやゲームを与えるべきか否か問題にも該当する。この点で、世の親御さんは、自身の子供を観る眼がいかに節穴の者が多いかの証明でもあろう。それは、その親自身が自らを、客観的に観る眼がないからでもある。
リビングでビールを飲みながら、野球中継を見て、我が子に「勉強しろ!」と言っても説得力はない。一方、親自身もテレビを消して、歴史小説などを静かに読む耽る傍らで「勉強しなさい!」と言えば、我が子も机に向かうというものだ。子は親の背を見て育つ典型的なケースである。
「衣食足りて礼節を知る」という格言と、「小人閑居して不善をなす」というものがあるが、この対極的な教訓は、社員、生徒、我が子に自由を与えて、それが吉と出るか、凶とでるか、その行方を占う上で、啓示的・暗示的である。
この<衣食>を<自由>に擬えてみよう、一方、<閑居>も<自由>と置き換えてみよう。すると、<自由>というものを身に付け、礼節を知るとは、その間に、規律という内発的理性という箍(たが)があってのことである。小人、いわば凡人、時に、愚者とは、これがない。この文脈で、ルソーは「子どもを不幸にするいちばん確実な方法はなにか、それをあなたは知っているだろうか。それは、いつでもなんでも手に入れられるようにしてやることだ」と語った真意が参考になる。ここに、自我が種ともなり、そこから発芽する規律という双葉すらない子どもに、その種を植え付けることも、いや、芽生えた段階で、その芽を雑草の如くに摘んでしまうバカ親への警告でもあろう。小人は、自由気ままにされた時、よくないことをしでかす、この「小人閑居して不善をなす」は、学校というトポスが、今や、学びの場ではなく、特に、小中の義務教育において、8時間から16時までの“託児所=日中によからぬことをしでかさないように繁華街から防衛する所”のような趣の場所になれさがった実状が、ものの見事に証明してもいよう。
糖尿病は、貧しい人に多いという言説を一昔耳にしたことがある。これなどは、一見すると、裕福層が、毎日、フレンチや鮨など高級料理を食しているせいで、むしろ彼らの方が多のでは?と疑問に思われるやもしれないが、現実は、そうではない。日本を含め先進国では、路上で餓死者はまず生まれない。よく、朝早く、工事現場に向かう肉体労働者が、コンビニでカップ麺と菓子パンを抱え、ワゴン車に乗り込む光景を目にする。また、昼時、またも、コンビニで菓子パンとカップ麺、もしくは、コンビニ弁当などを、工事現場で食す。晩は、居酒屋で焼酎やビールと焼き鳥なんぞを食する。また、家系ラーメンで満腹感を満たす。満腹感優先の食生活である。自己の空腹という不自由を蹴散らすのである。そのつけが、糖尿病として、我にふりかかってもくる。
また、欧米では、就職の面接で、肥満体質の人は、はねられるとも聞いた覚えがある。食生活における、自己管理ができていない人間とみなされるからだ。この点でも、孫正義や三木谷浩史などは、日ごろは、我々庶民同様、粗食であることは想像に難くない。健康管理からだ。ハリウッドセレブなども、ビーガンやベジタリアンが多いのもこうした事情から裏付けられる。
そうである。世のエスタブリッシュメントに限り、人も羨む成功、莫大な富、そうしたものを手にした者にかぎり、そこから派生する<自由>の諸刃の剣の怖さを認識しているのである。自由という豪華クルーザーに、規律という重し、それ相応の錨を装備してもいるのである。これがない凡人、愚者は、自由という大海原を彷徨い、台風の憂き目に遭い、難破座礁する、時に沈没する憂き目にあう。大海という自由の怖さを知らぬは、サルに近きホモサピエンスとも言い得よう。『ケータイを持ったサル』(2003年)や『スマホで馬鹿になる』(2014年)という本もあった。これは、世の半数以上の種族に該当する真実であろう。堀江貴文、落合陽一、ひろゆきなどは、こうした電子ツールには、飲み込まれず、超然として、デジタル器機に護身用の猛犬のように身辺警備させているに過ぎぬ。彼らを見て、デジタル居士となる。この三人をさかしらと幻想する者が、凡人であり、愚者でもある。大衆とは、オルテガにしろ、西部邁にしろ、こうした人種を指示しているである。先日逮捕された立花孝志やガーシーに扇動される大人たちでもある。
今や、多様性・個性優先で、生徒それぞれの教育が、デジタルツールもあいまって、花盛りである。しかし、こうした風潮は、一部の“お利口さん”には、該当するが、半数以上の少年少女には、適応しかねる方針・手法である。この点で、次回語ってみたいと思う。(つづく)