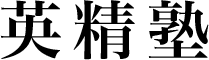コラム
規律という<型>から自由という<個性>が生まれる
権利と義務、当然ながら社会人として、国民として持つべき分別とやらである。前者に比重がかかる人間を、進歩派・革新派と呼び、後者を主張する人間を、保守派・守旧派とも呼ぶ。一般常識人は、この二つの比重の塩梅加減を弁えている人を言う。この権利ばかりを主張するアメリカの社会風潮に釘をさしたのが、ケネディ大統領の名演説の一節である。
芸術の面でも、序破急という世阿弥が述べた芸道の心得がある。また、守破離という利休が提唱した茶道の美の訓戒というものもある。これら三段階の序にしろ、守にしろ、まずは、基本ともいえる型の提唱である。この基礎・基盤の上にオリジナリティという苗木が生えてもくるという芸事における王道を説いたまでだ。この型を経ずして、個性を言い張っても、それは、デッサン力がなく、藝大に入学するようなものだ。私は、ピカソのような絵が描けるから藝大に入れてくれと喚く受験生のようなものだ。
一般社会人にしろ、芸術家にしろ、義務と序や守といた自己にとっては堅苦し、個というものをがんじがらめする律、いや、規律というものを前提にしての、自己を社会、その芸事の世界から自由にする個性というものが芽をだし始める、植物と同類の真理をいっているまでである。これは、書道という世界においても、楷書があって草書がある、草書から楷書のルートは不可能なのだ。これは、母国語を日本語とする日本人が、口語日本語文法をやるが、窮屈して、億劫なのと同じ感想を抱く事実に似ている。帰国子女が、日本に独特の英文法、いわゆる、学校文法を愚痴る、苦手とする事実も同様だ。アメリカンスクールから日本の、制服がある、校則も厳しい学校に転送するメンタルにも似ていよう。
ここにおいて、幼児、子供から少年少女にかけての、教育における規律か自由かといった命題が浮上してくる。
社会の多様化とSNS社会の到来、そして、グローバル化の波において、世界は一見自由になっているかに見える。それは、ある意味、錯覚に過ぎない。「それってあなたの感想ですよね」といったひろゆきの言説は、自由を放縦・気ままとする鎧であり、盾と矛ともなっている、その象徴なのだ。小学生から中高生にかけて、ほとんど規律という面で、無力化している学校という制度も、制服から校則にいたるまで、国是とも、社会の一般通念ともいいえる、自由と個性が、錦の御旗となっている趨勢なのである。集約していえば、従来は、学校の是と社会の是とは、生徒・学生という身分上、断絶してもいて当然であった。これが、社会の是というものが、幕末の日本に鎖国を放棄して開国させたように、学校の是とするような流れになっている現実がある。教育当局に見えない圧力がかかって、少子化と教師の無能化、そして、親御さんの高学歴化、教育のサービス産業化、こうした要素が複合汚染の如くに、社会の是と学校の是と同類のものへせよという風潮があるということなのだ。不登校生、ひきこもり生、クラーク国際学園やN高の台頭などは、こうした社会変化というものの生理的・心理的現象なのだ。この時代の潮流にうまく乗ったのが、工藤勇一氏の“学校の当たり前をやめた”である。キャチーで時代受けする。ある意味、学校の社会化を集約した言葉である。この言葉、令和の親の目線では、当然でもあろう。平成に中高を経た世代は、まだ、学校は、個を抑圧するというイメージを抱いてもいたからだ。彼らには、学校は、アンチの場所だった。それが我が子には、そうさせたくない心理も働いてもいよう。この工藤氏の言説を、国家レベルにまで上げれば、竹中平蔵をブレーンとした小泉構造改革にも比肩できようか。グローバル化と称しながら、アメリカンスタンダードを日本社会に導入したに過ぎぬ。持てる者、富める者は、その恩恵にあずかるが、そでない者は、敗者となる。できる生徒、能力ある生徒は、“学校の当たり前をやめた”の恩恵にはあずかれない。
子供は天才だ、子供の描く絵画はすばらしい!と岡本太郎なども、幼児から小学生の描く絵を絶賛する。これを、学校や社会が、その芽を摘んで、その個性を殺す教育をしていると指摘するものだ。羽仁進氏が設立した自由学園も同様である。
次回に詳しく述べることにするが、養老孟司氏も指摘していていることだが、人間は生まれてきた段階で、そもそも個性の塊で、地球上に60億人の個性があるという。その千差万別の個性では、社会、国家の秩序はもちろん、進化という文明や文化など発祥しなかたともいう。この個性の多様性を、ある意味画一化したことで人類は発展しもできたという。
次回の結論を言おう。個性を求めるは、人間社会の逆行であるともいう。この真実は、西南戦争における明治政府軍と西郷の薩摩軍でもあり、南北戦争における北軍と南軍といいえる真実などである。この定例を覆したのが、世界史上、アメリカ、中国、フランスにそれぞれ勝利したヴェトナムくらいなものである。
では、自由のほぼ同義ともいっていい、個性的であることは、結果であり、目的であってはいけないという私の説を語ってみたい。これは、オリジナリティといったものはない。それは幻想である。型という規律があって初めて、個性という自由が派生する、生まれてくるということなのだ。この文脈でいう、第二外国語を学ぶ、登頂するルートは、読み・書きがあって初めて、聞く・話すというスキルが完結するという英精塾のモットーとも同じである。
芸術の面でも、序破急という世阿弥が述べた芸道の心得がある。また、守破離という利休が提唱した茶道の美の訓戒というものもある。これら三段階の序にしろ、守にしろ、まずは、基本ともいえる型の提唱である。この基礎・基盤の上にオリジナリティという苗木が生えてもくるという芸事における王道を説いたまでだ。この型を経ずして、個性を言い張っても、それは、デッサン力がなく、藝大に入学するようなものだ。私は、ピカソのような絵が描けるから藝大に入れてくれと喚く受験生のようなものだ。
一般社会人にしろ、芸術家にしろ、義務と序や守といた自己にとっては堅苦し、個というものをがんじがらめする律、いや、規律というものを前提にしての、自己を社会、その芸事の世界から自由にする個性というものが芽をだし始める、植物と同類の真理をいっているまでである。これは、書道という世界においても、楷書があって草書がある、草書から楷書のルートは不可能なのだ。これは、母国語を日本語とする日本人が、口語日本語文法をやるが、窮屈して、億劫なのと同じ感想を抱く事実に似ている。帰国子女が、日本に独特の英文法、いわゆる、学校文法を愚痴る、苦手とする事実も同様だ。アメリカンスクールから日本の、制服がある、校則も厳しい学校に転送するメンタルにも似ていよう。
ここにおいて、幼児、子供から少年少女にかけての、教育における規律か自由かといった命題が浮上してくる。
社会の多様化とSNS社会の到来、そして、グローバル化の波において、世界は一見自由になっているかに見える。それは、ある意味、錯覚に過ぎない。「それってあなたの感想ですよね」といったひろゆきの言説は、自由を放縦・気ままとする鎧であり、盾と矛ともなっている、その象徴なのだ。小学生から中高生にかけて、ほとんど規律という面で、無力化している学校という制度も、制服から校則にいたるまで、国是とも、社会の一般通念ともいいえる、自由と個性が、錦の御旗となっている趨勢なのである。集約していえば、従来は、学校の是と社会の是とは、生徒・学生という身分上、断絶してもいて当然であった。これが、社会の是というものが、幕末の日本に鎖国を放棄して開国させたように、学校の是とするような流れになっている現実がある。教育当局に見えない圧力がかかって、少子化と教師の無能化、そして、親御さんの高学歴化、教育のサービス産業化、こうした要素が複合汚染の如くに、社会の是と学校の是と同類のものへせよという風潮があるということなのだ。不登校生、ひきこもり生、クラーク国際学園やN高の台頭などは、こうした社会変化というものの生理的・心理的現象なのだ。この時代の潮流にうまく乗ったのが、工藤勇一氏の“学校の当たり前をやめた”である。キャチーで時代受けする。ある意味、学校の社会化を集約した言葉である。この言葉、令和の親の目線では、当然でもあろう。平成に中高を経た世代は、まだ、学校は、個を抑圧するというイメージを抱いてもいたからだ。彼らには、学校は、アンチの場所だった。それが我が子には、そうさせたくない心理も働いてもいよう。この工藤氏の言説を、国家レベルにまで上げれば、竹中平蔵をブレーンとした小泉構造改革にも比肩できようか。グローバル化と称しながら、アメリカンスタンダードを日本社会に導入したに過ぎぬ。持てる者、富める者は、その恩恵にあずかるが、そでない者は、敗者となる。できる生徒、能力ある生徒は、“学校の当たり前をやめた”の恩恵にはあずかれない。
子供は天才だ、子供の描く絵画はすばらしい!と岡本太郎なども、幼児から小学生の描く絵を絶賛する。これを、学校や社会が、その芽を摘んで、その個性を殺す教育をしていると指摘するものだ。羽仁進氏が設立した自由学園も同様である。
次回に詳しく述べることにするが、養老孟司氏も指摘していていることだが、人間は生まれてきた段階で、そもそも個性の塊で、地球上に60億人の個性があるという。その千差万別の個性では、社会、国家の秩序はもちろん、進化という文明や文化など発祥しなかたともいう。この個性の多様性を、ある意味画一化したことで人類は発展しもできたという。
次回の結論を言おう。個性を求めるは、人間社会の逆行であるともいう。この真実は、西南戦争における明治政府軍と西郷の薩摩軍でもあり、南北戦争における北軍と南軍といいえる真実などである。この定例を覆したのが、世界史上、アメリカ、中国、フランスにそれぞれ勝利したヴェトナムくらいなものである。
では、自由のほぼ同義ともいっていい、個性的であることは、結果であり、目的であってはいけないという私の説を語ってみたい。これは、オリジナリティといったものはない。それは幻想である。型という規律があって初めて、個性という自由が派生する、生まれてくるということなのだ。この文脈でいう、第二外国語を学ぶ、登頂するルートは、読み・書きがあって初めて、聞く・話すというスキルが完結するという英精塾のモットーとも同じである。