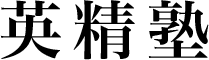コラム
"バカの壁"とは、国語や英語が苦手とする心根である
“バカの壁”とは、本も読まずして、国語ができるようになりたいと思う心根のことだ! つまり、興味や関心がない、時に、嫌いでさえある領域を武器にしようとするお目出度い部族の特性のことをいう。
これは、英語に関しても該当する。英単語の暗記が嫌だ、億劫だ!英文法も、小難しい、窮屈なルールだ、最小限度を覚えれば、英語は読み書きができるようになるはずだ、そう思い込んでいる種族のことでもある。
「人間の脳というのは、こういう順序、つまり出来るだけ多くの人に共通の了解事項を広げてゆく方向性をもって、いわゆる進歩を続けてきました。マスメディアの発達というのは、まさに「共通了解」の広がりそのものということになります」『バカの壁』42ページ
SNS社会の承認欲求の異常さを、イイね!多さに求めたり、YouTubeの隆盛の光景を概観すれば、すでに、25年以上も前に、大衆のバカの本質で、養老孟司氏が、それを言い当てている。灰汁の濃い自身の最小公倍数的主観は、他人に強要するが、自然界の空気や清水という、最大公倍数的客観というものを拒否する、まるで大国(アメリカ・中国・ロシア)のエゴが、一個人の脳内にまで同じドグマのようなものが集約されているというものが、今や、スマホでキャラが形成されつつある大衆という存在でもありましょう。このスマホという器機の登場以前に、世は、個性教育を是としてきたおぜん立てがあったのです。その、個性を絶対視するように、世の共通了解という世間という社会が、それぞれプラリベート空間で、<共通常識言語>を使用できない大衆を跋扈させてもきた。この予兆として、養老氏は、恐らく直観的に、バカの壁という衝立が、国民、社会人、学生と、スマホがそうさせる世界の到来を嗅ぎ分けてもいたのであろう。
「このところとみに、「個性」とか「自己」とか「独創的」とかを重宝する物言いが増えてきた。文部科学省も、ことあるごとに「個性」的な教育とか、「子供の個性を尊重する」とか、「独創性豊かな子供を作る」とか言っています。
しかし、これは、前述した「共通了解」を追求することが文明の自然な流れだとすれば、おかしな話です。明らかに矛盾していると言ってよい。多くの人にとって共通の了解事項を広げていく。これによって文明が発展してきたはずなのに、ところがもう片方では急に「個性」大切だとか何を言ってくるのは話しがおかしい。」『バカの壁』43ページ
小学生で、ろくすっぽ常用漢字も書けない、言葉遣いもなっていない、読書など全くしない。ゲームとアニメで、“感性”が育つと妄信している母親がいかに多いことか!好きなことだけ最優先で教育する母親である。我が子に、算数の、文章題や図形問題に必須の基礎計算もなおざり、掛け算九九程度があれば生きていけると、算数から数学への移行の意義など考慮の片隅にも置かない父親がどれほど目に付くことか!こうした初等教育における基礎学力ともいっていい共通了解を、考慮しない、丁度、政治家にもいる戦前教育・軍国教育のいいところを牽強付会的に主張して、憲法九条の理念を軽視、いや、無視して、自衛隊の軍事費を倍増する政策にも見えてこなくもない。断ってもおくが、私は平和憲法絶対死守派ではない。現在の、SNS社会で白痴化した大衆と、大局観を持たない{※古今東西の政治家が小粒になってきた証でもある}、浅慮の自民党政府では、憲法改正が改悪となることを憂いているだけである。
個性、個性とわめいても、所詮は、大衆の、個性なんぞは、我がまま、自己中の、それでいて我欲に駆動されたタコツボ型の主観性にすぎない。
ソクラテスの“無知の知”から、派生した格言である。
「愚者は、己を賢いと思うが、賢者は己が愚かなことを知っている。」(シェイクスピア)
「愚者は、経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」(ビスマルク)
賢者は、この危うき主観性に警鐘を鳴らしたに過ぎぬ。愚者は、自己に好都合の現実しか目に入らない、また、SNS社会で自己満足の対象しか興味がない種族である。
共通了解に裏打ちされぬ個性など、個性などではない。義務教育も受けずに、社会に放たれた12才の野生児に過ぎぬ。危険にして、蒙昧なる自我、タコツボ型主観性の皮を被った人間にすぎぬ。チンパンジーに幼児の服を着せているようなものだ。知性、教養、いや、良識、いやいや、常識というもの、それを有せずして、主観など幻想であり、大衆社会の蜃気楼のようなものだ。これが、ある意味、ヴァーチャルリアリティへと進む社会の実相でもあろう。この見事な実例が、初等教育から中等教育へ進む中学受験であり、中等教育から高等教育へ進む大学入試でもある。この、知の通過儀礼ともいえる関門、関所が、どんどん現今では、撤廃され、教育の主流、メインストリームもなっている。美大受験になぜ、デッサン力が必要なのか、医大は、大勢が推薦ではなく、今でも筆記試験がメインなのか?その観点から、一般入試を考える者が、マイナイーともなってきている現象も、個性が錦の御旗として、まかり通る、ある意味、バカでもOKシステムの導入と批判する者は、矢面に晒される。
「本来、意識というのは共通性を徹底的に追及するものなのです。その共通性を徹底的に確保するために、言語の論理と文化、伝統がある。
人間の脳の特に意識的な部分というのは、個人間の差異を無視して、同じにしよう、同じにしようとする性質を持っている。だから、言語から抽出された論理は、圧倒的な説得を持つ。論理に反するということはできない。」『バカの壁』48ページ
これは、弊著『反デジタル考』や本コラム欄でさんざん語ってきたことなのだが、ここでいう言語の論理、特に、論理というものが、中等教育で、どれだけ身につくことが困難であるか。映像主体のゲームとアニメの時代、無思考で日常を漠然をすごさせてくれるスマホの世界、こうしたデジタル帝国が、見えないヘゲモニーを有している生活の中で、論理といえば、プログラミングなどといった、コンピュータやAIとの人工言語の駆使能力のこと指すようになれ下がった。
小学校時代に、ほとんど読書もせず、常用漢字の半分以上も正確に読み書きもできにない生徒が、中学生になったところで、国語、特に現代文なんぞは、その3年間、小学校の国語の負の遺産を帳消しにする程度が関の山。そした中学生が、高校生になっても、大学入試の国公立の二次の現代文や、MARCHレベルの現代文には、苦手意識が終生つきまとうという宿命を有する、それが私になりの、国語という教科の真実である。“論理エンジン”で一世を風靡した出口汪氏の参考書を学んでも、林修氏の旧7帝大対象の現代文講座を受講しても、国語放棄派の私立理科系の受験生は当然のこと、国語苦手派の私立文系の受験生ですら、現代文の読解、いわば、論理の習得なんぞは、そらく、7割以上は、バカの壁を有してるがゆえに、かちかち山の泥船ともあいなる運命は、商売柄、教育産業側の者からはでてこない。国語という教科の講師であれば、あるほど、ある意味、新興宗教の教祖的存在の色彩が強くもなりがちであるから。これは、昭和一桁生まれの、英語教育など全くやらなかった少女時代を過ごした70歳の祖母が、家族と一緒に、ニューヨークに移住しても、生涯、英字新聞から英語小説など、読みこなせない境涯に似ている。こうした高校の現代文の論性の習得は、困難度において同次元でもあるということだ。
これは、英語に関しても該当する。英単語の暗記が嫌だ、億劫だ!英文法も、小難しい、窮屈なルールだ、最小限度を覚えれば、英語は読み書きができるようになるはずだ、そう思い込んでいる種族のことでもある。
「人間の脳というのは、こういう順序、つまり出来るだけ多くの人に共通の了解事項を広げてゆく方向性をもって、いわゆる進歩を続けてきました。マスメディアの発達というのは、まさに「共通了解」の広がりそのものということになります」『バカの壁』42ページ
SNS社会の承認欲求の異常さを、イイね!多さに求めたり、YouTubeの隆盛の光景を概観すれば、すでに、25年以上も前に、大衆のバカの本質で、養老孟司氏が、それを言い当てている。灰汁の濃い自身の最小公倍数的主観は、他人に強要するが、自然界の空気や清水という、最大公倍数的客観というものを拒否する、まるで大国(アメリカ・中国・ロシア)のエゴが、一個人の脳内にまで同じドグマのようなものが集約されているというものが、今や、スマホでキャラが形成されつつある大衆という存在でもありましょう。このスマホという器機の登場以前に、世は、個性教育を是としてきたおぜん立てがあったのです。その、個性を絶対視するように、世の共通了解という世間という社会が、それぞれプラリベート空間で、<共通常識言語>を使用できない大衆を跋扈させてもきた。この予兆として、養老氏は、恐らく直観的に、バカの壁という衝立が、国民、社会人、学生と、スマホがそうさせる世界の到来を嗅ぎ分けてもいたのであろう。
「このところとみに、「個性」とか「自己」とか「独創的」とかを重宝する物言いが増えてきた。文部科学省も、ことあるごとに「個性」的な教育とか、「子供の個性を尊重する」とか、「独創性豊かな子供を作る」とか言っています。
しかし、これは、前述した「共通了解」を追求することが文明の自然な流れだとすれば、おかしな話です。明らかに矛盾していると言ってよい。多くの人にとって共通の了解事項を広げていく。これによって文明が発展してきたはずなのに、ところがもう片方では急に「個性」大切だとか何を言ってくるのは話しがおかしい。」『バカの壁』43ページ
小学生で、ろくすっぽ常用漢字も書けない、言葉遣いもなっていない、読書など全くしない。ゲームとアニメで、“感性”が育つと妄信している母親がいかに多いことか!好きなことだけ最優先で教育する母親である。我が子に、算数の、文章題や図形問題に必須の基礎計算もなおざり、掛け算九九程度があれば生きていけると、算数から数学への移行の意義など考慮の片隅にも置かない父親がどれほど目に付くことか!こうした初等教育における基礎学力ともいっていい共通了解を、考慮しない、丁度、政治家にもいる戦前教育・軍国教育のいいところを牽強付会的に主張して、憲法九条の理念を軽視、いや、無視して、自衛隊の軍事費を倍増する政策にも見えてこなくもない。断ってもおくが、私は平和憲法絶対死守派ではない。現在の、SNS社会で白痴化した大衆と、大局観を持たない{※古今東西の政治家が小粒になってきた証でもある}、浅慮の自民党政府では、憲法改正が改悪となることを憂いているだけである。
個性、個性とわめいても、所詮は、大衆の、個性なんぞは、我がまま、自己中の、それでいて我欲に駆動されたタコツボ型の主観性にすぎない。
ソクラテスの“無知の知”から、派生した格言である。
「愚者は、己を賢いと思うが、賢者は己が愚かなことを知っている。」(シェイクスピア)
「愚者は、経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」(ビスマルク)
賢者は、この危うき主観性に警鐘を鳴らしたに過ぎぬ。愚者は、自己に好都合の現実しか目に入らない、また、SNS社会で自己満足の対象しか興味がない種族である。
共通了解に裏打ちされぬ個性など、個性などではない。義務教育も受けずに、社会に放たれた12才の野生児に過ぎぬ。危険にして、蒙昧なる自我、タコツボ型主観性の皮を被った人間にすぎぬ。チンパンジーに幼児の服を着せているようなものだ。知性、教養、いや、良識、いやいや、常識というもの、それを有せずして、主観など幻想であり、大衆社会の蜃気楼のようなものだ。これが、ある意味、ヴァーチャルリアリティへと進む社会の実相でもあろう。この見事な実例が、初等教育から中等教育へ進む中学受験であり、中等教育から高等教育へ進む大学入試でもある。この、知の通過儀礼ともいえる関門、関所が、どんどん現今では、撤廃され、教育の主流、メインストリームもなっている。美大受験になぜ、デッサン力が必要なのか、医大は、大勢が推薦ではなく、今でも筆記試験がメインなのか?その観点から、一般入試を考える者が、マイナイーともなってきている現象も、個性が錦の御旗として、まかり通る、ある意味、バカでもOKシステムの導入と批判する者は、矢面に晒される。
「本来、意識というのは共通性を徹底的に追及するものなのです。その共通性を徹底的に確保するために、言語の論理と文化、伝統がある。
人間の脳の特に意識的な部分というのは、個人間の差異を無視して、同じにしよう、同じにしようとする性質を持っている。だから、言語から抽出された論理は、圧倒的な説得を持つ。論理に反するということはできない。」『バカの壁』48ページ
これは、弊著『反デジタル考』や本コラム欄でさんざん語ってきたことなのだが、ここでいう言語の論理、特に、論理というものが、中等教育で、どれだけ身につくことが困難であるか。映像主体のゲームとアニメの時代、無思考で日常を漠然をすごさせてくれるスマホの世界、こうしたデジタル帝国が、見えないヘゲモニーを有している生活の中で、論理といえば、プログラミングなどといった、コンピュータやAIとの人工言語の駆使能力のこと指すようになれ下がった。
小学校時代に、ほとんど読書もせず、常用漢字の半分以上も正確に読み書きもできにない生徒が、中学生になったところで、国語、特に現代文なんぞは、その3年間、小学校の国語の負の遺産を帳消しにする程度が関の山。そした中学生が、高校生になっても、大学入試の国公立の二次の現代文や、MARCHレベルの現代文には、苦手意識が終生つきまとうという宿命を有する、それが私になりの、国語という教科の真実である。“論理エンジン”で一世を風靡した出口汪氏の参考書を学んでも、林修氏の旧7帝大対象の現代文講座を受講しても、国語放棄派の私立理科系の受験生は当然のこと、国語苦手派の私立文系の受験生ですら、現代文の読解、いわば、論理の習得なんぞは、そらく、7割以上は、バカの壁を有してるがゆえに、かちかち山の泥船ともあいなる運命は、商売柄、教育産業側の者からはでてこない。国語という教科の講師であれば、あるほど、ある意味、新興宗教の教祖的存在の色彩が強くもなりがちであるから。これは、昭和一桁生まれの、英語教育など全くやらなかった少女時代を過ごした70歳の祖母が、家族と一緒に、ニューヨークに移住しても、生涯、英字新聞から英語小説など、読みこなせない境涯に似ている。こうした高校の現代文の論性の習得は、困難度において同次元でもあるということだ。