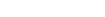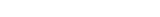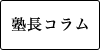カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2026年2月 (2)
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (3)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
コラム
⑪質か量か?~最終回~
初等教育、いわゆる、小学校時代は、思春期前の従順な気質も預かってか、量と数で、徹底的に帰納法で、教え叩き込む。勿論、当世風の考える授業やアクティブラーニングなど、二の次で構わない。中学受験をする、それも、超難関校をめざす六年生は、そうした授業の初歩も手ほどきせねばならないが。大方、人生で必要な基礎知識を、三角和雄流に“量があって質がある”を自覚させて小学生に対峙する。これしかない。但し、彼らに対する授業のモットーは、“楽しく・面白く”を忘れてはいけない。
次に、中等教育の段になるのだが、この時期は、まさしく、思春期ともいえる厄介な年ごろである。反抗期も重なって、我がまま根性が台頭してくる。学びにおける、こましゃくれた“大人”の精神とやらである。未熟にもかかわらず、いっぱしの大人となった気分でいる、そうした態度にでてくる。また、小学生とは異質の、別次元の、自己に打ち克つ必要性の自覚の濃淡が学力の命運を左右する。“克己性の偏差値”が、学力・受験の明暗を分ける。これは、小学校5~6年生で、これができている少年少女が、開成や桜蔭など合格する。彼らは、メンタルの確立が早い連中でもあるということだ。勿論、こうした気質を陶冶するのは、学校以前に親の役割であるのは言うまでもない。こうしたメンタルが中学生で芽生える連中は、翠嵐や湘南に合格する。野村克也が、ドラフトで入団した、野球エリート組に吐く言葉である。「人間的成長なくして技術の進歩なし」天才(超一流アスリート)とまでいうまい、秀才(一流アスリート)とは、これができている種族でもある。
しかし、中高生ともなれば、私の十代後半も含め、準秀才以下は、精神の揺れ、勉学以外の様々な誘惑に負けて、本来とるべき<時間と手間>というものをなおざりにしてしまう悪しき気質が台頭してもくる。これを名将野村は、「敵は我に在り」とも言い当てている。この敵を“仲間”と勘違いもする。「真実の言葉は耳に痛い」、その真意がわからないのである。
こうした準秀才ともいえる連中のために、教師、講師は、量や数という小学生時代とは、異質の学びの行程があると、教え子に実感させるのである。これができる英語教師とは、ネイティブや帰国子女から英語を教わる、英語嫌いになる、悪しき行程、一方、12才から英語を学んだ準ジャパの英語講師、しかし、苦心惨憺の末、英語道ともいってプロセスと経て教師となった者から英語を教わる、英語好きになる良き行程、この二者に典型的に、教え子の英語好きと英語の実力の違い現れる。その詳細は、弊著『英語教師は<英語>ができなくてもよい!』をお読みいただくと、その疑問点が氷解する。氷解しない人は、この表題のパラドクスが理解できない御仁でもある。
そうである、中等教育においては、その教科の本質、それを巧みに、面白く教えること、そして、そのコアから、その教科の定着を図る上でも、量と数を推奨し、内発的帰納法へと誘導する。これが、<帰納法を演繹法のはしためとする手法>なのだ。これは、具体的には、書道における、楷書を徹敵的に修練し、そして、その後、草書へと移行する手順とも似てもいる。また、英語における、読み・書き・話し・聞くの、まず、読み・書きを徹敵にやる{※実は、これが間違っていると主張する派が実に多い!}、それが確立した時点で、話し・聞くへと移行する。これは、英語のプロの指導者には、邪道と思われるが、現場で、我流ながら実証済みでもある。詳しくは、弊著『英語教師は<英語>ができなくてもよい!』を参照されたい。
「マイナス面に打ち勝てる知性、自分自身をコントロールする力を同時に成長させていかないと経験を活かし切るのは難しくなってしまう」(羽生善治)
※イギリス経験論=帰納法
では、高等教育ともいえる、大学時代にはこの帰納法と演繹法にどう向き合うべきなのか?そういった問いが浮上してくる。
まず、理系に関しては、実験という現場第一主義教育があるので、失敗につぐ失敗で、帰納法の本質に自覚せざるを得ない環境に置かれる。精神も大人になり、量や数という、失敗と成功の螺旋階段を上ってゆく営みを苦ともしない自我が芽生える。自身が成長してゆくという真実に、そうした自覚も発芽してくるからだ。理系には、治験で有名なように、帰納法こそ、研究と同義であるという気構えが、理系大学生の絶対条件ともなる。
では、文系に関してはどうであろうか?特に、文系の主要科目でもある英語、国語、社会などは、私流の<帰納法をはしためとする演繹法>で学んできた、比較的、勉強ができる学生の弱点、いわば、中等教育から高等教育へ移行する際の“諸刃の剣”ともなってしまうことが、玉に瑕ともなる。
平成後半から令和にかけての、例えば、早稲田大学の文系の学生はよく勉強するという。そして、昭和世代の5~60代のお父さん連中からは考えられないことだが、無遅刻無欠席の学生が、大多数を占めるともいう。昔の早稲田色が、ガラッと変わってしまった。こうした現象は、ある意味、「日本の大学は入るのが難しいが出るのは易しい」という言説から一種、欧米化してもいるのであろう。但し、断ってもおくが、令和の日本の大学に関しては、「日本の大学は(推薦で)入るは易しいし、出るのはもっと易しい」という点を見落としてはいけない。文系(例えば、慶應大学の英文科)でも、卒論コースから、ゼミに毎回出席し、レポートを提出するコース選択の学生が増えてもいるという現象も、大学受験による一発勝負から指定校推薦・総合選抜などへシフトしていることとパラレルの関係にあるともいえよう。危険や苦難を回避し、次段階へ進もうとする精神のことである。
こうした現象は、大学の高校化であると指摘することができよう。昭和の高卒が令和の大卒である教育観である。その証拠に、聞くところによると、現今の大学生は、「今週のゼミは、課題、宿題はないんですか?」と聞いてくるともいう。昭和の大学生からすると殊勝な心持ともいえる。だが、一方で、こうでもある。「これらの本は、図書館で借りるなり、是非読んでおくように、読んでおくといいですよう」というゼミで、教授はこのような言葉を発するようである。彼らは、宿題、課題はしっかりやってもくる。だが、授業中に推薦した、そうした書籍や名著の類を読んでおくようにとアドヴァイスしても、ゼミ生20人にうち1人も読んでいる学生はいなかったという現実、これは、大学の高校化、また、専門学校化とも、文系に関しては言い得る現象である。大学という4年は、きちんと単位を取り、無事に4年で卒業して、大手、有名企業へとドッキングすればいい、そういった学びのコスパ・タイパの顕れでもあろうか。余計な学びはしない、つまり、教養というものは無縁なのだ。
こうした文系学生気質は、当世の予備校・スタサプ・昭和に比べ格段に解りやすく、丁寧で、カラフルな参考書などが、高校生の学力の背を押してもいる。だが、こうした現象は、私のいう、<帰納法をはしためとした演繹法>による受験の勝ち組なのである。この、“効率的”な手法が、大学生にまで尾を引くのである。
ここで脱皮していないのが、大方の文系学生の悪しき気質なのである。
「高校時代は、小さな完成品より、大きな未完成品を作る時代だ」(阿川弘之)
大学時代も、小さな完成品を作ろうとする、また、高校時代の大きな未完成品には、目もくれず、そのままでほったらかしで大学4年を通りすぎてしまうのである。これぞ、大学生が、教授が進める本、高校時代に、倫政、国語・歴史などで耳にした古今東西の名著を読まない態度ともいいえる。
ここでも、あの野村の箴言が、浮上してくる。「人間的成長なくして技術の進歩なし」これは、アマ(中等教育)からプロ(高等教育)へ移行したアスリート(学生)への進言である。これを、勉強から学問へとスライドする、高校生から大学生のメンタルにも言い得る真理である。
受動的演繹法(中等教育)を武器にそこから派生する、たやすいい帰納法、こらから、能動的演繹法(高等教育)から困難な帰納法(学問の本道・科学の実相)へ、学びの革命、知の精神の脱皮を起こさねばならないという強烈な自覚が必要なのだ。この謂いの、メルクマールは、「東大までの人、東大からの人」という言葉にも集約されてもいよう。
大学時代は、自らの問い・社会への課題を見つけ、それへの方策・解決策へと波風のない入り江・湾から大海原へ出向してゆく帆船の出航(端緒)なのである。高等教育は、海図などない、自らが、思考錯誤、仮説から検証というプロセスを経て、自身の核・コア・本質を見出だしてもゆく航海(学問)であるとの自覚がない人が多いようだ。どうも、中等教育という答えのある、生温い、答えのある世界から答えなどない、分からない厳しい世界へと、20歳前後で気づかずに、アルコールランプ上の心地よいビーカーの中のカエルが、茹でカエルになってしまうことに類する。そうした“茹でカエル”が社会に出て行っていることが日本の経済の低迷とも深層でつながっているように思えて仕方がない。
次に、中等教育の段になるのだが、この時期は、まさしく、思春期ともいえる厄介な年ごろである。反抗期も重なって、我がまま根性が台頭してくる。学びにおける、こましゃくれた“大人”の精神とやらである。未熟にもかかわらず、いっぱしの大人となった気分でいる、そうした態度にでてくる。また、小学生とは異質の、別次元の、自己に打ち克つ必要性の自覚の濃淡が学力の命運を左右する。“克己性の偏差値”が、学力・受験の明暗を分ける。これは、小学校5~6年生で、これができている少年少女が、開成や桜蔭など合格する。彼らは、メンタルの確立が早い連中でもあるということだ。勿論、こうした気質を陶冶するのは、学校以前に親の役割であるのは言うまでもない。こうしたメンタルが中学生で芽生える連中は、翠嵐や湘南に合格する。野村克也が、ドラフトで入団した、野球エリート組に吐く言葉である。「人間的成長なくして技術の進歩なし」天才(超一流アスリート)とまでいうまい、秀才(一流アスリート)とは、これができている種族でもある。
しかし、中高生ともなれば、私の十代後半も含め、準秀才以下は、精神の揺れ、勉学以外の様々な誘惑に負けて、本来とるべき<時間と手間>というものをなおざりにしてしまう悪しき気質が台頭してもくる。これを名将野村は、「敵は我に在り」とも言い当てている。この敵を“仲間”と勘違いもする。「真実の言葉は耳に痛い」、その真意がわからないのである。
こうした準秀才ともいえる連中のために、教師、講師は、量や数という小学生時代とは、異質の学びの行程があると、教え子に実感させるのである。これができる英語教師とは、ネイティブや帰国子女から英語を教わる、英語嫌いになる、悪しき行程、一方、12才から英語を学んだ準ジャパの英語講師、しかし、苦心惨憺の末、英語道ともいってプロセスと経て教師となった者から英語を教わる、英語好きになる良き行程、この二者に典型的に、教え子の英語好きと英語の実力の違い現れる。その詳細は、弊著『英語教師は<英語>ができなくてもよい!』をお読みいただくと、その疑問点が氷解する。氷解しない人は、この表題のパラドクスが理解できない御仁でもある。
そうである、中等教育においては、その教科の本質、それを巧みに、面白く教えること、そして、そのコアから、その教科の定着を図る上でも、量と数を推奨し、内発的帰納法へと誘導する。これが、<帰納法を演繹法のはしためとする手法>なのだ。これは、具体的には、書道における、楷書を徹敵的に修練し、そして、その後、草書へと移行する手順とも似てもいる。また、英語における、読み・書き・話し・聞くの、まず、読み・書きを徹敵にやる{※実は、これが間違っていると主張する派が実に多い!}、それが確立した時点で、話し・聞くへと移行する。これは、英語のプロの指導者には、邪道と思われるが、現場で、我流ながら実証済みでもある。詳しくは、弊著『英語教師は<英語>ができなくてもよい!』を参照されたい。
「マイナス面に打ち勝てる知性、自分自身をコントロールする力を同時に成長させていかないと経験を活かし切るのは難しくなってしまう」(羽生善治)
※イギリス経験論=帰納法
では、高等教育ともいえる、大学時代にはこの帰納法と演繹法にどう向き合うべきなのか?そういった問いが浮上してくる。
まず、理系に関しては、実験という現場第一主義教育があるので、失敗につぐ失敗で、帰納法の本質に自覚せざるを得ない環境に置かれる。精神も大人になり、量や数という、失敗と成功の螺旋階段を上ってゆく営みを苦ともしない自我が芽生える。自身が成長してゆくという真実に、そうした自覚も発芽してくるからだ。理系には、治験で有名なように、帰納法こそ、研究と同義であるという気構えが、理系大学生の絶対条件ともなる。
では、文系に関してはどうであろうか?特に、文系の主要科目でもある英語、国語、社会などは、私流の<帰納法をはしためとする演繹法>で学んできた、比較的、勉強ができる学生の弱点、いわば、中等教育から高等教育へ移行する際の“諸刃の剣”ともなってしまうことが、玉に瑕ともなる。
平成後半から令和にかけての、例えば、早稲田大学の文系の学生はよく勉強するという。そして、昭和世代の5~60代のお父さん連中からは考えられないことだが、無遅刻無欠席の学生が、大多数を占めるともいう。昔の早稲田色が、ガラッと変わってしまった。こうした現象は、ある意味、「日本の大学は入るのが難しいが出るのは易しい」という言説から一種、欧米化してもいるのであろう。但し、断ってもおくが、令和の日本の大学に関しては、「日本の大学は(推薦で)入るは易しいし、出るのはもっと易しい」という点を見落としてはいけない。文系(例えば、慶應大学の英文科)でも、卒論コースから、ゼミに毎回出席し、レポートを提出するコース選択の学生が増えてもいるという現象も、大学受験による一発勝負から指定校推薦・総合選抜などへシフトしていることとパラレルの関係にあるともいえよう。危険や苦難を回避し、次段階へ進もうとする精神のことである。
こうした現象は、大学の高校化であると指摘することができよう。昭和の高卒が令和の大卒である教育観である。その証拠に、聞くところによると、現今の大学生は、「今週のゼミは、課題、宿題はないんですか?」と聞いてくるともいう。昭和の大学生からすると殊勝な心持ともいえる。だが、一方で、こうでもある。「これらの本は、図書館で借りるなり、是非読んでおくように、読んでおくといいですよう」というゼミで、教授はこのような言葉を発するようである。彼らは、宿題、課題はしっかりやってもくる。だが、授業中に推薦した、そうした書籍や名著の類を読んでおくようにとアドヴァイスしても、ゼミ生20人にうち1人も読んでいる学生はいなかったという現実、これは、大学の高校化、また、専門学校化とも、文系に関しては言い得る現象である。大学という4年は、きちんと単位を取り、無事に4年で卒業して、大手、有名企業へとドッキングすればいい、そういった学びのコスパ・タイパの顕れでもあろうか。余計な学びはしない、つまり、教養というものは無縁なのだ。
こうした文系学生気質は、当世の予備校・スタサプ・昭和に比べ格段に解りやすく、丁寧で、カラフルな参考書などが、高校生の学力の背を押してもいる。だが、こうした現象は、私のいう、<帰納法をはしためとした演繹法>による受験の勝ち組なのである。この、“効率的”な手法が、大学生にまで尾を引くのである。
ここで脱皮していないのが、大方の文系学生の悪しき気質なのである。
「高校時代は、小さな完成品より、大きな未完成品を作る時代だ」(阿川弘之)
大学時代も、小さな完成品を作ろうとする、また、高校時代の大きな未完成品には、目もくれず、そのままでほったらかしで大学4年を通りすぎてしまうのである。これぞ、大学生が、教授が進める本、高校時代に、倫政、国語・歴史などで耳にした古今東西の名著を読まない態度ともいいえる。
ここでも、あの野村の箴言が、浮上してくる。「人間的成長なくして技術の進歩なし」これは、アマ(中等教育)からプロ(高等教育)へ移行したアスリート(学生)への進言である。これを、勉強から学問へとスライドする、高校生から大学生のメンタルにも言い得る真理である。
受動的演繹法(中等教育)を武器にそこから派生する、たやすいい帰納法、こらから、能動的演繹法(高等教育)から困難な帰納法(学問の本道・科学の実相)へ、学びの革命、知の精神の脱皮を起こさねばならないという強烈な自覚が必要なのだ。この謂いの、メルクマールは、「東大までの人、東大からの人」という言葉にも集約されてもいよう。
大学時代は、自らの問い・社会への課題を見つけ、それへの方策・解決策へと波風のない入り江・湾から大海原へ出向してゆく帆船の出航(端緒)なのである。高等教育は、海図などない、自らが、思考錯誤、仮説から検証というプロセスを経て、自身の核・コア・本質を見出だしてもゆく航海(学問)であるとの自覚がない人が多いようだ。どうも、中等教育という答えのある、生温い、答えのある世界から答えなどない、分からない厳しい世界へと、20歳前後で気づかずに、アルコールランプ上の心地よいビーカーの中のカエルが、茹でカエルになってしまうことに類する。そうした“茹でカエル”が社会に出て行っていることが日本の経済の低迷とも深層でつながっているように思えて仕方がない。
2025年5月 6日 18:44