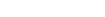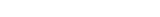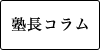カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2026年2月 (4)
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (3)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > ③自然・アナログ・デジタル~孫正義と森岡毅~
コラム
③自然・アナログ・デジタル~孫正義と森岡毅~
「AIは知のゴールドラッシュである」と孫正義は語っている。これは、企業レベル、国家レベルの、サバイバル競争の文明論の文脈においてである。また、一個人、一人の人間がたかだか人生90年の過程で、この呪文に執着するは、自己の、ある意味不幸を招く遠因ともいいえる。この弁は、カリスマ経営者のロマンチズムの現れとさえ言ってもいい。
七月末に開園した、沖縄のテーマパーク、ジャングリアがメディア等で話題になっている。USJを、西武園ゆうえんちを、それぞれV字回復させた、マーケティング会社“刀”のCEOであり、現代日本の最強マーケターでもある森岡毅が、様々な紆余曲折の末、完成にこぎつけた、沖縄の地域おこし、また、アジア各国から外貨を稼ぐ、日本のテーマパークを狙ったものだ。これからの日本のアミューズメント業界の試金石にもなる娯楽施設である。
あの1847年において、カリフォルニアで有名なゴールドラッシュで一攫千金を狙ったフォーティーナイナーズではなく、彼らを利用した、リーバイスというジーンズで、鉱山労働者の作業着を製作、販売した人物、リーバイ・ストラウスが、一番儲けたというエピソードを持ち出すまでもなく、金鉱というAIではなく、それに開発を凌ぐエンジニア、人間をビジネスの対象とした、テーマパークという“ジーンズ”という捉え方もある。ヴァーチャルというデジタルに疲れ、嫌気がさし、うんざりする人間を、リアルというアナログで癒しを与え、生の充実感を与えるアナログ・自然に、“商機”を見出だす術もあるということを言いたいに過ぎぬ。
国家、企業レベルでAI(幕政改革)に血眼になるは、その長(将軍)、そして、その幹部クラス(老中たち)、そしてその部下(旗本)くらいのものであろう。さらにその下の従業員(御家人)は、組織内で、AIというデジタルに四六時中向き合う中、私生活では、アナログの心的癒し(歌舞伎・相撲・遊郭・浮世絵など)を求めるのが、人間の性、生物としての常というものである。
スマホに24時間支配されているZ世代の少女は、リアルを求めてTDLまたUSJに足繁く通うリピーターなのだ。また、スポティファイなどで、サブスクとやらも加わって、携帯フォンで、アンドロイド系音楽に夢中になっても、やはり、AdoやYOASOBIなどのライブは超満員なのだ。デジタルで満たされぬ欲求、無意識なる欲求不満の顕れ行為である。
AIの進化により、どれほど、人間の生活は便利、快適になろうとも、その根源のデジタルでは、到底満たされぬ精神的領域というものがある。これが、生物としての証、人間の譲れぬ、非日常の、会社外、学校外における、人間の余暇・娯楽・趣味というもの“最終砦”でもある。ロジェ・カイヨワの『遊びと人間』を換骨奪胎して、“アナログと人間”とも言い得ると主張したいのである。生の体験、リアルの経験といったものだ。ここに、自然、アナログという存在理由がある。その微少なる傾向として、フィルムカメラの静かなブームとやらが挙げられよう。レコードやカセットテープは当然、山下達郎に典型的に見かけられるように、アナログ音楽の復興が近年、とみに有名である。
あの森岡毅が、西武園ゆうえんちを立て直すコンセプトして、TDLの真逆、レトロ感を全面に打ち出して、V字回復させた事例も、こうした彼の嗅覚がそうさせもしたのであろう。今般のジャングリアは、沖縄の自然というものを最大限活用し、東京や大阪のテーマパークでは及びもつかない、不可能なアトラクション満載の企画を実現された模様だ。まだ、このジャングリアが成功するか否かは不明だが、大いに勝算はありえよう。
親たちはもちろん、その子供たちも、日常から非日常にいたるまで、デジタルの空気、環境の中に置かれている。それに馴染んで、幸福感を感じる種族はそれでもよしとしよう。しかし、ディズニーランドのように、内面、システムなどは、デジタルガチガチでありながらも、リアルのミッキーとハグができたり、キャストのもてなしに感服したり、エレクトリカルパレードに魅了されたりする。肉体を通す刺激、興奮は、現今のアミューズメントパークの独壇場でもあろう。これは、リアル、アナログの魅力でもある。世の社会人、学生は、日常では、ほぼデジタルの空間に投げ入れられる。そこに、居らざるをえぬのある。そのデジタルという場から脱したいという生物的欲求が、TDL、USJ、そしてライブへと駆り立ててもいる最大の要因なのだ。
デジタルは、人間にとって完全、完璧なものではない。この永久に不備の側面を、アナログが埋めてもくれる。これは、未来、AIは、埋めることが永遠にできぬと、私は賭けよう。できたとすれば、それこそが、人間というホモサピエンスの死を意味する。これを養老孟司氏は、“AI支配でヒトは死ぬ!”~『Ai支配でヒトは死ぬ。』(ビジネス社)~とも語ったわけである。
嗅覚鋭いマーケター森岡毅は、デジタルのカウンターではなく、アナログのカウンターでもあった自然というものを、今回全面に戦略として打ち出してもきた。このジャングリアが頓挫するとすれば、それは、ヒトの内面にある、本来的人間性の衰退ともいえなくもない。それは、地球温暖化同様に、もう、人間の自然性、アナログ性、いや、文明社会にマグマのように内在している“野生”といったものが逆戻りできない段階に侵食され始めた段階に入っている証左とも言い得よう。
ゴールドラシュを先導する、唱道する孫正義に、大衆はつられて、西へ、西へ{デジタルへデジタルへ、人間の没落}と向かいはするが、そのデジタルブームの陰で、東へ、東へ{アナログ性、自然性の復興}に目をつけた森岡毅のような存在は、リーバイス・ストラウスとも暗喩できるのである。
七月末に開園した、沖縄のテーマパーク、ジャングリアがメディア等で話題になっている。USJを、西武園ゆうえんちを、それぞれV字回復させた、マーケティング会社“刀”のCEOであり、現代日本の最強マーケターでもある森岡毅が、様々な紆余曲折の末、完成にこぎつけた、沖縄の地域おこし、また、アジア各国から外貨を稼ぐ、日本のテーマパークを狙ったものだ。これからの日本のアミューズメント業界の試金石にもなる娯楽施設である。
あの1847年において、カリフォルニアで有名なゴールドラッシュで一攫千金を狙ったフォーティーナイナーズではなく、彼らを利用した、リーバイスというジーンズで、鉱山労働者の作業着を製作、販売した人物、リーバイ・ストラウスが、一番儲けたというエピソードを持ち出すまでもなく、金鉱というAIではなく、それに開発を凌ぐエンジニア、人間をビジネスの対象とした、テーマパークという“ジーンズ”という捉え方もある。ヴァーチャルというデジタルに疲れ、嫌気がさし、うんざりする人間を、リアルというアナログで癒しを与え、生の充実感を与えるアナログ・自然に、“商機”を見出だす術もあるということを言いたいに過ぎぬ。
国家、企業レベルでAI(幕政改革)に血眼になるは、その長(将軍)、そして、その幹部クラス(老中たち)、そしてその部下(旗本)くらいのものであろう。さらにその下の従業員(御家人)は、組織内で、AIというデジタルに四六時中向き合う中、私生活では、アナログの心的癒し(歌舞伎・相撲・遊郭・浮世絵など)を求めるのが、人間の性、生物としての常というものである。
スマホに24時間支配されているZ世代の少女は、リアルを求めてTDLまたUSJに足繁く通うリピーターなのだ。また、スポティファイなどで、サブスクとやらも加わって、携帯フォンで、アンドロイド系音楽に夢中になっても、やはり、AdoやYOASOBIなどのライブは超満員なのだ。デジタルで満たされぬ欲求、無意識なる欲求不満の顕れ行為である。
AIの進化により、どれほど、人間の生活は便利、快適になろうとも、その根源のデジタルでは、到底満たされぬ精神的領域というものがある。これが、生物としての証、人間の譲れぬ、非日常の、会社外、学校外における、人間の余暇・娯楽・趣味というもの“最終砦”でもある。ロジェ・カイヨワの『遊びと人間』を換骨奪胎して、“アナログと人間”とも言い得ると主張したいのである。生の体験、リアルの経験といったものだ。ここに、自然、アナログという存在理由がある。その微少なる傾向として、フィルムカメラの静かなブームとやらが挙げられよう。レコードやカセットテープは当然、山下達郎に典型的に見かけられるように、アナログ音楽の復興が近年、とみに有名である。
あの森岡毅が、西武園ゆうえんちを立て直すコンセプトして、TDLの真逆、レトロ感を全面に打ち出して、V字回復させた事例も、こうした彼の嗅覚がそうさせもしたのであろう。今般のジャングリアは、沖縄の自然というものを最大限活用し、東京や大阪のテーマパークでは及びもつかない、不可能なアトラクション満載の企画を実現された模様だ。まだ、このジャングリアが成功するか否かは不明だが、大いに勝算はありえよう。
親たちはもちろん、その子供たちも、日常から非日常にいたるまで、デジタルの空気、環境の中に置かれている。それに馴染んで、幸福感を感じる種族はそれでもよしとしよう。しかし、ディズニーランドのように、内面、システムなどは、デジタルガチガチでありながらも、リアルのミッキーとハグができたり、キャストのもてなしに感服したり、エレクトリカルパレードに魅了されたりする。肉体を通す刺激、興奮は、現今のアミューズメントパークの独壇場でもあろう。これは、リアル、アナログの魅力でもある。世の社会人、学生は、日常では、ほぼデジタルの空間に投げ入れられる。そこに、居らざるをえぬのある。そのデジタルという場から脱したいという生物的欲求が、TDL、USJ、そしてライブへと駆り立ててもいる最大の要因なのだ。
デジタルは、人間にとって完全、完璧なものではない。この永久に不備の側面を、アナログが埋めてもくれる。これは、未来、AIは、埋めることが永遠にできぬと、私は賭けよう。できたとすれば、それこそが、人間というホモサピエンスの死を意味する。これを養老孟司氏は、“AI支配でヒトは死ぬ!”~『Ai支配でヒトは死ぬ。』(ビジネス社)~とも語ったわけである。
嗅覚鋭いマーケター森岡毅は、デジタルのカウンターではなく、アナログのカウンターでもあった自然というものを、今回全面に戦略として打ち出してもきた。このジャングリアが頓挫するとすれば、それは、ヒトの内面にある、本来的人間性の衰退ともいえなくもない。それは、地球温暖化同様に、もう、人間の自然性、アナログ性、いや、文明社会にマグマのように内在している“野生”といったものが逆戻りできない段階に侵食され始めた段階に入っている証左とも言い得よう。
ゴールドラシュを先導する、唱道する孫正義に、大衆はつられて、西へ、西へ{デジタルへデジタルへ、人間の没落}と向かいはするが、そのデジタルブームの陰で、東へ、東へ{アナログ性、自然性の復興}に目をつけた森岡毅のような存在は、リーバイス・ストラウスとも暗喩できるのである。
2025年7月28日 17:47