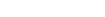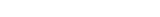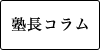カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2026年2月 (4)
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (3)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > 君は、タイムマシンで未来に、それとも過去に行くか?
コラム
君は、タイムマシンで未来に、それとも過去に行くか?
これは、よく生徒に質問する問いです。
「もし、ドラえもんの“どこでもドア”と“タイムマシン”をもらえるなら、どっちが欲しい?」
すると、大方、彼らは、「どこでもドアです」と応じできます。その理由は、電車や車など、移動手段を用いずに、瞬時にどこでもいけるからだそうです。現代っ子の“安近短”の気質が垣間見えてもきます。大の大人からすると、微笑ましい答えです。そこで、私は、「いや、どこでもドアがあれば、世界で最も儲かる運送会社を設立できる。そして、数秒で、アフリカや南米に荷物を届けられますよ。超もうかるでしょう!また、戦争の被災地などに瞬時に移動して、ケガ人などを連れてもこれするし、北朝鮮に侵入して、拉致被害者を連れ戻せもする。これは、超悪いケースだけど、世界の独裁者(プーチンなど)の官邸に侵入して、暗殺もできる。007の超優秀なスパイにもなり得る」と付け加えると、彼らは、更に満足気な表情をして、頷きます。しかし、「先生は、どこでもドアよりタイムマシンだな!」と彼らに言うと、どうして?と、反問してもきます。そこで、「タイムマシンがあると、未来に行ける、それは、先が解るということです。ならば、競馬で、数時間先にどの馬が来るか、明日は、どの株が急上昇すうか、それがわかっちゃうと、もう、それは、億万長者になることです。完全無欠な山師にもなれるということです。また、過去に遡れば、例えば、本能寺の変の場面に立ち会い、その光景を目にして、信長の死体がどこにあるか、その経緯はどうか知ることもできるし、邪馬台国の235年にタイムスリプして、卑弥呼はどういう女性だったか、邪馬台国はどこにあったか、などなど、歴史の真実を解明する、名歴史学者にもなれるだろう?」と大人目線の、現実的な、模範解答をすると、彼らは、未成年から成人の社会人の世界に覚醒した顔つきをします。小学生に、超わかりやすい金融教育や財テクを、リアルに話をした時の表情とも類似する顔つきです。この、<どこでもドアとタイムマシンの問い>の軍配は、私にあがるのです。人生経験の差に過ぎません。頭の優劣とか、思考力とかは、一切関係ありません。ここにも、政治家の総理、会社の社長が、一般的に、経験豊富な、中年以上が就任する理由の一つでもあるでしょう。
では、大人の世界の問いになります。
「あなたは、未来と過去では、もし行けるとすればどちらがいいですか?」というものを提示してみたいと思います。
これも、あくまでも一般論ともなりますが、未来に行きたいと応じる人は、恐らく理系の人ではないかと思います。自身のロマンが未来に広がる、科学技術への信頼、文明への信仰が、大木の根っ子の如く揺るがないなかです。一方、過去に行きたいと応える人は、文系気質の人ではないかと存じます。前者は、デジタル族、後者は、アナログ族と括ってもいいやに思われます。
戦後派の文豪、世界的にも名声が確立している作家、安部公房と三島由紀夫が対局をなすかと思います。安部の作品は、私は、『砂の女』や『壁』など以外、ほとんど読んでいません。名作とは理解できても、自身の感性がシンクロしないのです。つまり、好みではないのです。一方、三島の小説は、ほとんど読んでいます。心惹かれる、語彙の多彩さ、文体の華麗さ、テーマの焦点の当て方などなど、自身の好む文学世界でもあるからです。“過去のない未来人間”とも称される安部は、対象が未来へ、“憂国の美学者”とも認識される三島は、過去へ、それぞれペン先が向かうベクトルが真逆なのです。ここにも、私のアナログ度、いや、過去志向の気質が露わな点でもあるのです。
私は、小学校から中学校まで、漫画よりアニメ、それも、ロボット物{マジンガーZやゲッターロボ}や松本零士物{宇宙戦艦ヤマトや銀河鉄道999など}に惹かれた世代ではあっても、未来というものに、そんな憧れ・夢など抱いてもいなかったようです。知人や有名人など、手塚治虫の鉄腕アトムからやガンダム{※ガンダムがブームになった時、高校生の友人たちを醒めた眼で眺めていた}に至るまで、また、スターウォーズやスピルバーグの映画{未知との遭遇からET}などから、未来志向の大人になってゆく者が多い中、私は、未来もの、SFものからは、高校生以降だんだんと興味関心が薄らぎ、魅力の対象から遠ざかってもゆきました。これは、中学浪人時代に、読書人間、それも、文学青年に変貌していたことが最大の理由だったと思われます。世の中、社会の変化変貌より、自己の内面、自身の来し方・行く末、それにのみ関心があり、それの道標を、過去に、文学などに希求する精神的環境にあったと思われます。日々の多くの時間が、新潮文庫の小説に向きあう時間でもあったからでしょう。十代なかば、世は、インベーダーゲームが子供から大人まで席捲していた中、私は、冷めてもいました、まったく、はまりませんでした。こうしたことが、時代に逆行する気質を育んだとも言えましょう。その後、任天堂やソニーのゲーム機などには、一切、関与しない、デジタル娯楽とは無縁な生活、人生を送ってもきた。
日本は、失われた30年の間に、自動車や家電製品王国から、ゲーム・アニメ大国へと変貌を遂げました。ハードからソフトへ、モノからコトへ、文明の牽引役から文化の伝道師へと国の役割を変貌させて観がある。これも平成の後半から、若者気質に、草食系と揶揄される気質を育んだ遠因かもしれない。
世には、私のような、過去志向の人間とゲームやアニメに日々が占有される未来志向の人間とが存在するということを前提に、こうした、自己の資質、いや、気質というものに、どう距離を置いて、高校から大学へ、大学から社会へ対峙してゆくべきか。そして、新入社員から中堅社員へ、自己の内面に住み着いてもいる、デジタル族とアナログ族とをどう統べてゆく方策があるのか、それを次回語ってみたいと思います。
「もし、ドラえもんの“どこでもドア”と“タイムマシン”をもらえるなら、どっちが欲しい?」
すると、大方、彼らは、「どこでもドアです」と応じできます。その理由は、電車や車など、移動手段を用いずに、瞬時にどこでもいけるからだそうです。現代っ子の“安近短”の気質が垣間見えてもきます。大の大人からすると、微笑ましい答えです。そこで、私は、「いや、どこでもドアがあれば、世界で最も儲かる運送会社を設立できる。そして、数秒で、アフリカや南米に荷物を届けられますよ。超もうかるでしょう!また、戦争の被災地などに瞬時に移動して、ケガ人などを連れてもこれするし、北朝鮮に侵入して、拉致被害者を連れ戻せもする。これは、超悪いケースだけど、世界の独裁者(プーチンなど)の官邸に侵入して、暗殺もできる。007の超優秀なスパイにもなり得る」と付け加えると、彼らは、更に満足気な表情をして、頷きます。しかし、「先生は、どこでもドアよりタイムマシンだな!」と彼らに言うと、どうして?と、反問してもきます。そこで、「タイムマシンがあると、未来に行ける、それは、先が解るということです。ならば、競馬で、数時間先にどの馬が来るか、明日は、どの株が急上昇すうか、それがわかっちゃうと、もう、それは、億万長者になることです。完全無欠な山師にもなれるということです。また、過去に遡れば、例えば、本能寺の変の場面に立ち会い、その光景を目にして、信長の死体がどこにあるか、その経緯はどうか知ることもできるし、邪馬台国の235年にタイムスリプして、卑弥呼はどういう女性だったか、邪馬台国はどこにあったか、などなど、歴史の真実を解明する、名歴史学者にもなれるだろう?」と大人目線の、現実的な、模範解答をすると、彼らは、未成年から成人の社会人の世界に覚醒した顔つきをします。小学生に、超わかりやすい金融教育や財テクを、リアルに話をした時の表情とも類似する顔つきです。この、<どこでもドアとタイムマシンの問い>の軍配は、私にあがるのです。人生経験の差に過ぎません。頭の優劣とか、思考力とかは、一切関係ありません。ここにも、政治家の総理、会社の社長が、一般的に、経験豊富な、中年以上が就任する理由の一つでもあるでしょう。
では、大人の世界の問いになります。
「あなたは、未来と過去では、もし行けるとすればどちらがいいですか?」というものを提示してみたいと思います。
これも、あくまでも一般論ともなりますが、未来に行きたいと応じる人は、恐らく理系の人ではないかと思います。自身のロマンが未来に広がる、科学技術への信頼、文明への信仰が、大木の根っ子の如く揺るがないなかです。一方、過去に行きたいと応える人は、文系気質の人ではないかと存じます。前者は、デジタル族、後者は、アナログ族と括ってもいいやに思われます。
戦後派の文豪、世界的にも名声が確立している作家、安部公房と三島由紀夫が対局をなすかと思います。安部の作品は、私は、『砂の女』や『壁』など以外、ほとんど読んでいません。名作とは理解できても、自身の感性がシンクロしないのです。つまり、好みではないのです。一方、三島の小説は、ほとんど読んでいます。心惹かれる、語彙の多彩さ、文体の華麗さ、テーマの焦点の当て方などなど、自身の好む文学世界でもあるからです。“過去のない未来人間”とも称される安部は、対象が未来へ、“憂国の美学者”とも認識される三島は、過去へ、それぞれペン先が向かうベクトルが真逆なのです。ここにも、私のアナログ度、いや、過去志向の気質が露わな点でもあるのです。
私は、小学校から中学校まで、漫画よりアニメ、それも、ロボット物{マジンガーZやゲッターロボ}や松本零士物{宇宙戦艦ヤマトや銀河鉄道999など}に惹かれた世代ではあっても、未来というものに、そんな憧れ・夢など抱いてもいなかったようです。知人や有名人など、手塚治虫の鉄腕アトムからやガンダム{※ガンダムがブームになった時、高校生の友人たちを醒めた眼で眺めていた}に至るまで、また、スターウォーズやスピルバーグの映画{未知との遭遇からET}などから、未来志向の大人になってゆく者が多い中、私は、未来もの、SFものからは、高校生以降だんだんと興味関心が薄らぎ、魅力の対象から遠ざかってもゆきました。これは、中学浪人時代に、読書人間、それも、文学青年に変貌していたことが最大の理由だったと思われます。世の中、社会の変化変貌より、自己の内面、自身の来し方・行く末、それにのみ関心があり、それの道標を、過去に、文学などに希求する精神的環境にあったと思われます。日々の多くの時間が、新潮文庫の小説に向きあう時間でもあったからでしょう。十代なかば、世は、インベーダーゲームが子供から大人まで席捲していた中、私は、冷めてもいました、まったく、はまりませんでした。こうしたことが、時代に逆行する気質を育んだとも言えましょう。その後、任天堂やソニーのゲーム機などには、一切、関与しない、デジタル娯楽とは無縁な生活、人生を送ってもきた。
日本は、失われた30年の間に、自動車や家電製品王国から、ゲーム・アニメ大国へと変貌を遂げました。ハードからソフトへ、モノからコトへ、文明の牽引役から文化の伝道師へと国の役割を変貌させて観がある。これも平成の後半から、若者気質に、草食系と揶揄される気質を育んだ遠因かもしれない。
世には、私のような、過去志向の人間とゲームやアニメに日々が占有される未来志向の人間とが存在するということを前提に、こうした、自己の資質、いや、気質というものに、どう距離を置いて、高校から大学へ、大学から社会へ対峙してゆくべきか。そして、新入社員から中堅社員へ、自己の内面に住み着いてもいる、デジタル族とアナログ族とをどう統べてゆく方策があるのか、それを次回語ってみたいと思います。
2025年8月18日 16:17