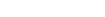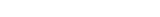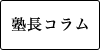カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2026年2月 (4)
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (3)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
コラム
未来型人間と過去型人間
前回、タイムマシンで、未来をのぞいてみたい人、過去に遡行して、史実を知りたい人、それぞれを理系人間、文系人間の表面的な気質であるとも指摘した。
理系人間、科学者は、仮説を立て、それを実験や観察により検証し、それを理論・定説として確立してゆくことを使命とする人種である。一方、文系人間は、歴史学者、経済学者、法学者、政治学者にしろ、過去と現在を比較し、その対照・相違点を分析し、現況に合致する制度やシステムなりを微調整しながら確立してゆくことを旨とする人種である。後者は、過去と現在を比較し、そして少々時代の先を視野に入れ、帰し方、行く末を分析するを生業とする。
将来宇宙飛行士になりたいとする少年のメンタルと古代エジプト文明に興味関心が旺盛な“博士ちゃん”などのメンタルが、まさしく、未来人間と過去人間の典型でもあろうか?前者の気質が、SF小説を生み、後者の気質が、歴史小説を生んでもきた。
SNS社会の皮肉ではないが、スマホなどで四六時中他者と連絡、コミュニケーションをとれる便利な社会にあっても、“つながり孤独”という、奇妙な社会現象が起き、社会の心的隔絶、いわば、自身の孤独や孤立に苛まれる時代が到来しているとも言われている。その癒し、解消手段として、生成AIを内蔵した、おしべり相手ロボットが出現したり、スマホの某機能で話し相手ともなってもらい、それに癒しを求める人間は、未来型人間でもあろうか。それに対して、生の、リアルの付き合い、集会に、また、仏教などの宗教に、また、書籍を通じて、時に、禅寺で座禅などを通して、そうした空虚感を解消、いや、埋める行為をする人間は、従来から存在する過去型人間でもあろう。
一般的に、未来に行ってみたいと公言する人間は、過去から現在の人類の経験・継続の“知”(履歴)にあまり関心がない。この喩えは、少々飛躍もあるが、ディズニーランドのリピーターの少女の気質に近いものがある。毎回のわくわく感、新しいアトラクションが現在の、当然過去は言わずもがなだが、自身の置かれている状況を脱却する快感が味わえることが、このテーマパークの魔力でもあり魅力なのだ。日々進化している“夢がかなう場所”でもあるからだ。また、前澤友作のような一部のセレブが、宇宙旅行をしたなどとメディアで報じられても、それに憧れ、羨望を感じる者は、これも当然未来型人間でもあろうか?
火星や月に、未来の宇宙基地が作られ、そこで生活する人類の子孫を、AI作成映像などで見せられるが、やはり、私なんぞの過去型人間からすると、いっこうにそんな美しい海も空も森もない世界で暮らしたいなどと憧れや希望など微塵も感じない。若田光一氏や野口聡一氏の宇宙ステーションでの映像を見せられても、代わりに、半年そこで生活してみるかと言われてみても、まっぴらごめんである。宇宙ステーションからの地球の眺望を生で観てはみたいが、その宇宙空間内での、生活の不如意を考えると、やはり、人工衛星から送られるてくる映像で十分である。
恐らく、ちょっと先を垣間見る大阪万博のような展示物くらいなら、まだしも、数百年先、千年先の人類など、見たくもない、もし、実際に、神なりが、その人間に、その社会生活の実体を見せつけさせたら、その本人は、“気が狂う”、また、“自殺する”、それほど、想像を絶する未来の地球の衝撃度でもあろう。未来などは、行けなくて丁度いい、見ない方が健全なのだ。この衝撃は、過去の、歴史上の真実を知った時の、その衝撃度などという比でない。やはり、未来に行ってみたいという人間の、精神の浅はかさ、楽天度の強さ、想像力の欠如などからもたらされるメンタル面の衝撃の凄さがわかっていない、極楽とんぼと言わざるを得ない。過去の真実を知った時のそれと現在の自己、実存への影響度といったものは、たかが知れている。
未来がわかってしまえば、夢という心的泉は干からびる。あらすじと結果がわかっているミステリー小説・サスペンス小説を読むようなものだ。炭酸の抜けたサイダーを飲むに等しい人生ともなる。一方、過去がわかっても、強靭なる精神から、その来し方から希望を構築し、それを土台に夢という建築物を、行く末に建てることができる。この文脈において、自動運転、GPS搭載の運転などは、未来がわかればそれでいいとする未来型人間の気質を如実にあらわしてもいよう!人生において予定調和こそ、未来型人間の、快適さ・心地よさなのかもしれない。
「一人の高齢者が死ぬと一つの図書館がなくなる」というアフリカで語られる格言があるが、一人の人間の尊厳とは、生命を別にすれば、その個人の記憶・履歴・経験というものにこそ、形而下では集約される。さらに、その総体、全体知として日本史・世界史という形而上のものがある。実は、デジタルという文明の流儀の最大の盲点、陥穽、危険というものが、生の人間から、こうしたものを剥奪するという怖さがあるという点なのだ。人々を先へ、先へ、空虚なる未来へと誘導する魔性をデジタル社会が内包している点なのだ。お彼岸やお盆のたびに、祖父母の生成AIによって作成された、動く、しゃべる映像を観て、話しかけ、応じてもくるデジタル社会に悲しみや喪失感の癒しを求める人間、それは、ある意味で、未来型人間である。一方、祖父母の墓石を前にして、また、遺影を見つめて、生前の彼らとの思い出を、様々な場面を回想する、振り返る所作というもので故人を偲び、その故人を慕う人間、それを過去型人間と呼ぼう。従来のアナログ社会と、デジタルに支配された未来型人間を良しとするか、それは、人間の心の純度の試金石にもなろう。ここでいう、人間におけるデジタル度、アナログ度、それは、過去型人間か、未来型人間か、そこでいう、後者になろう、なりたいなどと希求する種族は、豊饒たるべき人生90年を不毛に終わらせかねない危険性を孕む資質なのだ。卑近な例を持ち出すまでもなく、一日24時間、ほとんどスマホと寝食を共にしている生活がまさにそれである。こうした文脈で、私見を援護射撃してもくれる名品が、小林秀雄の『無常ということ』である。
これは誰も言っていないことなのだが、デジタルの、最大、最高の麻薬性とは、本来、全てもの、特に人間というものは無常であるはずの自身の存在なのに、それを、己自身にその“無常”を忘れさせてしまうことに存する。そうしたAI新興宗教に入信すべきか否か、そのメルクマールともいえる気質が、未来型人間と去型人間とも括れれる点なのだ。
電車内の無聊をかこつ時間をスマホを無為に眺めるサラリーマン、その後見もしないスマホ映像を無数保存している女子校生、今を忘れ、虚無なる未来に目を向ける未来型人間の一側面でもあろう。デジタル宗教が変えてしまった人間のメンタルの一光景でもある。
理系人間、科学者は、仮説を立て、それを実験や観察により検証し、それを理論・定説として確立してゆくことを使命とする人種である。一方、文系人間は、歴史学者、経済学者、法学者、政治学者にしろ、過去と現在を比較し、その対照・相違点を分析し、現況に合致する制度やシステムなりを微調整しながら確立してゆくことを旨とする人種である。後者は、過去と現在を比較し、そして少々時代の先を視野に入れ、帰し方、行く末を分析するを生業とする。
将来宇宙飛行士になりたいとする少年のメンタルと古代エジプト文明に興味関心が旺盛な“博士ちゃん”などのメンタルが、まさしく、未来人間と過去人間の典型でもあろうか?前者の気質が、SF小説を生み、後者の気質が、歴史小説を生んでもきた。
SNS社会の皮肉ではないが、スマホなどで四六時中他者と連絡、コミュニケーションをとれる便利な社会にあっても、“つながり孤独”という、奇妙な社会現象が起き、社会の心的隔絶、いわば、自身の孤独や孤立に苛まれる時代が到来しているとも言われている。その癒し、解消手段として、生成AIを内蔵した、おしべり相手ロボットが出現したり、スマホの某機能で話し相手ともなってもらい、それに癒しを求める人間は、未来型人間でもあろうか。それに対して、生の、リアルの付き合い、集会に、また、仏教などの宗教に、また、書籍を通じて、時に、禅寺で座禅などを通して、そうした空虚感を解消、いや、埋める行為をする人間は、従来から存在する過去型人間でもあろう。
一般的に、未来に行ってみたいと公言する人間は、過去から現在の人類の経験・継続の“知”(履歴)にあまり関心がない。この喩えは、少々飛躍もあるが、ディズニーランドのリピーターの少女の気質に近いものがある。毎回のわくわく感、新しいアトラクションが現在の、当然過去は言わずもがなだが、自身の置かれている状況を脱却する快感が味わえることが、このテーマパークの魔力でもあり魅力なのだ。日々進化している“夢がかなう場所”でもあるからだ。また、前澤友作のような一部のセレブが、宇宙旅行をしたなどとメディアで報じられても、それに憧れ、羨望を感じる者は、これも当然未来型人間でもあろうか?
火星や月に、未来の宇宙基地が作られ、そこで生活する人類の子孫を、AI作成映像などで見せられるが、やはり、私なんぞの過去型人間からすると、いっこうにそんな美しい海も空も森もない世界で暮らしたいなどと憧れや希望など微塵も感じない。若田光一氏や野口聡一氏の宇宙ステーションでの映像を見せられても、代わりに、半年そこで生活してみるかと言われてみても、まっぴらごめんである。宇宙ステーションからの地球の眺望を生で観てはみたいが、その宇宙空間内での、生活の不如意を考えると、やはり、人工衛星から送られるてくる映像で十分である。
恐らく、ちょっと先を垣間見る大阪万博のような展示物くらいなら、まだしも、数百年先、千年先の人類など、見たくもない、もし、実際に、神なりが、その人間に、その社会生活の実体を見せつけさせたら、その本人は、“気が狂う”、また、“自殺する”、それほど、想像を絶する未来の地球の衝撃度でもあろう。未来などは、行けなくて丁度いい、見ない方が健全なのだ。この衝撃は、過去の、歴史上の真実を知った時の、その衝撃度などという比でない。やはり、未来に行ってみたいという人間の、精神の浅はかさ、楽天度の強さ、想像力の欠如などからもたらされるメンタル面の衝撃の凄さがわかっていない、極楽とんぼと言わざるを得ない。過去の真実を知った時のそれと現在の自己、実存への影響度といったものは、たかが知れている。
未来がわかってしまえば、夢という心的泉は干からびる。あらすじと結果がわかっているミステリー小説・サスペンス小説を読むようなものだ。炭酸の抜けたサイダーを飲むに等しい人生ともなる。一方、過去がわかっても、強靭なる精神から、その来し方から希望を構築し、それを土台に夢という建築物を、行く末に建てることができる。この文脈において、自動運転、GPS搭載の運転などは、未来がわかればそれでいいとする未来型人間の気質を如実にあらわしてもいよう!人生において予定調和こそ、未来型人間の、快適さ・心地よさなのかもしれない。
「一人の高齢者が死ぬと一つの図書館がなくなる」というアフリカで語られる格言があるが、一人の人間の尊厳とは、生命を別にすれば、その個人の記憶・履歴・経験というものにこそ、形而下では集約される。さらに、その総体、全体知として日本史・世界史という形而上のものがある。実は、デジタルという文明の流儀の最大の盲点、陥穽、危険というものが、生の人間から、こうしたものを剥奪するという怖さがあるという点なのだ。人々を先へ、先へ、空虚なる未来へと誘導する魔性をデジタル社会が内包している点なのだ。お彼岸やお盆のたびに、祖父母の生成AIによって作成された、動く、しゃべる映像を観て、話しかけ、応じてもくるデジタル社会に悲しみや喪失感の癒しを求める人間、それは、ある意味で、未来型人間である。一方、祖父母の墓石を前にして、また、遺影を見つめて、生前の彼らとの思い出を、様々な場面を回想する、振り返る所作というもので故人を偲び、その故人を慕う人間、それを過去型人間と呼ぼう。従来のアナログ社会と、デジタルに支配された未来型人間を良しとするか、それは、人間の心の純度の試金石にもなろう。ここでいう、人間におけるデジタル度、アナログ度、それは、過去型人間か、未来型人間か、そこでいう、後者になろう、なりたいなどと希求する種族は、豊饒たるべき人生90年を不毛に終わらせかねない危険性を孕む資質なのだ。卑近な例を持ち出すまでもなく、一日24時間、ほとんどスマホと寝食を共にしている生活がまさにそれである。こうした文脈で、私見を援護射撃してもくれる名品が、小林秀雄の『無常ということ』である。
これは誰も言っていないことなのだが、デジタルの、最大、最高の麻薬性とは、本来、全てもの、特に人間というものは無常であるはずの自身の存在なのに、それを、己自身にその“無常”を忘れさせてしまうことに存する。そうしたAI新興宗教に入信すべきか否か、そのメルクマールともいえる気質が、未来型人間と去型人間とも括れれる点なのだ。
電車内の無聊をかこつ時間をスマホを無為に眺めるサラリーマン、その後見もしないスマホ映像を無数保存している女子校生、今を忘れ、虚無なる未来に目を向ける未来型人間の一側面でもあろう。デジタル宗教が変えてしまった人間のメンタルの一光景でもある。
2025年8月25日 17:00