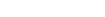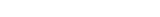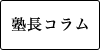カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2026年1月 (2)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (3)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > 平成から令和にかけて英語より数学でしょう!
コラム
平成から令和にかけて英語より数学でしょう!
ここ10年くらいだろうか、高等教育では、文理融合が提言されている、事実、推進もされているようだが、教員の理想と現場の学生には、当然ながら“学びの齟齬”が存在する。その最大の原因は、中等教育にある。高大接続という、耳あたりのいいスローガンは、大学から高校への、学びの責任転嫁の呪文のようなフレーズである。
文系でもデータサイエンスを、理系でも哲学・歴史など教養を、強いられる時代になってきてはいるが、現状は、余り変わっていない。勿論、日本においての話である。また、大学入試、とりわけ、大学入学共通テストなどの、問題の質も、様々な教科横断型の問題傾向となってきた。数学の問題が、国語の読解をも視野に入れている問題の傾向となってきているなど、英語の問題が、従来の読解力以上に、表や図といったデータを瞬時にプチ(即断)分析できる能力、いや、資質が求められている点なのだ。現実の共通テストの理念とは、問題の質が大いにかけ離れている。中等教育、特に高校でも、歴史総合といった、日本史と世界史の近代史の融合性を掘り下げる教科へ変貌しているなど、これまでの“英数国理社といった、教科分離の意識”では、太刀打ち、対応できないようなシステムに変化している様は明々白々なのだ。
こうした傾向は、科学というジャンルで、ここ50年以上、応用科学という名称で、遺伝子工学やゲノム解読など、生物と物理、化学の総力戦の時代に突入したことでも、その進化の特質が証明されてもいよう。文系でも、地政学などが、脚光を浴びてもきた。最近では、地経学なる用語の書籍まで目につくようになってきている。これは、人類の進化発展の証左でもあろうか、中世から近世への移行の期間、数学が、物理学を産み落とし、近世から近代への激動期、またもや、数学が経済学を“成人学問”にした。その“成人科学”が、金融工学で、初めての蹉跌がリーマンショックでもあろう。ここでも、全ての学問(科学)からビジネスにいたるまで、コンピュータ、そしてAIを無視しては、成立しない時代の突入したことの顕れでもあろう。
全ての学問が、サイエンスを“憲法”としなければ成立しない、その時代の流れを鋭く嗅ぎ分けて早稲田大学田中愛治総長が、2021年に、早稲田の政治経済学に数学ⅠAを必須とする決断を下したりしたのは、令和の高校生への、身近な、卑近な、入試という通過儀礼を通して、“グローバル的学問基準の本道”を自覚させるメッセージでもあったであろう。サイエンスの中枢神経・脳髄とは、数学であるという真実を当たり前のように断行したまでである。これは、スマホ世代、デジタルネイティブという気質を持ち合わせている中高生には、文科省の、高校3年間数学必須のカリキュラムをゴリ押しすれば、強要すれば、それで済むことである。英語教育ばかりに汲々として、現場に<使える英語>{※逆説めくが、皮肉なことに、国が“使える英語”を推進すればするほど現場では、“英語が使えない生徒”を量産しているのである!}を押しつける、それ以前に、数学を徹底に学ばせる教育システムの方が、どれほど必要か、国家は分かっていない。優秀な英語の教員以上に、数学の優秀な教員が払底している現実が、それを不可能にしている現状を、誰も指摘しない。現今、英語以上に数学が大切なのは、21世紀は外国人と、20世紀以来の“現代のラテン語=地球共通語=英語”よりも、機械、コンピュータと対話する、それを生み出す、そして、教育する“数学というコトバ”の方がどれほど大切かがわかっていない証拠である。数学が、デジタル世界(=グローバル社会)の共通言語である。C言語という名称があるように、それの重要性を中学生の段階から滔々と啓蒙しなければならないのである。このデジタル社会こそ、高卒、中卒でも、C言語が自由自在に操れる者は、食いぱぐれることはない。色々なゲームソフトを開発でき、様々なアプリを作成できることからも得心がゆくであろう。一方、英語がどんなにぺらぺら喋れても、数学がからっきしダメ、非大卒、いや、政治、経済など教養がなければ、生きてはいけない。当然、英語ぺらぺらでも、海外で和食店、寿司バーを経営するなど、飲食業、サービス業で財をなすことも、当然可能でもあるが、そうした者は、本来、商才に長けている者がただ偶然に英語ができたケースに過ぎない。また、それまでの、色々な人生経験が、“学び舎”の人間でもあった可能性が大の人間なのだ。
英語ができると、世界へ羽ばたける、世界を相手にビジネスができる、よって、豊かな未来が見えてもいた、そうした幻想が、20世紀の時代でもあったであろう。また、日本が、自動車、家電など、世界の工業の牽引役の時代であれば、理系と文系の大学生が、社会人として、その会社・社会・国家を分業で支えてもいた幸福な、人口も多い時代であった。年功序列・終身雇用、その呼称が、理系・文系の種族の棲み分けの可能な、幸福な、安穏とした時代を象徴してもいようか!
医師という部族、勤務医と開業医との資質の差は、文系資質の濃淡にあるとも言われる。知人にもいたが、ビジネス感覚を持ちあわせていない医師は、開業医には不向きである。勤務医が、独立する際、経営コンサルに相談する事例が、それを如実に、雄弁に物語ってもいる。
今の時代、「会社は頼れない、依存する意識を持つは厳禁」ともいう。転職サイト花盛りである。これは、学歴があてにならない時代の証左である、よって、今は、学歴ではなく学び歴の時代とされる所以である。変化の激しい時代、自身の自慢のスキルは、ホコリを被り、浜辺の鉄柱のように、すぐにさび付く。このメンテナンスを、学びともいい、リスキリングとも称する。組織的、個人的、時代の大流としてDXが喧伝されている所以である。この潮流に乗るには、英語ではなく、数学であると、文科省は、世の中高生に、声高に、脅迫まがいに、唱道していない。理系教育重視だの、理系離れを食い止めるだの、漠然と現場に指導しているだけで、教室内の生徒には、まるで、明治政府が出した、五箇条の御誓文や五榜の掲示のように、明治臣民の心には届いていない状況と似たものがある。
昭和の時代、「英語が大切だ!英語が必要だ!」とやたらと現場の教室内に、親御さんの間に、叫ばれた風潮の如きに、令和において、「数学が大切だ!数学が必要だ!」と主張し、中高生を洗脳するくらいの極端な、教育政策を行わない限り、日本の経済復興もありえない!
失われた30年における、最大の、教育的過ちは、時代が、英語から数学へと、大転換している時代の流れを、文科省、いや、世の親たちが、見誤ったことにあると、指摘する者はいない。帝国海軍が、日露戦争での成功体験に固執し、一つの巨大戦艦、“大和”の如き巨艦主義(英語)を第一世界大戦後も続けたるなれの果ては、世は航空母艦至上主義(数学)の時代に突入している変化に瞑して、第二世界大戦で失敗したる事例は、英語と数学の関係においても該当すると私は思うのである。
文系でもデータサイエンスを、理系でも哲学・歴史など教養を、強いられる時代になってきてはいるが、現状は、余り変わっていない。勿論、日本においての話である。また、大学入試、とりわけ、大学入学共通テストなどの、問題の質も、様々な教科横断型の問題傾向となってきた。数学の問題が、国語の読解をも視野に入れている問題の傾向となってきているなど、英語の問題が、従来の読解力以上に、表や図といったデータを瞬時にプチ(即断)分析できる能力、いや、資質が求められている点なのだ。現実の共通テストの理念とは、問題の質が大いにかけ離れている。中等教育、特に高校でも、歴史総合といった、日本史と世界史の近代史の融合性を掘り下げる教科へ変貌しているなど、これまでの“英数国理社といった、教科分離の意識”では、太刀打ち、対応できないようなシステムに変化している様は明々白々なのだ。
こうした傾向は、科学というジャンルで、ここ50年以上、応用科学という名称で、遺伝子工学やゲノム解読など、生物と物理、化学の総力戦の時代に突入したことでも、その進化の特質が証明されてもいよう。文系でも、地政学などが、脚光を浴びてもきた。最近では、地経学なる用語の書籍まで目につくようになってきている。これは、人類の進化発展の証左でもあろうか、中世から近世への移行の期間、数学が、物理学を産み落とし、近世から近代への激動期、またもや、数学が経済学を“成人学問”にした。その“成人科学”が、金融工学で、初めての蹉跌がリーマンショックでもあろう。ここでも、全ての学問(科学)からビジネスにいたるまで、コンピュータ、そしてAIを無視しては、成立しない時代の突入したことの顕れでもあろう。
全ての学問が、サイエンスを“憲法”としなければ成立しない、その時代の流れを鋭く嗅ぎ分けて早稲田大学田中愛治総長が、2021年に、早稲田の政治経済学に数学ⅠAを必須とする決断を下したりしたのは、令和の高校生への、身近な、卑近な、入試という通過儀礼を通して、“グローバル的学問基準の本道”を自覚させるメッセージでもあったであろう。サイエンスの中枢神経・脳髄とは、数学であるという真実を当たり前のように断行したまでである。これは、スマホ世代、デジタルネイティブという気質を持ち合わせている中高生には、文科省の、高校3年間数学必須のカリキュラムをゴリ押しすれば、強要すれば、それで済むことである。英語教育ばかりに汲々として、現場に<使える英語>{※逆説めくが、皮肉なことに、国が“使える英語”を推進すればするほど現場では、“英語が使えない生徒”を量産しているのである!}を押しつける、それ以前に、数学を徹底に学ばせる教育システムの方が、どれほど必要か、国家は分かっていない。優秀な英語の教員以上に、数学の優秀な教員が払底している現実が、それを不可能にしている現状を、誰も指摘しない。現今、英語以上に数学が大切なのは、21世紀は外国人と、20世紀以来の“現代のラテン語=地球共通語=英語”よりも、機械、コンピュータと対話する、それを生み出す、そして、教育する“数学というコトバ”の方がどれほど大切かがわかっていない証拠である。数学が、デジタル世界(=グローバル社会)の共通言語である。C言語という名称があるように、それの重要性を中学生の段階から滔々と啓蒙しなければならないのである。このデジタル社会こそ、高卒、中卒でも、C言語が自由自在に操れる者は、食いぱぐれることはない。色々なゲームソフトを開発でき、様々なアプリを作成できることからも得心がゆくであろう。一方、英語がどんなにぺらぺら喋れても、数学がからっきしダメ、非大卒、いや、政治、経済など教養がなければ、生きてはいけない。当然、英語ぺらぺらでも、海外で和食店、寿司バーを経営するなど、飲食業、サービス業で財をなすことも、当然可能でもあるが、そうした者は、本来、商才に長けている者がただ偶然に英語ができたケースに過ぎない。また、それまでの、色々な人生経験が、“学び舎”の人間でもあった可能性が大の人間なのだ。
英語ができると、世界へ羽ばたける、世界を相手にビジネスができる、よって、豊かな未来が見えてもいた、そうした幻想が、20世紀の時代でもあったであろう。また、日本が、自動車、家電など、世界の工業の牽引役の時代であれば、理系と文系の大学生が、社会人として、その会社・社会・国家を分業で支えてもいた幸福な、人口も多い時代であった。年功序列・終身雇用、その呼称が、理系・文系の種族の棲み分けの可能な、幸福な、安穏とした時代を象徴してもいようか!
医師という部族、勤務医と開業医との資質の差は、文系資質の濃淡にあるとも言われる。知人にもいたが、ビジネス感覚を持ちあわせていない医師は、開業医には不向きである。勤務医が、独立する際、経営コンサルに相談する事例が、それを如実に、雄弁に物語ってもいる。
今の時代、「会社は頼れない、依存する意識を持つは厳禁」ともいう。転職サイト花盛りである。これは、学歴があてにならない時代の証左である、よって、今は、学歴ではなく学び歴の時代とされる所以である。変化の激しい時代、自身の自慢のスキルは、ホコリを被り、浜辺の鉄柱のように、すぐにさび付く。このメンテナンスを、学びともいい、リスキリングとも称する。組織的、個人的、時代の大流としてDXが喧伝されている所以である。この潮流に乗るには、英語ではなく、数学であると、文科省は、世の中高生に、声高に、脅迫まがいに、唱道していない。理系教育重視だの、理系離れを食い止めるだの、漠然と現場に指導しているだけで、教室内の生徒には、まるで、明治政府が出した、五箇条の御誓文や五榜の掲示のように、明治臣民の心には届いていない状況と似たものがある。
昭和の時代、「英語が大切だ!英語が必要だ!」とやたらと現場の教室内に、親御さんの間に、叫ばれた風潮の如きに、令和において、「数学が大切だ!数学が必要だ!」と主張し、中高生を洗脳するくらいの極端な、教育政策を行わない限り、日本の経済復興もありえない!
失われた30年における、最大の、教育的過ちは、時代が、英語から数学へと、大転換している時代の流れを、文科省、いや、世の親たちが、見誤ったことにあると、指摘する者はいない。帝国海軍が、日露戦争での成功体験に固執し、一つの巨大戦艦、“大和”の如き巨艦主義(英語)を第一世界大戦後も続けたるなれの果ては、世は航空母艦至上主義(数学)の時代に突入している変化に瞑して、第二世界大戦で失敗したる事例は、英語と数学の関係においても該当すると私は思うのである。
2025年9月 1日 16:35