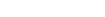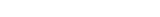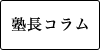カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (3)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > 中学受験の合格体験は、ビジネスの成功体験に比類する
コラム
中学受験の合格体験は、ビジネスの成功体験に比類する
「梯子の頂上に登る勇気は貴い、更にそこから降りてきて、再び登り返す勇気を持つ者は更に貴い」(速水御舟)
ビジネスの世界では、従来からの言い古された格言「失敗は成功の母」といったものより、近年では、「成功は失敗の母」といった、一種「勝って兜の緒を締めよ」的意味あいの新たな格言が生まれてきた。昭和の時代の「厳しく育てよ」~体罰是認~から平成の「褒めて育てよ」~体罰厳禁~へと教育的手法が激変したように、処世術にしろ、教育手法にしろ、時代、世界というものが豹変してきた、その事象を表徴する言葉でもあろうか。
甘い言葉、心地よい体験は、失敗へと誘導する蜜の香りとも言えようか?初代創業者社長が、二代目に「可愛い子には旅をさせよ」とは、社内で、口外してはいても、傍から見ると、甘っちょろい経験しかさせずに二代目を継承させるビジネスモデルとも言えなくもない。この、二代目のメンタルが、進学校へと進んだ中学生にも酷似しているという指摘をしておこう。
21世紀、科学技術にしろ、学問にしろ、長足の進歩を遂げる時代、また、ドッグイヤーとも称される今日、その成功体験というものは、次段階の自身の地雷ともなる、恐ろしい状況下にいることに警鐘を鳴らす「成功は最低の教師」(ビル・ゲイツ)「成功は一日で捨て去れ」(柳井正)といった名言は、そうした真実を露骨に諭してもくれる。
以上のように、ビジネスの世界、また、実社会における、成功という勲章をいつまでも首にかけていては、今、どこで、どうしているかもわからない金メダリスト、名アスリートのような存在を彷彿させてもくれよう。親が、国体レベル、やっとオリンピックに出たくらいの二流アスリートに限り、我が子が、メダリストになるケースは暇がないほど多いが、特に、金メダリストの親が、我が子をメダリストにしたケースは皆無なのだ。
実は、この成功体験で、一番人生の初段階で、足をすくわれるのが、公立小学校から、進学塾(サピックスや日能研)を経て、進学校の名門(聖光・栄光・浅野・サレジオ~神奈川県~)、中高一貫校に入学した、少年の連中なのである。実は、そうした私立の進学校に進んだ新入生に、校長は、まず、この成功体験=合格体験の魔性、中毒症、麻薬性を、滔々と警告しなければならないのである。たかだか12、13歳の中一生でも、“clever”ではなく“wise”の精神年齢を持ち合わせている者は、言われなくても、内発的に、初等教育から中等教育への精神の啓蒙を自身に、無意識に課していることだろう。これが、その後、6年後の、大学入試への勝ち組の道程をすでに敷き詰めている賢者(Mr.Wisdom
)なのだ。
文字通り、初等教育の教科名、<国語・算数・理科・社会>から、中等教育の教科名、<英語・数学・国語・理科・社会>へと看板名を置き換えるのである。実は、この、教科の看板の変更、それが、どれほどの意味、意義を持つのか分からぬ思春期前夜の少年が実に多いのである。いわば、小学生のメンタルのままで、どれほど多く者が、中学生になっているのかという実体があるということに過ぎにぬ。それは、畢竟、お勉強から勉強、そして、プチ学問の領域に、まるで、知の木立から、知の林へ、更には、知の森へと踏み込んでゆく、知的冒険となること気づいていないのである。それは、踏み入れてゆく本人の人格(心)と精神(技)の成長を促す、より高い峰をめざす“知的営為とも言いうる登山”のような自覚を強烈に持たねば、知の達成<≒志望大学合格>はないのである。端折って言うが、学びの成長と心の成長が比例しない現実があるということでもある。ここにおいても、「人間的な成長なくして、技術の進歩なし」(野村克也)という格言が一脈も、二脈も通底している真実ではある。
小学生時代は、その公立小学校で、“秀才”天才”の誉れ高い少年でもあったろう。それは、中学時代に、野球の才能があると周囲におだてあげられてもいた“エリート野球少年”にも比類できよう。しかし、彼らは、各地域からの猛者・ギフティッドが集まる、超進学校、超野球の名門校(横浜高校・東海大相模)で、昼行燈の如き存在を自覚せざるおえなくなく。そこなのだ!そこを、自身の凡才の強烈なる自覚から、再度、そのスタートラインから技能・技術の鍛錬修練による進歩が始まる。“自身の天才に絶望した時に、真の努力が覚醒する”ではないが、甲子園出場の高校球児、それも名投手としてプロ野球に入った川上哲治しかり、王貞治しかり、その後、伝説の打者として大成した事例を持ち出すまでもない。「失敗は成功の母」とは、こうした偉人的アスリートから余りにも多くの人が、口にする、また頭では認識できてもいよう。だが、「挫折・蹉跌が成功の母」と自覚する者は、少数派、いや皆無なのである。ここに言葉の真意をくみ取れるか否かの三叉路がある。超進学校に入学した“凡夫”が、悟れない、見えない人生行路の難所があるのである。今もっとも脚光を浴びている医師、あの鉄緑会の生みの親にして、精神科医でもある和田秀樹氏などは、灘中にトップクラスで入学し、その後、成績は高校2年まで下降線を辿り、全校で底辺に近い順位にまで落ちぶれるが、そこからが、V字回復、和田式受験テクニックの覚醒、いわば、学びの悟りのようなものである。そして、東大理Ⅲに合格するのである。これなどは、小中接続の学びの手法、いわば、小学校と中学校・高校では、まったく勉強手法が違っているということを悟るのに、5年弱を要した範例のようなものでもあろう。実は、大方の中等教育段階の少年の不本意な学業の伸び悩みの淵源とは、この和田氏の縮小版にすぎぬのである。
このように、小学校から中学校へ進む少年たちの、成否は、丁度、幕末の特に、下級身分の武士の者が、その後、明治という近代化社会の中で、大成してゆくか様が、歴史群像が証明してもくれている。当然、その人の天分もあろうが、天保の偉人たち、特に、教育者の福澤諭吉、実業家の渋沢栄一、政治家の伊藤博文など、何故だか、天保期間に、明治時代の礎と築いた英傑が枚挙に暇がないほど、綺羅星の如く存在する。当然坂本龍馬もいる。
では、この小学校から中学校への過渡期の、各教科への現場中学生への教訓、また、その親御さんへの助言などを次回語ってみたい。(つづく)
ビジネスの世界では、従来からの言い古された格言「失敗は成功の母」といったものより、近年では、「成功は失敗の母」といった、一種「勝って兜の緒を締めよ」的意味あいの新たな格言が生まれてきた。昭和の時代の「厳しく育てよ」~体罰是認~から平成の「褒めて育てよ」~体罰厳禁~へと教育的手法が激変したように、処世術にしろ、教育手法にしろ、時代、世界というものが豹変してきた、その事象を表徴する言葉でもあろうか。
甘い言葉、心地よい体験は、失敗へと誘導する蜜の香りとも言えようか?初代創業者社長が、二代目に「可愛い子には旅をさせよ」とは、社内で、口外してはいても、傍から見ると、甘っちょろい経験しかさせずに二代目を継承させるビジネスモデルとも言えなくもない。この、二代目のメンタルが、進学校へと進んだ中学生にも酷似しているという指摘をしておこう。
21世紀、科学技術にしろ、学問にしろ、長足の進歩を遂げる時代、また、ドッグイヤーとも称される今日、その成功体験というものは、次段階の自身の地雷ともなる、恐ろしい状況下にいることに警鐘を鳴らす「成功は最低の教師」(ビル・ゲイツ)「成功は一日で捨て去れ」(柳井正)といった名言は、そうした真実を露骨に諭してもくれる。
以上のように、ビジネスの世界、また、実社会における、成功という勲章をいつまでも首にかけていては、今、どこで、どうしているかもわからない金メダリスト、名アスリートのような存在を彷彿させてもくれよう。親が、国体レベル、やっとオリンピックに出たくらいの二流アスリートに限り、我が子が、メダリストになるケースは暇がないほど多いが、特に、金メダリストの親が、我が子をメダリストにしたケースは皆無なのだ。
実は、この成功体験で、一番人生の初段階で、足をすくわれるのが、公立小学校から、進学塾(サピックスや日能研)を経て、進学校の名門(聖光・栄光・浅野・サレジオ~神奈川県~)、中高一貫校に入学した、少年の連中なのである。実は、そうした私立の進学校に進んだ新入生に、校長は、まず、この成功体験=合格体験の魔性、中毒症、麻薬性を、滔々と警告しなければならないのである。たかだか12、13歳の中一生でも、“clever”ではなく“wise”の精神年齢を持ち合わせている者は、言われなくても、内発的に、初等教育から中等教育への精神の啓蒙を自身に、無意識に課していることだろう。これが、その後、6年後の、大学入試への勝ち組の道程をすでに敷き詰めている賢者(Mr.Wisdom
)なのだ。
文字通り、初等教育の教科名、<国語・算数・理科・社会>から、中等教育の教科名、<英語・数学・国語・理科・社会>へと看板名を置き換えるのである。実は、この、教科の看板の変更、それが、どれほどの意味、意義を持つのか分からぬ思春期前夜の少年が実に多いのである。いわば、小学生のメンタルのままで、どれほど多く者が、中学生になっているのかという実体があるということに過ぎにぬ。それは、畢竟、お勉強から勉強、そして、プチ学問の領域に、まるで、知の木立から、知の林へ、更には、知の森へと踏み込んでゆく、知的冒険となること気づいていないのである。それは、踏み入れてゆく本人の人格(心)と精神(技)の成長を促す、より高い峰をめざす“知的営為とも言いうる登山”のような自覚を強烈に持たねば、知の達成<≒志望大学合格>はないのである。端折って言うが、学びの成長と心の成長が比例しない現実があるということでもある。ここにおいても、「人間的な成長なくして、技術の進歩なし」(野村克也)という格言が一脈も、二脈も通底している真実ではある。
小学生時代は、その公立小学校で、“秀才”天才”の誉れ高い少年でもあったろう。それは、中学時代に、野球の才能があると周囲におだてあげられてもいた“エリート野球少年”にも比類できよう。しかし、彼らは、各地域からの猛者・ギフティッドが集まる、超進学校、超野球の名門校(横浜高校・東海大相模)で、昼行燈の如き存在を自覚せざるおえなくなく。そこなのだ!そこを、自身の凡才の強烈なる自覚から、再度、そのスタートラインから技能・技術の鍛錬修練による進歩が始まる。“自身の天才に絶望した時に、真の努力が覚醒する”ではないが、甲子園出場の高校球児、それも名投手としてプロ野球に入った川上哲治しかり、王貞治しかり、その後、伝説の打者として大成した事例を持ち出すまでもない。「失敗は成功の母」とは、こうした偉人的アスリートから余りにも多くの人が、口にする、また頭では認識できてもいよう。だが、「挫折・蹉跌が成功の母」と自覚する者は、少数派、いや皆無なのである。ここに言葉の真意をくみ取れるか否かの三叉路がある。超進学校に入学した“凡夫”が、悟れない、見えない人生行路の難所があるのである。今もっとも脚光を浴びている医師、あの鉄緑会の生みの親にして、精神科医でもある和田秀樹氏などは、灘中にトップクラスで入学し、その後、成績は高校2年まで下降線を辿り、全校で底辺に近い順位にまで落ちぶれるが、そこからが、V字回復、和田式受験テクニックの覚醒、いわば、学びの悟りのようなものである。そして、東大理Ⅲに合格するのである。これなどは、小中接続の学びの手法、いわば、小学校と中学校・高校では、まったく勉強手法が違っているということを悟るのに、5年弱を要した範例のようなものでもあろう。実は、大方の中等教育段階の少年の不本意な学業の伸び悩みの淵源とは、この和田氏の縮小版にすぎぬのである。
このように、小学校から中学校へ進む少年たちの、成否は、丁度、幕末の特に、下級身分の武士の者が、その後、明治という近代化社会の中で、大成してゆくか様が、歴史群像が証明してもくれている。当然、その人の天分もあろうが、天保の偉人たち、特に、教育者の福澤諭吉、実業家の渋沢栄一、政治家の伊藤博文など、何故だか、天保期間に、明治時代の礎と築いた英傑が枚挙に暇がないほど、綺羅星の如く存在する。当然坂本龍馬もいる。
では、この小学校から中学校への過渡期の、各教科への現場中学生への教訓、また、その親御さんへの助言などを次回語ってみたい。(つづく)
2025年9月 8日 16:53