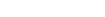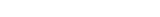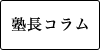カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (3)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > 英語は数学と国語の"中間子"である
コラム
英語は数学と国語の"中間子"である
前回語ったように、中高生が、志望の大学へ行ける、希望の高等教育課程へと進める、その分岐点は、初等教育から中等教育へ進んだ段階の、<自己の学びの維新>の自覚、そして覚悟であり、それが命運をわけるということは明々白々なのである。ビジネスの成功体験から中学受験の合格を逆照射すれば、その相似形がわかるというものだ。
では、その我が生徒、我が子への具体的処方箋とでも申すますか、また、指標ともいいますか、その学びの通過儀礼で行うべきアドヴァイスを語ってみることにします。
小学生の時代、国算理社(国語・算数・理科・社会)が、4大メイン科目でもあり、その科目の配列こそ、その重要性を物語ってもいよう。「小学生で、大切なのは、一に国語、二に国語、三、四がなくて、五に算数、パソコン(プログラミング)、英会話、こんなのどうでもいい。」(藤原正彦)の名言が文字通り雄弁に証明してもいよう。
では、それが、中学生になると、英数国理社(英語・数学・国語・理科・社会)という科目配列になる。これも、中等教育における教科の重要性の証左ともなっているし、また、12才以降の新教科の登場への自覚を促すものともなっていよう。
小学校にしろ、中学校にしろ、その教科の呼称の配列{国数理社⇒英数国理社}に意識を向ける者はほとんどいない。実は、この配列というものが、教育上非常に重要な学びの真理を物語ってもいるということを。
平成の後半から、小学校で、英語が正規の教科となってはいても、やはり、令和7年の現在でも、英語は中学生になっての段階での勝負科目であることは変わりはない。その証拠に、中学受験で、開成・麻布・桜蔭などの超進学校では、入試科目には、英語がない、また、そうした秀才・天才ぞろいの中高一貫校では、中学校からが、英語の勝ち負けを決める教科になるのである。この点は、世の親御さんは留意しておくべき点ではある。
まず、英語は、脇におくとしよう。問題は、数学である。これは、小学校の算数が、中学校へ移るや、数学という、看板名を変更した科目に変貌する。これは、江戸時代の、図形問題主流の和算が、明治期に入り、ユークリッド幾何学へと大転換した如きに、教科の革命が起こるのである。建前上、XやYといった記号はもちろん、様々な公式といったものを援用して解を求める行為へと激変する。
国語に関しても、小学校時代は、主に、おおむね物語文(小説)は主体となる国語の教科から、論説文主体の現代文へと大きく舵をきる。そして、中3頃になると、古文や漢文の入門・初級へと、古典という領域に足を踏み入れる。これも、小学生時代の、感性優先から、知性第一主義へと面舵一杯と、小学校時代の内海から、中学校時代の大海へと進み出る。
こうした、中学における数学と国語という教科に共通す項として、武器としての概念が、論理性というものとして浮上してくる。極端な言い方だが、数学は、算数とは異なり、様々な記号や公式を覚え、それを最大限、解を導き出すために自由自在にすることを至上命題とする。その駆使する能力は、実は、小学校時代の感性にある。この点で、国語の大切さ、算数で磨かれた“感性”が挙げられよう。また、一見飛躍と思われがちだが、算数における解法のセンスといったものが背後に、一応は隠れていても、それがうまく数学へと継承されうるかという学習上の類似性がある。この流れで、小学生時代は、算数が得意でも、数学が苦手となる原因が潜んでもいようか。苦手とならない少年は、小学校時代の算数へのプライドが、中学校時代数学への矜持へと連結している種族である。国語に関しても、小学生時代の、物語文読解のセンスとやらが、評論文主流の現代文でも、その感性とやらを論理へと脱皮、いや、その感性が論理性育成の肥料となっていない中高生は、現代文でもがき苦しむ羽目となる。ここに、小学校時代の国語の大切さの要因が潜んでもいる。
そうである。新教科である数学と国語(現代文)とに共通する、要諦ともなる概念が、まさしく、論理性というものとなる。この論理性とは、子供から大人へ成長する思春期の段階で、身に付けなくてはならない思考の武器でもある。これは、中等教育段階ともダブる思春期で、どれほど自覚をもって、ブラシュアップするかが、ある意味、私大と国立かの受験選択の命運をわけるものともなる。大方、この点で、教師や親の責任は重大なのだ。なぜなら、この思春期の最大の性質は、知性、感性、どちらにしろ、論理性を心理的・生理的に拒否してしまう、一種、ホモサピエンス(社会的動物)になることを拒み続ける、人間の動物的本能が最大限にして、最終的に、暴れまわる時期でもあるからだ。この意味でも、この暴れ馬を御する騎手としての教師や親という存在が重要でもあるということだ。
英語は、数学と国語にまたがる教科である、その両者に論理性を啓蒙する、鼓舞する、そういう意味でも大切なのである。いわば、英語は、数学(陽子)と国語(中性子)の“中間子”のような役割を果たしていうということだ。次回、この英語という“中間子”としての科目の役割、意義といったものを語ってみたい。(つづく)
では、その我が生徒、我が子への具体的処方箋とでも申すますか、また、指標ともいいますか、その学びの通過儀礼で行うべきアドヴァイスを語ってみることにします。
小学生の時代、国算理社(国語・算数・理科・社会)が、4大メイン科目でもあり、その科目の配列こそ、その重要性を物語ってもいよう。「小学生で、大切なのは、一に国語、二に国語、三、四がなくて、五に算数、パソコン(プログラミング)、英会話、こんなのどうでもいい。」(藤原正彦)の名言が文字通り雄弁に証明してもいよう。
では、それが、中学生になると、英数国理社(英語・数学・国語・理科・社会)という科目配列になる。これも、中等教育における教科の重要性の証左ともなっているし、また、12才以降の新教科の登場への自覚を促すものともなっていよう。
小学校にしろ、中学校にしろ、その教科の呼称の配列{国数理社⇒英数国理社}に意識を向ける者はほとんどいない。実は、この配列というものが、教育上非常に重要な学びの真理を物語ってもいるということを。
平成の後半から、小学校で、英語が正規の教科となってはいても、やはり、令和7年の現在でも、英語は中学生になっての段階での勝負科目であることは変わりはない。その証拠に、中学受験で、開成・麻布・桜蔭などの超進学校では、入試科目には、英語がない、また、そうした秀才・天才ぞろいの中高一貫校では、中学校からが、英語の勝ち負けを決める教科になるのである。この点は、世の親御さんは留意しておくべき点ではある。
まず、英語は、脇におくとしよう。問題は、数学である。これは、小学校の算数が、中学校へ移るや、数学という、看板名を変更した科目に変貌する。これは、江戸時代の、図形問題主流の和算が、明治期に入り、ユークリッド幾何学へと大転換した如きに、教科の革命が起こるのである。建前上、XやYといった記号はもちろん、様々な公式といったものを援用して解を求める行為へと激変する。
国語に関しても、小学校時代は、主に、おおむね物語文(小説)は主体となる国語の教科から、論説文主体の現代文へと大きく舵をきる。そして、中3頃になると、古文や漢文の入門・初級へと、古典という領域に足を踏み入れる。これも、小学生時代の、感性優先から、知性第一主義へと面舵一杯と、小学校時代の内海から、中学校時代の大海へと進み出る。
こうした、中学における数学と国語という教科に共通す項として、武器としての概念が、論理性というものとして浮上してくる。極端な言い方だが、数学は、算数とは異なり、様々な記号や公式を覚え、それを最大限、解を導き出すために自由自在にすることを至上命題とする。その駆使する能力は、実は、小学校時代の感性にある。この点で、国語の大切さ、算数で磨かれた“感性”が挙げられよう。また、一見飛躍と思われがちだが、算数における解法のセンスといったものが背後に、一応は隠れていても、それがうまく数学へと継承されうるかという学習上の類似性がある。この流れで、小学生時代は、算数が得意でも、数学が苦手となる原因が潜んでもいようか。苦手とならない少年は、小学校時代の算数へのプライドが、中学校時代数学への矜持へと連結している種族である。国語に関しても、小学生時代の、物語文読解のセンスとやらが、評論文主流の現代文でも、その感性とやらを論理へと脱皮、いや、その感性が論理性育成の肥料となっていない中高生は、現代文でもがき苦しむ羽目となる。ここに、小学校時代の国語の大切さの要因が潜んでもいる。
そうである。新教科である数学と国語(現代文)とに共通する、要諦ともなる概念が、まさしく、論理性というものとなる。この論理性とは、子供から大人へ成長する思春期の段階で、身に付けなくてはならない思考の武器でもある。これは、中等教育段階ともダブる思春期で、どれほど自覚をもって、ブラシュアップするかが、ある意味、私大と国立かの受験選択の命運をわけるものともなる。大方、この点で、教師や親の責任は重大なのだ。なぜなら、この思春期の最大の性質は、知性、感性、どちらにしろ、論理性を心理的・生理的に拒否してしまう、一種、ホモサピエンス(社会的動物)になることを拒み続ける、人間の動物的本能が最大限にして、最終的に、暴れまわる時期でもあるからだ。この意味でも、この暴れ馬を御する騎手としての教師や親という存在が重要でもあるということだ。
英語は、数学と国語にまたがる教科である、その両者に論理性を啓蒙する、鼓舞する、そういう意味でも大切なのである。いわば、英語は、数学(陽子)と国語(中性子)の“中間子”のような役割を果たしていうということだ。次回、この英語という“中間子”としての科目の役割、意義といったものを語ってみたい。(つづく)
2025年9月15日 16:19