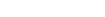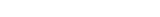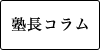カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2026年2月 (4)
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (3)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > 学校当局者の責務~英数国を通して~
コラム
学校当局者の責務~英数国を通して~
これまで、特に、英数国という中等教育の要となる教科が、英語が中間子となり、左右の数学と国語と連結しているとか、また、五輪ならぬ、三輪の如く、論理性をコアに、英語の成績を伸ばせば(正しく指導するという前提で:英文法主体で、英単語を暗記し、それに付随して漢字の語彙の強化)、自ずと、左部の数学と右部の国語が上昇するという私見を述べてまいりました。それは、現場生徒の学習メンタルの成長とも比例するので、本来各自の、小学校までの学びのバックグラウンドが十人十色で、十把一絡げとは、現実的には、私見通りにはいかないケースを前提に申しあげているまでです。ここでも、“理論と実践とは必ずしも一致せず”が当てはまります。
これこそ、現場指導者でもある教師、校長、理事長などがそのかじ取り役として、重要な役割を果たすのは言うまでもありません。これは、企業における社長、国家における総理という存在が、社員、国民の安寧・幸福を、ある程度左右するのと同じ関係にあると認識していない学校関係者が余りに多い。いや、そうしている、そう心掛けていると語る学校運営の上層部は、幻想を抱いているに過ぎません。「人を見て法を説け」ではありませんが、公立の超名門校麹町中学校で成功した手法を、ヘッドハンティングされた、進学校としては標準の、いや、非進学校の、私立の中高一貫校創英学園で、失敗した工藤勇一氏しかり、西武黄金時代を築いた森祇晶監督が、その後、横浜ベイスターズで何の功績も残さず、去っていったケースしかりであります。そうした事例こそ「成功体験は一日で捨て去れ」に該当するケースでもありましょうや!こうしたケースなど、人生で二度、<僥倖なる勲章>はもらえないという事実でもありましょうか。「名選手、必ずしも名監督に非ず」という通説を裏付けてもくれます。
大学では、新年度、様々なオリエンテーションなるものが、4月から5月初旬まで行われます。様々な科目、講座、教授など、アラカルト方式で、入学したての一年生に行われるものです。実は、特に、私立の中高一貫校の、あの難しい(国語・算数・理科・社会)問題を経てきた少年少女に、新たな教科、英語、数学、国語(現代文・古文・漢文)を学ぶ意義、そして、その共通概念、まるで、三つの団子を串刺しにする、竹製の串、それこそが論理性であるということを、啓蒙的にガイダンスしなければならないのです。当然、そのガイダンスだけで終わりではありません。それぞれの教師が、数学なら、どうして算数から名称が変わったのか?その意義を、その問いかけを。小学校時代の話せる英語から、英単語がきちんと書けて、英文を明解に読み込め、そして、英文を、日記・手紙程度なら書ける域に到達する必要性、国語なら、小説主体の授業から論説文主流の授業へどうして移行したのか、どうして、日本語が話せて読めるのに、わざわざ“日本語”を、国語の授業で学ばなければならないのか?中3から高1にかけての生徒には、古文はどうしてやるべきなのか、古典を学ぶその意義の哲学的問いをするのです。また、古文には、古典文法が絶対に必要であること、それは、英文法の重要性に優るとも劣らぬくらいのものであるということの自覚への啓蒙授業です。そして、各教科の先生は、数学における論理性・抽象性の、英語にもまた、英文の背後にあるそれと比類した論理性・抽象性があること、更に、現代文でも、明治以降に生まれた様々な語彙、それから派生する概念や、文構造が、外国語という論理体系の下に生まれ、生成され、進化を遂げてきた経緯、それを背景に、現代の日本語がうごめいていることを、分かりやすく、また、おもしろく説明してあげる義務を教師が背負っているという、学びの実体、即ち、“なぜ学び?どのように学ぶべきなのか?”それを強烈に意識させる必要があるのです。余談ではありますが、弊塾では、古文、古典文法を教える際に、英語をフル活用して教えています。古文の助動詞も英語の助動詞も、その働きの仕組みはほぼ同じであると言うと、彼らは、目から鱗状態、学びの刮目をするわけです。古文は、我々の用いる現代文より、むしろ英語に近い、いや、そうした自覚を持たせなければ、古文なんぞは読み込めないのです。こうした体験は、小学校の“~算”と称される問題のほとんどが、中学校の数学の武器、XとYとを用いた方程式を用いると大方解けてしまう快感に似て非ではないと存じます。私が、某学校の理事長、また、校長であれば、古文の教師と英語教師のコラボ授業など、様々な学校改革プランを持ってもいます。そのプランを、横浜の場末の塾で実践しているにすぎないのであります。
現代、いや、ここ数十年、高等教育では、リベラルアーツを中心に、学際的(※これは、私の記憶が確かなら、1991年SFC誕生の頃からだろうと存じます)なる概念の重要性が浮上してきてもいます。生成AIの驚異的な進化・進歩を目の当たりにしている昨今、大学では、人文科学系の学問に光が当たってきてもいます。何も、学際的なる教育とは、大学の専売特許ではありません。この兆候は、令和に入って、歴史総合やら、地理総合、公共など、従来にない教科の出現を目の当たりにしていますが、これは、表層的なカリィキュラムにすぎません。もっと現場、学校では、その深層的、英数国を貫く、学際性というものを、中高生に覚醒させる責任があると思うのですが、如何でありましょうや?
これこそ、現場指導者でもある教師、校長、理事長などがそのかじ取り役として、重要な役割を果たすのは言うまでもありません。これは、企業における社長、国家における総理という存在が、社員、国民の安寧・幸福を、ある程度左右するのと同じ関係にあると認識していない学校関係者が余りに多い。いや、そうしている、そう心掛けていると語る学校運営の上層部は、幻想を抱いているに過ぎません。「人を見て法を説け」ではありませんが、公立の超名門校麹町中学校で成功した手法を、ヘッドハンティングされた、進学校としては標準の、いや、非進学校の、私立の中高一貫校創英学園で、失敗した工藤勇一氏しかり、西武黄金時代を築いた森祇晶監督が、その後、横浜ベイスターズで何の功績も残さず、去っていったケースしかりであります。そうした事例こそ「成功体験は一日で捨て去れ」に該当するケースでもありましょうや!こうしたケースなど、人生で二度、<僥倖なる勲章>はもらえないという事実でもありましょうか。「名選手、必ずしも名監督に非ず」という通説を裏付けてもくれます。
大学では、新年度、様々なオリエンテーションなるものが、4月から5月初旬まで行われます。様々な科目、講座、教授など、アラカルト方式で、入学したての一年生に行われるものです。実は、特に、私立の中高一貫校の、あの難しい(国語・算数・理科・社会)問題を経てきた少年少女に、新たな教科、英語、数学、国語(現代文・古文・漢文)を学ぶ意義、そして、その共通概念、まるで、三つの団子を串刺しにする、竹製の串、それこそが論理性であるということを、啓蒙的にガイダンスしなければならないのです。当然、そのガイダンスだけで終わりではありません。それぞれの教師が、数学なら、どうして算数から名称が変わったのか?その意義を、その問いかけを。小学校時代の話せる英語から、英単語がきちんと書けて、英文を明解に読み込め、そして、英文を、日記・手紙程度なら書ける域に到達する必要性、国語なら、小説主体の授業から論説文主流の授業へどうして移行したのか、どうして、日本語が話せて読めるのに、わざわざ“日本語”を、国語の授業で学ばなければならないのか?中3から高1にかけての生徒には、古文はどうしてやるべきなのか、古典を学ぶその意義の哲学的問いをするのです。また、古文には、古典文法が絶対に必要であること、それは、英文法の重要性に優るとも劣らぬくらいのものであるということの自覚への啓蒙授業です。そして、各教科の先生は、数学における論理性・抽象性の、英語にもまた、英文の背後にあるそれと比類した論理性・抽象性があること、更に、現代文でも、明治以降に生まれた様々な語彙、それから派生する概念や、文構造が、外国語という論理体系の下に生まれ、生成され、進化を遂げてきた経緯、それを背景に、現代の日本語がうごめいていることを、分かりやすく、また、おもしろく説明してあげる義務を教師が背負っているという、学びの実体、即ち、“なぜ学び?どのように学ぶべきなのか?”それを強烈に意識させる必要があるのです。余談ではありますが、弊塾では、古文、古典文法を教える際に、英語をフル活用して教えています。古文の助動詞も英語の助動詞も、その働きの仕組みはほぼ同じであると言うと、彼らは、目から鱗状態、学びの刮目をするわけです。古文は、我々の用いる現代文より、むしろ英語に近い、いや、そうした自覚を持たせなければ、古文なんぞは読み込めないのです。こうした体験は、小学校の“~算”と称される問題のほとんどが、中学校の数学の武器、XとYとを用いた方程式を用いると大方解けてしまう快感に似て非ではないと存じます。私が、某学校の理事長、また、校長であれば、古文の教師と英語教師のコラボ授業など、様々な学校改革プランを持ってもいます。そのプランを、横浜の場末の塾で実践しているにすぎないのであります。
現代、いや、ここ数十年、高等教育では、リベラルアーツを中心に、学際的(※これは、私の記憶が確かなら、1991年SFC誕生の頃からだろうと存じます)なる概念の重要性が浮上してきてもいます。生成AIの驚異的な進化・進歩を目の当たりにしている昨今、大学では、人文科学系の学問に光が当たってきてもいます。何も、学際的なる教育とは、大学の専売特許ではありません。この兆候は、令和に入って、歴史総合やら、地理総合、公共など、従来にない教科の出現を目の当たりにしていますが、これは、表層的なカリィキュラムにすぎません。もっと現場、学校では、その深層的、英数国を貫く、学際性というものを、中高生に覚醒させる責任があると思うのですが、如何でありましょうや?
2025年9月29日 16:49