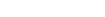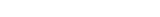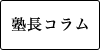カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2026年2月 (4)
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (3)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > <自由と規律>のバランスに欠けた令和
コラム
<自由と規律>のバランスに欠けた令和
今の天皇陛下が、独身で、英国留学されていた頃、昭和の時代である。浩宮殿下が、メディアの質問か何かで、「何か、お好きな書は、ございますか?」と質問をされた際、『自由と規律』(池田潔)という岩波新書を挙げられていたことが、今でも印象深く記憶に残っている。この、デジタルファシズムとも言われる昨今、SNS社会において、時折、早朝の日課のウォーキングをしている最中、脳裏に、ふと、不思議と浮かんでくる、その遠因なるものを思索してみると、この現代、21世紀、令和という時代における、様々なる温故知新とでも申しましょうか、現代にける病理の処方箋なるヒントがあるではないかと、この書が想起されてもくるのであります。
この“自由と規律”とは、勉学やスポーツであれ、自ら規律を持って臨み、それを基盤として自由な発想を育成し、人格を涵養してゆくというイギリスのパブリックスクール(日本の、私立の中高一貫校)に由来する教育理念であり、慶應大学教授の池田潔が、英国留学中に、新渡戸稲造が“武士道”を日本人の見えざる倫理としてまとめたように、外国人でもある日本人が、英国紳士の“卵=ノーブレス・オブリージュのひな型”の理念をまとめたようなものでもある。
この理念は、芸術でも、水墨画、江戸文化、これらが、ある制約=規律の足かせがあって、独特の、独自の、独創的なジャンルのアートを生み出した、芸術の法則とも通底してもいよう。いや、ワインやウィスキーといった樽の中で長き熟成を経て、芳醇な液体としての飲み物として生まれかわる自然の摂理とも似通ってもいよう。
この自由と規律という概念は、人間行動を導く、二つの、それぞれを諫める、けん制する、逆のベクトルの役割をしているとも申せましょう。民主主義国家と独裁国家、資本主義と社会主義、革新と保守など、様々な政治的次元でも該当する概念ではありますが、そうした上部構造的な論は、このコラムではふさわしくない、もっと、次元を下げた、下部構造的、個人的、庶民的、そして教育的次元で敷衍してみたい。
今や、社会の多元化、多様化が叫ばれ、少子化、ジェンダー化(ユニセックス化)が学校レベルにまで下りてきたのか、校則(ピンからキリまである校則全て)の撤廃から服装の多様化、時に、私服化にいたるまで、規律を緩和、撤廃、そして自由の推進へと、特に、教えない教育、自主性に基づく学びなど、綺麗な理念で、社会的通念を学校的通念にまで下げて、適用しようとする風潮があちらこちらで目に付きます。これは、私見ではありますが、天才・秀才などで成功したケーススタディーを、準秀才(がり勉から凡才に至る)如何に当てはめようとする牽強付会的言説なのであります。
灘、麻布、筑駒など、超超進学校などは、私服で有名です。また、学びにおいても当局は、自由放任、彼らの自主性に任せています。基礎学力と将来の目標・目的が明確であれば、自らを律する克己が、自身の中等教育のprincipleの無意識なる“憲法”ともなっている。丁度、英国のパブリックスクールと同類の少年であります。余談ではありますが、あの工藤勇一氏が、都内でトップともいえる公立中学麹町中学校で、“学校の当たり前をやめた”、その手法が、成功するのも当然といわねばなりません。彼らには、目的・目標に裏打ちされた学びの規律がある最多集団でもあるからです。これが、神奈川の超超標準校創英学園で、同じことをやっても成功するわけもありません。西武グループの黄金期、総帥堤義明が、長野オリンピックのフィクサーとしても絶大な権力を有していた時代、西武ライオンズが森祇晶監督のもと、黄金期を築き上げたその手法を、弱小で、フロントも大して力もなく、財力もない横浜ベイスターに招聘されても、まったく、何の実績も上げずに、自身の晩節をキャリアの面で汚した事例も同じであります。ものごとの深層とは、そんなものです。少々熟慮をすれば、誰でも気づく真実です。これも、よく雑誌のアエラ等で目にする傾向ですが、“令和の高校生は、東大よりもハーバードをめざす”といった特集です。失われた30年で、GDPが、三分の一にまでなった日本で、そんなキャッチコピー通りに夢かなう高校生は、“べらぼうな学力”か“べらぼうな財力”を有する者のみです。
この自由と規律とは、現今、教育面、学校関係者、地方自治体(愛知県の豊明市のスマホ使用の1日2時間以内の条例)、国家レベル(オーストラリアの16才未満のSNS禁止)を見るまでもでもなく、デジタルとアナログとの関係にも集約できます。SNS情報とオールドメディア情報(地上波のニュースや新聞・雑誌など)、便利さ、快適さというものに靡く人間の弱さともいいえるものかもしれません。性善説を信じて、法のない社会でも人間は悪を犯さず、秩序を維持し、幸福に生きていける、そういった楽天的側面が、規律をなるべくなくし、自由を与えようとする、放任主義、放縦主義の顕れ、それが、SNS社会の影の部分、弊害でもあります。学校レベルで申しますと、麹町中学校の“学校のあたり前”をやめた一例で、定期試験をやめたがあります。これなんぞは、当校の生徒のほとんどが、中学受験失敗組、その敗者が、3年後、そのリベンジをする目的で、放課後に、エイリート塾に夜遅くまで通う日課(ルーティン)がある、それゆえ、むしろ、学校が息抜き、リラックスの場と化している事実、それが、相乗効果のプラスとなったに過ぎません。これなども、普通の公立中学校で行ってみなさい、その学校の中学生は、志望の県立高校へと進めない者が続出する悲惨な末路が待ち構えてもいることは想像に難くない。
9月3日の朝日新聞の記事に、野田秀樹氏のインタビューが載っていた。「人が何かを受け止める順番は『感じる・考える・信じる』のはずなのに、最近は『考える』が抜け落ちて、『感じる・信じる』が直結しているのではないか」、これを、野田氏は、「近年のSNS社会は“stupid network society”ではないですか!」と皮肉ってもいる。
この考える大本とは、まさしく、“規律”というものです。その喪失が令和という時代でもあるのです。
この“自由と規律”とは、勉学やスポーツであれ、自ら規律を持って臨み、それを基盤として自由な発想を育成し、人格を涵養してゆくというイギリスのパブリックスクール(日本の、私立の中高一貫校)に由来する教育理念であり、慶應大学教授の池田潔が、英国留学中に、新渡戸稲造が“武士道”を日本人の見えざる倫理としてまとめたように、外国人でもある日本人が、英国紳士の“卵=ノーブレス・オブリージュのひな型”の理念をまとめたようなものでもある。
この理念は、芸術でも、水墨画、江戸文化、これらが、ある制約=規律の足かせがあって、独特の、独自の、独創的なジャンルのアートを生み出した、芸術の法則とも通底してもいよう。いや、ワインやウィスキーといった樽の中で長き熟成を経て、芳醇な液体としての飲み物として生まれかわる自然の摂理とも似通ってもいよう。
この自由と規律という概念は、人間行動を導く、二つの、それぞれを諫める、けん制する、逆のベクトルの役割をしているとも申せましょう。民主主義国家と独裁国家、資本主義と社会主義、革新と保守など、様々な政治的次元でも該当する概念ではありますが、そうした上部構造的な論は、このコラムではふさわしくない、もっと、次元を下げた、下部構造的、個人的、庶民的、そして教育的次元で敷衍してみたい。
今や、社会の多元化、多様化が叫ばれ、少子化、ジェンダー化(ユニセックス化)が学校レベルにまで下りてきたのか、校則(ピンからキリまである校則全て)の撤廃から服装の多様化、時に、私服化にいたるまで、規律を緩和、撤廃、そして自由の推進へと、特に、教えない教育、自主性に基づく学びなど、綺麗な理念で、社会的通念を学校的通念にまで下げて、適用しようとする風潮があちらこちらで目に付きます。これは、私見ではありますが、天才・秀才などで成功したケーススタディーを、準秀才(がり勉から凡才に至る)如何に当てはめようとする牽強付会的言説なのであります。
灘、麻布、筑駒など、超超進学校などは、私服で有名です。また、学びにおいても当局は、自由放任、彼らの自主性に任せています。基礎学力と将来の目標・目的が明確であれば、自らを律する克己が、自身の中等教育のprincipleの無意識なる“憲法”ともなっている。丁度、英国のパブリックスクールと同類の少年であります。余談ではありますが、あの工藤勇一氏が、都内でトップともいえる公立中学麹町中学校で、“学校の当たり前をやめた”、その手法が、成功するのも当然といわねばなりません。彼らには、目的・目標に裏打ちされた学びの規律がある最多集団でもあるからです。これが、神奈川の超超標準校創英学園で、同じことをやっても成功するわけもありません。西武グループの黄金期、総帥堤義明が、長野オリンピックのフィクサーとしても絶大な権力を有していた時代、西武ライオンズが森祇晶監督のもと、黄金期を築き上げたその手法を、弱小で、フロントも大して力もなく、財力もない横浜ベイスターに招聘されても、まったく、何の実績も上げずに、自身の晩節をキャリアの面で汚した事例も同じであります。ものごとの深層とは、そんなものです。少々熟慮をすれば、誰でも気づく真実です。これも、よく雑誌のアエラ等で目にする傾向ですが、“令和の高校生は、東大よりもハーバードをめざす”といった特集です。失われた30年で、GDPが、三分の一にまでなった日本で、そんなキャッチコピー通りに夢かなう高校生は、“べらぼうな学力”か“べらぼうな財力”を有する者のみです。
この自由と規律とは、現今、教育面、学校関係者、地方自治体(愛知県の豊明市のスマホ使用の1日2時間以内の条例)、国家レベル(オーストラリアの16才未満のSNS禁止)を見るまでもでもなく、デジタルとアナログとの関係にも集約できます。SNS情報とオールドメディア情報(地上波のニュースや新聞・雑誌など)、便利さ、快適さというものに靡く人間の弱さともいいえるものかもしれません。性善説を信じて、法のない社会でも人間は悪を犯さず、秩序を維持し、幸福に生きていける、そういった楽天的側面が、規律をなるべくなくし、自由を与えようとする、放任主義、放縦主義の顕れ、それが、SNS社会の影の部分、弊害でもあります。学校レベルで申しますと、麹町中学校の“学校のあたり前”をやめた一例で、定期試験をやめたがあります。これなんぞは、当校の生徒のほとんどが、中学受験失敗組、その敗者が、3年後、そのリベンジをする目的で、放課後に、エイリート塾に夜遅くまで通う日課(ルーティン)がある、それゆえ、むしろ、学校が息抜き、リラックスの場と化している事実、それが、相乗効果のプラスとなったに過ぎません。これなども、普通の公立中学校で行ってみなさい、その学校の中学生は、志望の県立高校へと進めない者が続出する悲惨な末路が待ち構えてもいることは想像に難くない。
9月3日の朝日新聞の記事に、野田秀樹氏のインタビューが載っていた。「人が何かを受け止める順番は『感じる・考える・信じる』のはずなのに、最近は『考える』が抜け落ちて、『感じる・信じる』が直結しているのではないか」、これを、野田氏は、「近年のSNS社会は“stupid network society”ではないですか!」と皮肉ってもいる。
この考える大本とは、まさしく、“規律”というものです。その喪失が令和という時代でもあるのです。
2025年10月13日 16:10