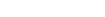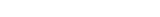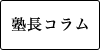カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (3)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > 成功の反対は失敗?自由の反対は不自由?
コラム
成功の反対は失敗?自由の反対は不自由?
「成功の反対は、失敗ではなく妥協である」この言葉は、吉本興業の名プロデューサー木村政雄のものです。この名言には、人間の本性、人間の弱さ、人間のファジーさ、こうした側面が、映し出されてもいます。
「東大がだめなら、高卒で働くよ。お父さん!」ここまで、両親に断言して受験勉強する高校生はいない。そう宣言しておきながら、内心は、高1の段階で、「早稲田に行ければ十分だな!」と思い、ハードルを下げる、そして高3になると「MARCHのどこかに行ければいいや!」とさらに弱気になる。現実の受験勉強の困難さ、努力の限界、自身の能力、こうしたものを自身で烙印を押し、厳しい現実から逃避しようとする。こうしたメンタルが、妥協の本性でもあろう。余談だが、政治、交渉とは、むしろ良い妥協が成功とされるのとは対照的でもあろう。自身との交渉では、負けの部類に入ることを、木村氏は語ってもいよう。
受験のみならず、就活にしろ、ビジネスにしろ、こうした、成功と失敗とのはざまにある、グレーゾーンで、消極的満足をし、人生行路を進んでゆくというものが、悲しいかな、人間の本性でもあろう。本来の人間の精神とは、この灰色ゾーンの中に、どれだけ自己満足、自己肯定感、ささやかな幸福感を見出だすか、それが、生き方の、ある意味、上手なノウハウともなろう。米津玄師、林修、為末大なども口をそろえていう言葉、「努力は、報われない方が多い!」に、禅僧的悟りを一般人は見出だし、そこから、初めて、人生とは如何なりや?の公案を突き付けられる。そこから、真の考えが立ち上がってもくる。
実は、人間らしいとは、こうしたスタートラインに立つことが肝要なのである。失敗を肥やしに、それを成功に転化する否かは、こうした心の持ち様でもあろう。つまりは、成功の反対は、失敗に見えても、その内奥は、妥協が姿を変えたものが大半なのである。これと似たようなことを芥川龍之介も吐いている、「人生は、地獄よりも地獄的である」と。
成功の反対を、失敗とするは、辞書的文脈で、妥協とするは、人性論的文脈で、それぞれ字義が適ってもいる。実は、ここにも、デジタルとアナログという対照的流儀が浮上しもくる。
デジタルは、0と1との二進法でできている、曖昧さを拒絶する性質のものだ、一方、アナログとは、0と1では割り切れない、0と1との間にある、少数や分数の値が無限にあり、それは、人間の数だけ、個性があるように、その人間のキャラは十人十色であるということでもある。人生の幸福が、人さまざまであるように、また、人生の後半、晩年、死ぬ間際で、そうでもなければならない。その人の人生が正解など、神のみぞ知るである。
色の3原色(赤・青・黄)があるように、赤、青、黄が、幸福ゾーンと人は、人は見なしやすい、しかし、自身が、色を組み合わせ、配色し、自身のカラーを、独自の魅力的カラーを作り出すのが人生である、それが、幸福のオリジナリティーというものである。実は、幸福の3原色(裕福な出自に生まれ、それ自体が存在感のオーラを放つ:平安時代の、皇族の家系;平氏の家系;源氏の家系)に対比して、それこそが、人生の成功と見なす、そうした通俗性(赤、青、黄がいいなと思う!そうした心根)から脱皮すること、これができない種族を、親ガチャ族とも言えようか?しかし、彼らにも、彼らなりの大義名分とやらがあることを斟酌しなくてはならないのは言うまでもない。
赤と緑と黄を混ぜると、黒が生まれる、この黒、不幸、死、絶望のメタファーを暗示する。その色の調合、配分、これこそが、幸せの真の姿でもあろうか。因に、印象派は、これらを混ぜず、カンバスの上の、ただ置いた、その色の視覚効果を、離れてみて、初めてその画風とした。この手法にも、人生を生きるヒントが学べもする。
超一流の、一貫校に、ぎりぎり合格し、その後6年、学業の側面から暗な、鬱な生活を送るよりも、一流か、準一流の進学校に入学して、学業以外の自己の強みを見出だし、個性に研磨をかけるという道筋も、いい意味での、成功の反対の妥協かもしれない。だが、こうした積極的妥協を、プラスに転じるは、「他人の芝生は青く見える」という、比較精神の悪しき気質が足を引っ張り、なかなかできるものではない。
デジタル思考とは、成功の反対は失敗と決めつけることで、次の段階へすすむロイター版を放棄したようなものである。できた、ダメだった、この白黒の二元論的なものだ。一方、アナログ志向とは、悪しき妥協の精神、これは、ある意味、自己の限界を知る、我を知るということでもあり、そこにこそ自己の本来の姿を見出だす“楽園”があるとする心的姿勢なのである。
一般論的に申せば、世は、いじめ、いやがらせ、学校の環境から、不登校、引きこもり、時に、自殺すらもたらす思考回路の少年少女は、実は、デジタル思考の典型的人間の姿を露わしてもいようか。パソコンやゲーム、スマホといったデジタル器機がそうさせてもいると考えるのは論理の飛躍であろうか?
最後に、前回も語ったことだが、自由の反対を不自由とみるか、それは、成功の反対は失敗と考えるに等しいことだ。デジタル思考である。アナログ思考とは、その不自由を、自身の規律へと向ける、転化する姿勢、それを指す。自由の反意語を不自由と見るは、その真の自由の価値すら見誤る。それを、規律と見るは、自由という真の価値を深く認識させてもくれる。
アクセルを自由とする者、それしか知らぬ者は、減速を不自由と、悪と見なす。一方、その減速を、規律と見なす者は、真の自由を手にする。アクセルだけの車は、危ない、加速の快感のみである。ここに、車におけるブレーキという規律の存在意義が浮上する。
企業でいう、ホンダ技研工業の、本田宗一郎と藤沢武夫であり、総理大臣中曽根康弘と官房長官後藤田正晴であり、来年の大河ドラマ『豊臣兄弟』における秀吉と秀長でもある。組織や政治における、この両輪は、誰しも理解可能の範疇ではあるが、これが、自身の内面、自身の人生ともなると、眼力が鈍る、慧眼がもてないものである。(つづく)
「東大がだめなら、高卒で働くよ。お父さん!」ここまで、両親に断言して受験勉強する高校生はいない。そう宣言しておきながら、内心は、高1の段階で、「早稲田に行ければ十分だな!」と思い、ハードルを下げる、そして高3になると「MARCHのどこかに行ければいいや!」とさらに弱気になる。現実の受験勉強の困難さ、努力の限界、自身の能力、こうしたものを自身で烙印を押し、厳しい現実から逃避しようとする。こうしたメンタルが、妥協の本性でもあろう。余談だが、政治、交渉とは、むしろ良い妥協が成功とされるのとは対照的でもあろう。自身との交渉では、負けの部類に入ることを、木村氏は語ってもいよう。
受験のみならず、就活にしろ、ビジネスにしろ、こうした、成功と失敗とのはざまにある、グレーゾーンで、消極的満足をし、人生行路を進んでゆくというものが、悲しいかな、人間の本性でもあろう。本来の人間の精神とは、この灰色ゾーンの中に、どれだけ自己満足、自己肯定感、ささやかな幸福感を見出だすか、それが、生き方の、ある意味、上手なノウハウともなろう。米津玄師、林修、為末大なども口をそろえていう言葉、「努力は、報われない方が多い!」に、禅僧的悟りを一般人は見出だし、そこから、初めて、人生とは如何なりや?の公案を突き付けられる。そこから、真の考えが立ち上がってもくる。
実は、人間らしいとは、こうしたスタートラインに立つことが肝要なのである。失敗を肥やしに、それを成功に転化する否かは、こうした心の持ち様でもあろう。つまりは、成功の反対は、失敗に見えても、その内奥は、妥協が姿を変えたものが大半なのである。これと似たようなことを芥川龍之介も吐いている、「人生は、地獄よりも地獄的である」と。
成功の反対を、失敗とするは、辞書的文脈で、妥協とするは、人性論的文脈で、それぞれ字義が適ってもいる。実は、ここにも、デジタルとアナログという対照的流儀が浮上しもくる。
デジタルは、0と1との二進法でできている、曖昧さを拒絶する性質のものだ、一方、アナログとは、0と1では割り切れない、0と1との間にある、少数や分数の値が無限にあり、それは、人間の数だけ、個性があるように、その人間のキャラは十人十色であるということでもある。人生の幸福が、人さまざまであるように、また、人生の後半、晩年、死ぬ間際で、そうでもなければならない。その人の人生が正解など、神のみぞ知るである。
色の3原色(赤・青・黄)があるように、赤、青、黄が、幸福ゾーンと人は、人は見なしやすい、しかし、自身が、色を組み合わせ、配色し、自身のカラーを、独自の魅力的カラーを作り出すのが人生である、それが、幸福のオリジナリティーというものである。実は、幸福の3原色(裕福な出自に生まれ、それ自体が存在感のオーラを放つ:平安時代の、皇族の家系;平氏の家系;源氏の家系)に対比して、それこそが、人生の成功と見なす、そうした通俗性(赤、青、黄がいいなと思う!そうした心根)から脱皮すること、これができない種族を、親ガチャ族とも言えようか?しかし、彼らにも、彼らなりの大義名分とやらがあることを斟酌しなくてはならないのは言うまでもない。
赤と緑と黄を混ぜると、黒が生まれる、この黒、不幸、死、絶望のメタファーを暗示する。その色の調合、配分、これこそが、幸せの真の姿でもあろうか。因に、印象派は、これらを混ぜず、カンバスの上の、ただ置いた、その色の視覚効果を、離れてみて、初めてその画風とした。この手法にも、人生を生きるヒントが学べもする。
超一流の、一貫校に、ぎりぎり合格し、その後6年、学業の側面から暗な、鬱な生活を送るよりも、一流か、準一流の進学校に入学して、学業以外の自己の強みを見出だし、個性に研磨をかけるという道筋も、いい意味での、成功の反対の妥協かもしれない。だが、こうした積極的妥協を、プラスに転じるは、「他人の芝生は青く見える」という、比較精神の悪しき気質が足を引っ張り、なかなかできるものではない。
デジタル思考とは、成功の反対は失敗と決めつけることで、次の段階へすすむロイター版を放棄したようなものである。できた、ダメだった、この白黒の二元論的なものだ。一方、アナログ志向とは、悪しき妥協の精神、これは、ある意味、自己の限界を知る、我を知るということでもあり、そこにこそ自己の本来の姿を見出だす“楽園”があるとする心的姿勢なのである。
一般論的に申せば、世は、いじめ、いやがらせ、学校の環境から、不登校、引きこもり、時に、自殺すらもたらす思考回路の少年少女は、実は、デジタル思考の典型的人間の姿を露わしてもいようか。パソコンやゲーム、スマホといったデジタル器機がそうさせてもいると考えるのは論理の飛躍であろうか?
最後に、前回も語ったことだが、自由の反対を不自由とみるか、それは、成功の反対は失敗と考えるに等しいことだ。デジタル思考である。アナログ思考とは、その不自由を、自身の規律へと向ける、転化する姿勢、それを指す。自由の反意語を不自由と見るは、その真の自由の価値すら見誤る。それを、規律と見るは、自由という真の価値を深く認識させてもくれる。
アクセルを自由とする者、それしか知らぬ者は、減速を不自由と、悪と見なす。一方、その減速を、規律と見なす者は、真の自由を手にする。アクセルだけの車は、危ない、加速の快感のみである。ここに、車におけるブレーキという規律の存在意義が浮上する。
企業でいう、ホンダ技研工業の、本田宗一郎と藤沢武夫であり、総理大臣中曽根康弘と官房長官後藤田正晴であり、来年の大河ドラマ『豊臣兄弟』における秀吉と秀長でもある。組織や政治における、この両輪は、誰しも理解可能の範疇ではあるが、これが、自身の内面、自身の人生ともなると、眼力が鈍る、慧眼がもてないものである。(つづく)
2025年11月 3日 16:17