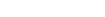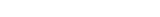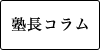カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
コラム
現代文参考書の解説のいかがわしさ
私の教え子で、10年近く前に東工大に進学したH君という男子生徒の弁です。
「東工大の数学の問題は、解法、突破口のような問題の切り口、入り口みたいなものを、ある意味、遠回りしながらでも、いわば、計算力で、時間をかければ何とか答えまで到達できるが、東大の数学は、その問題がお城だとすれば、その城攻めをどこから攻めればいいのか、その入り口が分からない。力という計算力と時間だけでは落城させられない難しさがある。その難しさを、センスとか閃きとか言ってしまえばそれまでだが、そんな閃きが求められるのが東大の数学なんです。」
数学くずれの、国立断念派の、私立文系に進んだ私としては、非常に印象深く記憶に残り続けていることばである。
これは英精塾の第一期卒業生(23年前)で、その後、神奈川県の某中学受験専門の進学塾の教室長となったO君が、私に語ってくれたこととダブって思えたものである。それは、次のような意見である。
「浅野学園くらいまでなら、日曜日や祝日をつぶしてまで、毎日マンツーマンで勉強を教えれば何とか合格させることができる自信がある。しかし、栄光学園や聖光学院レベルとなると、親御さんにその保証はできかねる。人の倍以上の努力で何とかなる進学校と何とかならない超進学校がある」※関東だと開成筑駒レベルとそれに準じるレベルの差、また関西だと灘や甲陽学院とそれに準じるレベルといったらいいだろうか?
この教え子のH君とO君との見解を反芻すると、実は、大学受験における現代文という科目に帰着するように思えて仕方がない。それはこういうことでもある。
一般の書店で売られている現代文の問題集や参考書の類の、その解法とやらで共通するのが、その重要箇所、またキーポイントの文に傍線が引かれていても、誰もが疑問を抱かぬ点である。
具体例を挙げよう。ある箇所A(作者の主張したコト)、そしてA’、更にはA”と類似箇所をAグループとして、様々な箇所に傍線が引かれている。また、それと対立する事項としてB(作者の意見とは反するコト)、そしてB’、更に、B”というように、傍線が引かれている。そして、そのAとBのグループを論理性といって、その参考書の筆者が解答へと誘導してゆく、その説明手法が殆どである。予備校のカリスマ講師もライブ授業で同じ戦術で問題をさばいてゆく。実は、ここに問題点があるのである。
大方、具体的に言わせてもらえば、実力は日東駒専レベルの生徒が、ワンランク上の志望校でもあるMARCHレベルの問題に立ち向かってゆく際に生じる、“疑問?”とやらである。それは、そのカリスマ現代文講師が、どうしてそこに傍線を引いたのか?何故この箇所が重要表現足りえているのか?「この言葉・語句をマルで囲め、重要だから!」と指摘した根拠はどこにあるのか?こうした、その入試問題を前にして、その講師の指摘する箇所に標準的な生徒が向き合い、同じように気づくか否か、それこそが実は<問題(参考書のいかがわしさ)>なのである。そうである。もう、その解答で線引きされて、二項対立とやらの論法で丸め込まれれば、どれが正解、不正解、ダミー選択肢か、誰も反論はできぬものである。
実は、この現代文を読み込む最中に、どの箇所が重要表現か、キーワードなのか、線引きしたりマルで囲んだりする行為が、数学という問題と格闘しながら、その解法のヒント、いわば、補助線をどこに引くのか、そのひらめきと通底しているものが、感性というルートでつながっているように思えて仕方がないのである。その感性とやらのあるなしの濃淡が、実は読書量、読書体験などがモノを言う領域なのである。これぞ学習上の<暗黙知>である。ある名工に弟子入りしても、後継者として大成するか、その道をあきらめるかといった分岐点と酷似している真実でもある。
数学の問題集の解答を見ても、その解法のルートがひらめくことがなければ、何題、何十題とベクトルや三角関数の問題を解いても、一向に成長したことにはならない。だから、数学は、凡人向けによく言われる通説として、「数学は暗記科目である!」という言説がある。鉄緑会を立ち上げた精神科医でもある和田秀樹氏の説である。しかし、いくら様々な問題を解いて、その解法をマスターして、その適用応用の戦略を強調しても、最後は、その適用や応用が頭に浮かんでくるか否かは、やはりセンスにゆきつくともいわれる。修練のたまものとも言えるセンスというものだろう。ここに、早稲田や難関私大の現代文・旧7帝大の二次の記述形式現代文と、標準的MARCHレベルの現代文との壁、開きがあることを誰も指摘しない。特に現代文講師本人がである。
これは個人的体験談だが、母校のI校に、仏文の大学院生の頃である、英語の教育実習で赴いた時のことである。
英語の授業を、すでに塾や予備校などで自身の“英文を如何に読むか?”の流儀を確立していた私は、授業の中で、「このItは、どうして強調構文のItでなくてはならないのか?」「このThatは、なぜ同格のThatであるのか?」などなど、詰め将棋的に理詰めで、文章を論理的に読む姿勢を教えていた数日後のことである。私の指導教官のT教諭は、「理屈もへったくりもなく、このItは初めから仮主語だと教えて、このThatは、関係代名詞だと記しをつけさせて教えなさい。」このように私に助言してきた、命じてきた。確かに教える立場からすれば、教えるのが楽である。また、生徒も、初めから頭を働かせることもなく「わかった!つもり?」とその場で実感をもち、その場の雰囲気も「何故?」を抱かせずに済む。そのT教諭は、私の高校3年生時の英語担当教師だった人である。あの頃は、何の疑問も抱かずに、そのT先生の授業を何食わぬ顔で受けていたが、浪人し、駿台予備校の英語の授業で刮目したのである。その経験があり、教育実習の際、伊藤和夫の『英文解釈教室』の流儀を分かりやすく標準的な生徒でもわかるように、噛んで含めるように、その手法を我流にアレンジして母校の高校生に教えていたわけである。しかし、その指導教官T先生は横やりを入れてきた。しかしT先生の指示を無視して、その後1週間、我流を貫いた。結果は、生徒から絶大な支持を受けた。「先生の英語の読み方、目からうろこです」「英語って、こう読むものなんですね!」教育実習生ながら、50代のヴェテラン英語教師より受けがよかった。教育実習の際の自慢話である。そのT先生は少々面白くなかったことであろう。宮城県の湊町の進学校である。仙台までローカル線で1時間以上かかる地方町である。ネット授業もスマホもない時代である。あの『英文解釈教室』のコンセプト、英文の読み方を懇切丁寧に理詰めで教えたのである。その“英文とは如何に読むべきか?”の伝授の成功体験が、その後のフランス語を捨て、受験英語を生業とする道を選んだ契機の一つになったかもしれない。
だいぶ横道に逸れてしまったようだ。本題に戻るとしよう。
現代文における、その参考書の筆者、またその授業の講師の、目の付け所、いわゆる、どこに傍線を引くか、また、どの言葉・語句にマル印をつけるのか、それは、数学における解法の突破口ともいえる、自身で無意識に補助線を引く勘に似てもいる。教えられる次元のものではない。この補助線なるものは、学力で培われて、引けたものか、否、もって生まれた地頭を基盤とするセンスによるものか、その相似関係をなすというのが現代文の解説から沸き起こってくる命題なのである。
高校1年レベルでの話である。このItが、非人称か、前出のものか、仮主語か、強調構文のものか、また、文脈でこのReasonという単語が「理由」か「理性」か、はたまた“動詞”なのか、そうした見極めが読解の最中に余裕で認識できる者は、英語も現段階では勝ち組でもある。二流、三流英語教師ではないが、初めから、そのItの正体は何なのか?また、初めからこのReasonとは、こういう意味であると、教えてしてしまうような現代文の参考書・問題集が殆どなのである。ここに、現代文という科目の、怪しさ、信頼性の薄さを感じてしまるのは私だけであろうか?
余談ながら、プロ野球の或るエピソードを挙げておく。よく教え子に話す逸話でもある。
昔巨人に中畑清という、元横浜ベイスターズの監督も務めた、今の巨人軍原辰徳監督のライバルの野手がいた。ある球団のピッチャーがまるきし、打てない。苦手投手である。その頃、世界のホームラン王、第一回国民栄誉賞者でもある王貞治監督は、数週間付きっ切りでマンツーマン指導したそうである。そして、対戦日の当日、その投手に全くの凡打に終わり、最終打席の後、王監督は、ベンチから出てきて「あれほど教えたのに、練習したのに、どうして打てないんだ!」と怒鳴りつけられた時、初めて‘雲上人’でもある王監督にくってかっかたそうである。「あんただから、あのピッチャーが打てるんでしょうが!俺は監督ほど才能もないっすよ!」と反論したそうである。これは理想の高い東大卒の教育ママが、我が子を観る目線に似てもいる。
東大の難問は秀才でも難しいものである。長嶋茂雄にとっての村山実、王貞治にとっての江夏豊、野村克也にとっての稲尾和久のようなものである。
(つづく)
「東工大の数学の問題は、解法、突破口のような問題の切り口、入り口みたいなものを、ある意味、遠回りしながらでも、いわば、計算力で、時間をかければ何とか答えまで到達できるが、東大の数学は、その問題がお城だとすれば、その城攻めをどこから攻めればいいのか、その入り口が分からない。力という計算力と時間だけでは落城させられない難しさがある。その難しさを、センスとか閃きとか言ってしまえばそれまでだが、そんな閃きが求められるのが東大の数学なんです。」
数学くずれの、国立断念派の、私立文系に進んだ私としては、非常に印象深く記憶に残り続けていることばである。
これは英精塾の第一期卒業生(23年前)で、その後、神奈川県の某中学受験専門の進学塾の教室長となったO君が、私に語ってくれたこととダブって思えたものである。それは、次のような意見である。
「浅野学園くらいまでなら、日曜日や祝日をつぶしてまで、毎日マンツーマンで勉強を教えれば何とか合格させることができる自信がある。しかし、栄光学園や聖光学院レベルとなると、親御さんにその保証はできかねる。人の倍以上の努力で何とかなる進学校と何とかならない超進学校がある」※関東だと開成筑駒レベルとそれに準じるレベルの差、また関西だと灘や甲陽学院とそれに準じるレベルといったらいいだろうか?
この教え子のH君とO君との見解を反芻すると、実は、大学受験における現代文という科目に帰着するように思えて仕方がない。それはこういうことでもある。
一般の書店で売られている現代文の問題集や参考書の類の、その解法とやらで共通するのが、その重要箇所、またキーポイントの文に傍線が引かれていても、誰もが疑問を抱かぬ点である。
具体例を挙げよう。ある箇所A(作者の主張したコト)、そしてA’、更にはA”と類似箇所をAグループとして、様々な箇所に傍線が引かれている。また、それと対立する事項としてB(作者の意見とは反するコト)、そしてB’、更に、B”というように、傍線が引かれている。そして、そのAとBのグループを論理性といって、その参考書の筆者が解答へと誘導してゆく、その説明手法が殆どである。予備校のカリスマ講師もライブ授業で同じ戦術で問題をさばいてゆく。実は、ここに問題点があるのである。
大方、具体的に言わせてもらえば、実力は日東駒専レベルの生徒が、ワンランク上の志望校でもあるMARCHレベルの問題に立ち向かってゆく際に生じる、“疑問?”とやらである。それは、そのカリスマ現代文講師が、どうしてそこに傍線を引いたのか?何故この箇所が重要表現足りえているのか?「この言葉・語句をマルで囲め、重要だから!」と指摘した根拠はどこにあるのか?こうした、その入試問題を前にして、その講師の指摘する箇所に標準的な生徒が向き合い、同じように気づくか否か、それこそが実は<問題(参考書のいかがわしさ)>なのである。そうである。もう、その解答で線引きされて、二項対立とやらの論法で丸め込まれれば、どれが正解、不正解、ダミー選択肢か、誰も反論はできぬものである。
実は、この現代文を読み込む最中に、どの箇所が重要表現か、キーワードなのか、線引きしたりマルで囲んだりする行為が、数学という問題と格闘しながら、その解法のヒント、いわば、補助線をどこに引くのか、そのひらめきと通底しているものが、感性というルートでつながっているように思えて仕方がないのである。その感性とやらのあるなしの濃淡が、実は読書量、読書体験などがモノを言う領域なのである。これぞ学習上の<暗黙知>である。ある名工に弟子入りしても、後継者として大成するか、その道をあきらめるかといった分岐点と酷似している真実でもある。
数学の問題集の解答を見ても、その解法のルートがひらめくことがなければ、何題、何十題とベクトルや三角関数の問題を解いても、一向に成長したことにはならない。だから、数学は、凡人向けによく言われる通説として、「数学は暗記科目である!」という言説がある。鉄緑会を立ち上げた精神科医でもある和田秀樹氏の説である。しかし、いくら様々な問題を解いて、その解法をマスターして、その適用応用の戦略を強調しても、最後は、その適用や応用が頭に浮かんでくるか否かは、やはりセンスにゆきつくともいわれる。修練のたまものとも言えるセンスというものだろう。ここに、早稲田や難関私大の現代文・旧7帝大の二次の記述形式現代文と、標準的MARCHレベルの現代文との壁、開きがあることを誰も指摘しない。特に現代文講師本人がである。
これは個人的体験談だが、母校のI校に、仏文の大学院生の頃である、英語の教育実習で赴いた時のことである。
英語の授業を、すでに塾や予備校などで自身の“英文を如何に読むか?”の流儀を確立していた私は、授業の中で、「このItは、どうして強調構文のItでなくてはならないのか?」「このThatは、なぜ同格のThatであるのか?」などなど、詰め将棋的に理詰めで、文章を論理的に読む姿勢を教えていた数日後のことである。私の指導教官のT教諭は、「理屈もへったくりもなく、このItは初めから仮主語だと教えて、このThatは、関係代名詞だと記しをつけさせて教えなさい。」このように私に助言してきた、命じてきた。確かに教える立場からすれば、教えるのが楽である。また、生徒も、初めから頭を働かせることもなく「わかった!つもり?」とその場で実感をもち、その場の雰囲気も「何故?」を抱かせずに済む。そのT教諭は、私の高校3年生時の英語担当教師だった人である。あの頃は、何の疑問も抱かずに、そのT先生の授業を何食わぬ顔で受けていたが、浪人し、駿台予備校の英語の授業で刮目したのである。その経験があり、教育実習の際、伊藤和夫の『英文解釈教室』の流儀を分かりやすく標準的な生徒でもわかるように、噛んで含めるように、その手法を我流にアレンジして母校の高校生に教えていたわけである。しかし、その指導教官T先生は横やりを入れてきた。しかしT先生の指示を無視して、その後1週間、我流を貫いた。結果は、生徒から絶大な支持を受けた。「先生の英語の読み方、目からうろこです」「英語って、こう読むものなんですね!」教育実習生ながら、50代のヴェテラン英語教師より受けがよかった。教育実習の際の自慢話である。そのT先生は少々面白くなかったことであろう。宮城県の湊町の進学校である。仙台までローカル線で1時間以上かかる地方町である。ネット授業もスマホもない時代である。あの『英文解釈教室』のコンセプト、英文の読み方を懇切丁寧に理詰めで教えたのである。その“英文とは如何に読むべきか?”の伝授の成功体験が、その後のフランス語を捨て、受験英語を生業とする道を選んだ契機の一つになったかもしれない。
だいぶ横道に逸れてしまったようだ。本題に戻るとしよう。
現代文における、その参考書の筆者、またその授業の講師の、目の付け所、いわゆる、どこに傍線を引くか、また、どの言葉・語句にマル印をつけるのか、それは、数学における解法の突破口ともいえる、自身で無意識に補助線を引く勘に似てもいる。教えられる次元のものではない。この補助線なるものは、学力で培われて、引けたものか、否、もって生まれた地頭を基盤とするセンスによるものか、その相似関係をなすというのが現代文の解説から沸き起こってくる命題なのである。
高校1年レベルでの話である。このItが、非人称か、前出のものか、仮主語か、強調構文のものか、また、文脈でこのReasonという単語が「理由」か「理性」か、はたまた“動詞”なのか、そうした見極めが読解の最中に余裕で認識できる者は、英語も現段階では勝ち組でもある。二流、三流英語教師ではないが、初めから、そのItの正体は何なのか?また、初めからこのReasonとは、こういう意味であると、教えてしてしまうような現代文の参考書・問題集が殆どなのである。ここに、現代文という科目の、怪しさ、信頼性の薄さを感じてしまるのは私だけであろうか?
余談ながら、プロ野球の或るエピソードを挙げておく。よく教え子に話す逸話でもある。
昔巨人に中畑清という、元横浜ベイスターズの監督も務めた、今の巨人軍原辰徳監督のライバルの野手がいた。ある球団のピッチャーがまるきし、打てない。苦手投手である。その頃、世界のホームラン王、第一回国民栄誉賞者でもある王貞治監督は、数週間付きっ切りでマンツーマン指導したそうである。そして、対戦日の当日、その投手に全くの凡打に終わり、最終打席の後、王監督は、ベンチから出てきて「あれほど教えたのに、練習したのに、どうして打てないんだ!」と怒鳴りつけられた時、初めて‘雲上人’でもある王監督にくってかっかたそうである。「あんただから、あのピッチャーが打てるんでしょうが!俺は監督ほど才能もないっすよ!」と反論したそうである。これは理想の高い東大卒の教育ママが、我が子を観る目線に似てもいる。
東大の難問は秀才でも難しいものである。長嶋茂雄にとっての村山実、王貞治にとっての江夏豊、野村克也にとっての稲尾和久のようなものである。
(つづく)
2021年5月10日 17:54