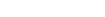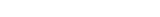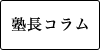カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年7月 (2)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
コラム
好きか嫌いかは、質か量かに依る
私は、子どもの頃、小学校低学年くらいまで、肉や魚(生魚・鮨)が食べられなかった、嫌いだったものです。その一方、父親は、食道楽、今でいうグルメ人間であった。私のその食の気質は、母親ゆずりのものであったように思う。母は、肉も生魚も食しない、好みは、今でいう準ベジタリアン的女性でもあり、焼き鮭でお茶漬け、釜飯、蕎麦など、洋風なものが好みではなく、和風、準懐石料理的な、むしろ精進料理派、それも庶民派のそれでもあった。両親は、食に関しては、好対照でもあり、浅草での外食に際しても、父は、すき焼きや鰻を、母は、蕎麦や釜飯を、別個に食する、<浅草という街全体>が、<露木家のフードコート>のようでもあった。しかし、天ぷらだけは、共通の一致を見る、浅草の天ぷらの名店では家族で食の好みが共通する場所でもあった。私は、小学校4年生くらいまでは、母的食の嗜好少年でもあった。それには、理由があった。
我が家は、祖父の代で、大正末期和菓子を始め、父の代で、昭和20年代にパン製造小売業、また洋菓子店と事業を拡大してもいった。そのため、私が、もの心が付く頃には、パンやケーキ職人が、工場上の寮で住み込み従業員として結構な数働いていた。そのため、その職人の若い衆のために、祖母が、大きな鍋などで、三度の食事(賄い食)を作ってもいた。その食事担当係が祖母で、近所の高度成長期の地元のパパママストアーで食材を調達してもいた。因に、母は、店の切り盛り、パートの女子従業員の指導担当など、一切食事の料理にはかかわらなかった。母の作る食事は、遠足や運動会など、私自身の学校行事の際のみであった。よって、幼児期から小学校までは、この祖母が職人さんたちに賄う食事を一緒にしていたことに、食の片寄りの原因があった。
祖母が、夕食に出す肉は、牛から豚にいたるまで安く量のある、質は二の次のものを選んでいたと思う。また、昼時の、刺身などマグロにしろ、記憶では、噛み終わると筋が口の中に残るような赤身を出していた。こうした、食環境が、どうも、肉や魚を美味しいと思わない遠因にもなり、結局は、私を肉と魚(生魚)嫌いにしていたように思われる。
そう、小学校4年くらいまでは、浅草で食事をしても、母の方についてゆく派(妹も)でもあり、行きつけの蕎麦屋は、<尾張屋>という、永井荷風もご愛用の名店と決まっていた。
父は父で、行きつけの地元江戸川区の寿司屋に住み込み職人を数名連れてゆく際も、私が、かんぴょう巻、かっぱ巻き、たまごと、生ものを注文しないので、連れ出すこともなくなっていた。
このような私の食好みを観てか、気づいてか、その食癖を改めようと考えたのか、ある日、小学校5年生くらいだったと記憶しているが、父が私を一人だけその鮨屋に連れ出した。確か、店内には、客は一人もいなかった。予約ではなく、偶然だったであろう。二人でカウンター席につくや、
「おやじ、いつもの頼むわ!」と馴染みの店主に声をかけた。
「だんな、わかりやした!」と応じると、向かい側の調理場端の大きな冷蔵庫から、あるものを取り出し、包丁で数枚切り取る、そして、手際よく、寿司を握り、私の前に出した。
「僕、食べてみな!」とかすかな笑みとともに、一言いった。
「お父さん、僕、生もの食べないって知ってるよね、どうして、こんなの握らせたの?」くちを尖がらせて、父に言い放った。
「いいから、食ってみな、食べなさい!」と強い語気でいってきた。顔は笑っていない。正面のおやじさんは、ニコニコして、僕を見つめている。二人に見つめられながら、恐る恐る、いや、しぶしぶその一貫を手でつまみ、生醤油をつけ、口にゆっくりと運んだ。温かいシャリと何かほどよい冷たさの身の感触が口蓋にふれるや、数回かみしめる。すると、その身が口の中で、数回噛むだけで、魚の身とは思われないくらいに、す~っと溶けていった。「あの、おばーちゃんが、夕餉時に出す、赤身のマグロとは違う!なんだ、このマグロは、……」「旨い!」いや、そういう感想は、店を出てから実感が湧いてきたと思う。それほど、本物の寿司、それも、大トロだったと思う、恐らく、一見さんには決して出さない、お得意さん限定の、“大間”級の高級ネタであったことは、確かである。そして、二貫目も口に運んだ。
「どうだ、旨いだろう?」と父親は、ぽつりと言った。父の、大の好物は、寿司のマグロと牛肉と鰻、そして天ぷらである。その父親の、伝家の宝刀、“大間の大トロ”に、マグロというものの旨みというものを思い知らされた。それを契機に、恐らく父は、エビも、最上級の、見たこともない大ぶりの車えびの寿司を私の前に出させた。こうして、生もの、寿司というもの苦手を克服した。いや、その後、能動的に、二流、三流の寿司でも食せるようになった。
次は、肉の第二ステージである。これも、小学校の6年くらいだったろうか、父親の食教育というものの一環、第二幕である。我が子が、将来、男子でありながら、寿司もダメ、牛肉もダメとなると、将来を慮ったのでもあろう。寿司がどうにか食べられるようになって間もない頃、秋だっただろうか、ケーキやパンのトレーや包装用紙など消耗品を合羽橋道具街への週一回の買い出しの帰途のことである。大橋巨泉が行きつけの、父もお馴染みの、浅草のステーキの名店<松喜>という松坂牛の専門店に連れてゆかれた。この時も、「僕は、肉なんて手べないよ、行くなら、尾張屋の蕎麦屋がいい!」と言い放った。しかし、父は、聞く耳を持たずに、私をそのビルの二階へと連れ込んだ。いや、その当時は、ビルではなかったかもしれない。
父子二人で、テーブルに向き合い、待っていると、鉄板の上でジュ~ジュ~と煙のなかで焼かれたばかりのステーキが出てきた。「これは、テンダーロインステーキと言って、旨いぞ!食ってみろ」その後知るのだが、松坂牛のヒレステーキであった。昭和40年代から50年代など、松坂牛など、知る人ぞ知るグルメ牛の象徴でもあった時代である。祖母が、工場の職人さんのために使用する、スーパーの牛肉とは、わけが違う。地方のさびれた遊園地しか知らない子どもが、ディズニーランドに連れて行かれたような経験でもあっただろうか。
「あの、おばーちゃんが、夕食で職人さんに出す、あの肉と違う!」肉厚なのに、軽くかむだけで、牛肉独特の風味という、豚と鶏とは全く違う感動が、12才の心を包んだ。それまで、憎んでいた人、嫌だと思っていた人、そうした、人間が、話してみて、初めていい人、素晴らしい人であった、そうした人生論的感激ともいおうか、考えの、趣向の、コペルニクス的大変換というものを味わった一瞬でもあった。それ以後、その<松喜>に数回、また、すき焼きで名高い<ちんや>にも父子二人で、通った。私の食の成長の第二ステージが終了した。
父親の、食のエリート教育である。これは、食の片寄り、食の好き嫌い、それを克服するには、まず、その子に、最高の食材・料理を与えることであるといえる教訓である。
昔、料理の周富徳や周富輝だったと思う、ピーマンやニンジンが大嫌いな子どもを、その家庭に赴き、中華の超一品料理を、その嫌悪の食材で作り、その子どもに食させる。当然、その子どもは、その嫌いな食材の旨みに気づく、そして、野菜嫌いを克服させる、そうした企画番組があった。これなど、普通の子どもの嫌いな野菜を、超一流のシェフに作らせ、食べさせると、その嫌悪の対象が克服されるという見本の一例でもあろう。
私もそうだったのだが、子どもから少年にかけてトマト嫌いが意外と多い。これも、その初体験のトマトの食材が原因なことが大半でもあろう。一個数百円以上もする高級トマトを、適度に冷やし、スライスして、その子に出せば、だいたいは、そのトマトの旨さに気づき、トマト嫌いがなくなる可能性が大とも思われる。
我が子に、無責任に、それも闇雲に大量ドリル・問題集、集団塾、いや、個別塾にしろ大学生レベルの講師をあてがう、これがもとで、量の勉強の被害、そして嫌い、苦手へと誘導されるのではないかと思う。ただでさえ、日本の小中学校は、質より量の授業である。嫌いになるのも無理はない。
ここにおいても、質から入るというのが、学びのプロセスの要諦である。
量から入るから、<食>のみならず、<学>においても、苦手、嫌いという心的現象が起こるものである。次回は、この軸足を、学びにおける、量と質に絞り語ってみたいと思う。(つづく)
我が家は、祖父の代で、大正末期和菓子を始め、父の代で、昭和20年代にパン製造小売業、また洋菓子店と事業を拡大してもいった。そのため、私が、もの心が付く頃には、パンやケーキ職人が、工場上の寮で住み込み従業員として結構な数働いていた。そのため、その職人の若い衆のために、祖母が、大きな鍋などで、三度の食事(賄い食)を作ってもいた。その食事担当係が祖母で、近所の高度成長期の地元のパパママストアーで食材を調達してもいた。因に、母は、店の切り盛り、パートの女子従業員の指導担当など、一切食事の料理にはかかわらなかった。母の作る食事は、遠足や運動会など、私自身の学校行事の際のみであった。よって、幼児期から小学校までは、この祖母が職人さんたちに賄う食事を一緒にしていたことに、食の片寄りの原因があった。
祖母が、夕食に出す肉は、牛から豚にいたるまで安く量のある、質は二の次のものを選んでいたと思う。また、昼時の、刺身などマグロにしろ、記憶では、噛み終わると筋が口の中に残るような赤身を出していた。こうした、食環境が、どうも、肉や魚を美味しいと思わない遠因にもなり、結局は、私を肉と魚(生魚)嫌いにしていたように思われる。
そう、小学校4年くらいまでは、浅草で食事をしても、母の方についてゆく派(妹も)でもあり、行きつけの蕎麦屋は、<尾張屋>という、永井荷風もご愛用の名店と決まっていた。
父は父で、行きつけの地元江戸川区の寿司屋に住み込み職人を数名連れてゆく際も、私が、かんぴょう巻、かっぱ巻き、たまごと、生ものを注文しないので、連れ出すこともなくなっていた。
このような私の食好みを観てか、気づいてか、その食癖を改めようと考えたのか、ある日、小学校5年生くらいだったと記憶しているが、父が私を一人だけその鮨屋に連れ出した。確か、店内には、客は一人もいなかった。予約ではなく、偶然だったであろう。二人でカウンター席につくや、
「おやじ、いつもの頼むわ!」と馴染みの店主に声をかけた。
「だんな、わかりやした!」と応じると、向かい側の調理場端の大きな冷蔵庫から、あるものを取り出し、包丁で数枚切り取る、そして、手際よく、寿司を握り、私の前に出した。
「僕、食べてみな!」とかすかな笑みとともに、一言いった。
「お父さん、僕、生もの食べないって知ってるよね、どうして、こんなの握らせたの?」くちを尖がらせて、父に言い放った。
「いいから、食ってみな、食べなさい!」と強い語気でいってきた。顔は笑っていない。正面のおやじさんは、ニコニコして、僕を見つめている。二人に見つめられながら、恐る恐る、いや、しぶしぶその一貫を手でつまみ、生醤油をつけ、口にゆっくりと運んだ。温かいシャリと何かほどよい冷たさの身の感触が口蓋にふれるや、数回かみしめる。すると、その身が口の中で、数回噛むだけで、魚の身とは思われないくらいに、す~っと溶けていった。「あの、おばーちゃんが、夕餉時に出す、赤身のマグロとは違う!なんだ、このマグロは、……」「旨い!」いや、そういう感想は、店を出てから実感が湧いてきたと思う。それほど、本物の寿司、それも、大トロだったと思う、恐らく、一見さんには決して出さない、お得意さん限定の、“大間”級の高級ネタであったことは、確かである。そして、二貫目も口に運んだ。
「どうだ、旨いだろう?」と父親は、ぽつりと言った。父の、大の好物は、寿司のマグロと牛肉と鰻、そして天ぷらである。その父親の、伝家の宝刀、“大間の大トロ”に、マグロというものの旨みというものを思い知らされた。それを契機に、恐らく父は、エビも、最上級の、見たこともない大ぶりの車えびの寿司を私の前に出させた。こうして、生もの、寿司というもの苦手を克服した。いや、その後、能動的に、二流、三流の寿司でも食せるようになった。
次は、肉の第二ステージである。これも、小学校の6年くらいだったろうか、父親の食教育というものの一環、第二幕である。我が子が、将来、男子でありながら、寿司もダメ、牛肉もダメとなると、将来を慮ったのでもあろう。寿司がどうにか食べられるようになって間もない頃、秋だっただろうか、ケーキやパンのトレーや包装用紙など消耗品を合羽橋道具街への週一回の買い出しの帰途のことである。大橋巨泉が行きつけの、父もお馴染みの、浅草のステーキの名店<松喜>という松坂牛の専門店に連れてゆかれた。この時も、「僕は、肉なんて手べないよ、行くなら、尾張屋の蕎麦屋がいい!」と言い放った。しかし、父は、聞く耳を持たずに、私をそのビルの二階へと連れ込んだ。いや、その当時は、ビルではなかったかもしれない。
父子二人で、テーブルに向き合い、待っていると、鉄板の上でジュ~ジュ~と煙のなかで焼かれたばかりのステーキが出てきた。「これは、テンダーロインステーキと言って、旨いぞ!食ってみろ」その後知るのだが、松坂牛のヒレステーキであった。昭和40年代から50年代など、松坂牛など、知る人ぞ知るグルメ牛の象徴でもあった時代である。祖母が、工場の職人さんのために使用する、スーパーの牛肉とは、わけが違う。地方のさびれた遊園地しか知らない子どもが、ディズニーランドに連れて行かれたような経験でもあっただろうか。
「あの、おばーちゃんが、夕食で職人さんに出す、あの肉と違う!」肉厚なのに、軽くかむだけで、牛肉独特の風味という、豚と鶏とは全く違う感動が、12才の心を包んだ。それまで、憎んでいた人、嫌だと思っていた人、そうした、人間が、話してみて、初めていい人、素晴らしい人であった、そうした人生論的感激ともいおうか、考えの、趣向の、コペルニクス的大変換というものを味わった一瞬でもあった。それ以後、その<松喜>に数回、また、すき焼きで名高い<ちんや>にも父子二人で、通った。私の食の成長の第二ステージが終了した。
父親の、食のエリート教育である。これは、食の片寄り、食の好き嫌い、それを克服するには、まず、その子に、最高の食材・料理を与えることであるといえる教訓である。
昔、料理の周富徳や周富輝だったと思う、ピーマンやニンジンが大嫌いな子どもを、その家庭に赴き、中華の超一品料理を、その嫌悪の食材で作り、その子どもに食させる。当然、その子どもは、その嫌いな食材の旨みに気づく、そして、野菜嫌いを克服させる、そうした企画番組があった。これなど、普通の子どもの嫌いな野菜を、超一流のシェフに作らせ、食べさせると、その嫌悪の対象が克服されるという見本の一例でもあろう。
私もそうだったのだが、子どもから少年にかけてトマト嫌いが意外と多い。これも、その初体験のトマトの食材が原因なことが大半でもあろう。一個数百円以上もする高級トマトを、適度に冷やし、スライスして、その子に出せば、だいたいは、そのトマトの旨さに気づき、トマト嫌いがなくなる可能性が大とも思われる。
我が子に、無責任に、それも闇雲に大量ドリル・問題集、集団塾、いや、個別塾にしろ大学生レベルの講師をあてがう、これがもとで、量の勉強の被害、そして嫌い、苦手へと誘導されるのではないかと思う。ただでさえ、日本の小中学校は、質より量の授業である。嫌いになるのも無理はない。
ここにおいても、質から入るというのが、学びのプロセスの要諦である。
量から入るから、<食>のみならず、<学>においても、苦手、嫌いという心的現象が起こるものである。次回は、この軸足を、学びにおける、量と質に絞り語ってみたいと思う。(つづく)
2024年4月22日 18:04