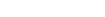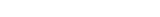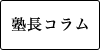カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (3)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > ①自然・アナログ・デジタル~デジタルに非ずんば人に非ずの世~~
コラム
①自然・アナログ・デジタル~デジタルに非ずんば人に非ずの世~~
昭和の時代、ウォークマンを一つ、ラジカセでも一台買えば、故障するまで使う、使い切るのが習わしであった。理由は、そんな機種や器具など、数年、いや十年くらい機能は進化しなかったからだ。それに、健全に機能していれば、買い替えなどといった意識さえ頭に浮かんでもこなかった。ものを大切に使うという、道徳的社会通念がまだ残存してもいた時代であった。ファーストファッションという言葉すらないことがそれを裏付けてもいよう。2000年前後だろうか、ユニクロが数千円のフリースを販売して、「洗濯屋に出すくらいなら、買い替えた方がましだ!」的経済観念が、消費者に芽生えた時代が懐かしい。
平成の後半だろうか状況が激変した。携帯電話、そしてスマホの機能といたものが長足の進歩を遂げ、目を見張るスピードで、機能性の重視、スペック至上主義だろうか、機能の向上、使い勝手さのよさなど、まだ十分使えれる段階でも、iPhone10をiPhone11に機種変更する若者が多数出現する。近年では、買い替え疲れとやらで、そうした消費者行動は減ってはきているとも聞く。電池の劣化や起動ののろさなどで不満が溜まり買い替えをする者は、依然として多いと聞く。
こうした、社会の変化をドッグイヤーとも言い、平成半ば頃から耳にするようになってきた。
人類発祥(ホモサピエンス誕生)の頃、火を使い始めた数十万年前から1945年までの人間社会の文明の進歩の度合いは、1945から2025年までのそれに匹敵するとも言われることが、上記のことの証左ともなっていよう。AI社会の到来は、それにますます拍車をかけ、加速度的になってもいる。実業家孫正義の「AIは、知のゴールドラッシュである」という言葉ではないが、とてつもない未来が人類を待ち構えてもいよう。
昭和の頃は、デジタルという言葉の具体的意味、また、コンピュータというものの深い存在意義など表面的にしか、一般庶民には認識はいなかった時代である。音楽業界でも、CD以前のレコードやカセットテープの時代だ。デジタルは異端児(未来のツール)、マイナー、“日陰者”、60年代から70年代にかけて、エレキギターが不良の象徴ともみなされていた時代とかぶる。そう、アコースティックギターが主役の中で、戦後、エレキギターが登場した、それが、“楽器のデジタルの象徴”の登場といってもいい。
平成の時代に入るや、このデジタルという用語が、ようやく市民権を得て、アナログとデジタルという、男女同権のごときに、勢いづき、変わってもゆく。このデジタルという言葉で、それまでは、自分たちの世界は、アナログの時代だったことを我々は痛感させらもした。丁度、外国人目線で、その翻訳語で、江戸時代は“鎖国”だったのかと日本人は覚醒した経験とも似ている、また、明治初期、自由という概念に目覚め、それまでの封建的慣習・習慣のなかで暮らしていたのだと悟ってもゆく日本人にも類するだろう。
令和に入るや、もう、アナログという概念は、巷に、皆目見当たらなくなったガラケーやワープロの存在ように、忘れ去られた感が強い。だから、スマホの操作の仕方のマニュアル本がバカ売れし、スマホの操作の特集を組んで、50代以上の女性をターゲットとした雑誌『ハルメク』の異常な部数の右肩上がり現象が、そうしたデジタル主役の生活を余儀なくされる時代を象徴している。企業内のDXだけではない、個人の生活内も、DXを余儀なくされている現実の証左である。出版界も、デジタル化をマーケティングしなければ、部数はもちろん、その会社も生き残ってはいけないあらわれでもある。余談ではあるが、私は、今でもガラケーならぬガラホ{※巷のご老人方は、このガラホの存在を全く知らない。4Gであと10年は使える事実を知らない!}の使用者である。当然、iPhoneやアイパットを所有してはいるが、ほとんど使用していない。必要な時に、最低限に抑えている、極力使用しない。故に、“アマゾン”などとは一切無縁の生活を送っている。デジタルに染まってはいない、これを“DXしていない!”と曲解してもっては困る。また、弊塾の教材づくりは、パソコンならぬワープを使用している。ワープロ派でもある。余計なことだが、知の巨人片山杜秀氏もワープロ派である。
もはや、令和は、「平家に非ずんば人に非ず」ではないが、「デジタルに非ずんば情報弱者、買い物弱者、つまり、生活不便者なり」そういったことを声高に叫ばれる時代に突入した。
昭和の頃、「勉強ばかりしないで、外で遊びなさい」「テレビばかり観ていないで本を読みなさい」「マンガばかり読んでいないで勉強をしなさい」、こういった言葉が、家庭内で飛び交ってもいた。こうした、子供たち、少年たちの生活の範疇は、ほとんど非デジタルの領域ともいえる行為・行動であった。つまり、アナログの生活規範で、遊びと学びとが円環状にうごめいてもいた。従って、そのアナログから息抜きする、リフレッシュする存在として、自然があった。アナログ生活の輪廻からの解脱、それが、身体を動かす“自然体験”でもあったということだ。「良く学び、よく遊べ!」この言葉の要は、アナログの輪廻から自然への解脱という含意もあったはずなのである。空き地での草野球や缶蹴りなど、また、スポーツや登山、キャンプ、山や海の中でのレジャーであった。そうである。昭和は、アナログの対立事項として自然があったのだ。任天堂やソニーのゲーム機など存在しなかった、ましてや、現今のeスポーツなど、その当時の誰が予想したであろうか?今でも、eスポーツなど、オリンピックの種目に加えるなどは言語道断だと言い張る者が多いのも、その文脈においてなのである。
これが、平成になるや、アナログの領域がどんどんデジタルに寝食されてもいった。現代の街の書店数の激減、新聞購読数の右肩下がり現象、それが具体的な現象ともいえることである。小中高の若者も、勉強の手段が、紙の教科書からアイパットへ、従来の黒板も電子黒板へ、そうした勉強にしろ、娯楽(息抜き・楽しみ)にしろ、ほぼデジタルに置き換えられてしまった。学びとしては、電子ツールで勉強し、遊び、娯楽としても、電子ツールでゲームをする、日常生活の中で、アナログというツールの介入してくる余地がほとんどなくなってしまった。近年、プロゴルフ界も、T・ウッズが中心になり、デジタル空間内のトーナメント(バーチャルゴルフリーグ TGL)まで出現した。人生ゲームなどのボードゲームは、今や絶滅危惧種である。レコードと同じ存在である。ましてや、タワマンや高層マンションはもちろん、一戸建てにしろ、アマゾンやウーバーなどで日常生活を送る家庭が大半をしめ、衣食住のインフラが、デジタルという軍門に下った感がある。<天下布武>ならぬ、<天下布“電”>である。デジタルがアナログを放逐した。まるで、明治の北海道開拓使で、本州から送り込まれた元武士が、アイヌの人(アナログ族)を絶滅の際まで追い込んだとの同じ事態が、このデジタル化社会とかぶって見えてくる。
昭和の時代、アナログに支配されていていた。学校から会社にいたるまでの生活の規範は、その息抜きとしては、自然体験というもので、本来の人間性を回復するものであった、生物として、肉体として、リフレッシュやストレス解消をしていた。精神の<生物としての健全化>である。レクレーションとかレジャーとも称されて領域である。一戸建てやマンション内で飼っているトイプードルを、近くの公園などに散歩に連れ出すようなものである。近年、小型犬の多くは、屋外に一切出さないご家庭が多いとも聞く。これは、ある意味、ペットのデジタル化ともいっていい行為である。
平成の時代になると、社会の規範ともいえる“憲法”が、アナログからデジタルへと大きく変化した、その度合いは、日本社会における戦前と戦後、それと同じくらいの激変を遂げたといいえる変革である。書籍・新聞・ワープロなどの存在がまさしくそれを表徴してもいよう。学びから仕事に至るまで、デジタル王国の軍門に下る、しかも、遊びからレジャーにいたるまでもがデジタル王国の支配をうける。昭和の頃の、子供たちの、野山を走り回ったり、空き地で野球をしたり、街中を流れる川でザリガニ取り、魚釣りなど消滅してしまった。自然という存在は、家族で、年一、二回旅行をするだけという意識の閾ないに囲い込まれた。、自然という精神の回復をするトポスが街の書店のように姿を消した。昭和に流行った“東京砂漠”や“都会のジャングル”という言葉が、今やレトロ調に懐かしく思い出されてもくる。
令和はどうであろう。自然はもちろん、アナログも日常の空間から、視界には入らず、脳裏にも浮かばない、小中高生の生活というものは、身体を通した生の体験ということが、絶滅危惧種、いや、消滅してしまったとも言える。これは、昭和っ子と令和っ子の体力測定の数値が前者が勝る、視力も前者が勝る。昭和は眼鏡っ子など珍しかった。だから、ドラえもんののび太のように、いじめられっ子は大方、マンガなどでは眼鏡をかけてもいた。こうした肉体的特徴も、非自然派の、インドア―派で、テレビゲームに興じる日常が最大の原因でもあろう。デジタル社会の負の側面である。
昭和は、アナログの世界を自然が包み覆ってもいた。アナログが“オゾン層”の役割でもあっただろう。平成後期は、アナログとデジタルの共存の前期を経て、前者を放逐したデジタル王国の時代ともなった。その過程で、自然という“オゾン層”は、破壊され、もろくもなり、その意義は、ますます、軽視されようとしている。令和は、デジタルオンリーのデジタル帝国の時代に突入した。この超長足の進歩を遂げる社会にあっては、人間性の、その精神の復元ともなる、アナログや自然という範疇が、若干ではあるが、顧みられる傾向がうかがわれるが、やはり、デジタル化が、DXという用語に、国是ならぬ、時代是のように象徴されてもいよう。学習から仕事に至るまで、時勢の必然とも思えてもくる。アナログは、今や、習近平中国社会における、自由・民権という概念、そして行動ともかぶってくる。
自然(生物としての人間の認識)、アナログ(文化)、デジタル(文明)、こうした範疇の概念を、デジタルネイチャーという狡猾な言葉を通して、人類進歩容認派の、落合陽一が、唱道している様は、大阪万博の落合陽一のパビリオンを見ると、そうなのかと理解はできるが、生理的、心理的に容認できない自分がいる。次回、このデジタル帝国の到来というものが、どういうものか、その言説の領域を広めてもいきたいと思う。(つづく)
平成の後半だろうか状況が激変した。携帯電話、そしてスマホの機能といたものが長足の進歩を遂げ、目を見張るスピードで、機能性の重視、スペック至上主義だろうか、機能の向上、使い勝手さのよさなど、まだ十分使えれる段階でも、iPhone10をiPhone11に機種変更する若者が多数出現する。近年では、買い替え疲れとやらで、そうした消費者行動は減ってはきているとも聞く。電池の劣化や起動ののろさなどで不満が溜まり買い替えをする者は、依然として多いと聞く。
こうした、社会の変化をドッグイヤーとも言い、平成半ば頃から耳にするようになってきた。
人類発祥(ホモサピエンス誕生)の頃、火を使い始めた数十万年前から1945年までの人間社会の文明の進歩の度合いは、1945から2025年までのそれに匹敵するとも言われることが、上記のことの証左ともなっていよう。AI社会の到来は、それにますます拍車をかけ、加速度的になってもいる。実業家孫正義の「AIは、知のゴールドラッシュである」という言葉ではないが、とてつもない未来が人類を待ち構えてもいよう。
昭和の頃は、デジタルという言葉の具体的意味、また、コンピュータというものの深い存在意義など表面的にしか、一般庶民には認識はいなかった時代である。音楽業界でも、CD以前のレコードやカセットテープの時代だ。デジタルは異端児(未来のツール)、マイナー、“日陰者”、60年代から70年代にかけて、エレキギターが不良の象徴ともみなされていた時代とかぶる。そう、アコースティックギターが主役の中で、戦後、エレキギターが登場した、それが、“楽器のデジタルの象徴”の登場といってもいい。
平成の時代に入るや、このデジタルという用語が、ようやく市民権を得て、アナログとデジタルという、男女同権のごときに、勢いづき、変わってもゆく。このデジタルという言葉で、それまでは、自分たちの世界は、アナログの時代だったことを我々は痛感させらもした。丁度、外国人目線で、その翻訳語で、江戸時代は“鎖国”だったのかと日本人は覚醒した経験とも似ている、また、明治初期、自由という概念に目覚め、それまでの封建的慣習・習慣のなかで暮らしていたのだと悟ってもゆく日本人にも類するだろう。
令和に入るや、もう、アナログという概念は、巷に、皆目見当たらなくなったガラケーやワープロの存在ように、忘れ去られた感が強い。だから、スマホの操作の仕方のマニュアル本がバカ売れし、スマホの操作の特集を組んで、50代以上の女性をターゲットとした雑誌『ハルメク』の異常な部数の右肩上がり現象が、そうしたデジタル主役の生活を余儀なくされる時代を象徴している。企業内のDXだけではない、個人の生活内も、DXを余儀なくされている現実の証左である。出版界も、デジタル化をマーケティングしなければ、部数はもちろん、その会社も生き残ってはいけないあらわれでもある。余談ではあるが、私は、今でもガラケーならぬガラホ{※巷のご老人方は、このガラホの存在を全く知らない。4Gであと10年は使える事実を知らない!}の使用者である。当然、iPhoneやアイパットを所有してはいるが、ほとんど使用していない。必要な時に、最低限に抑えている、極力使用しない。故に、“アマゾン”などとは一切無縁の生活を送っている。デジタルに染まってはいない、これを“DXしていない!”と曲解してもっては困る。また、弊塾の教材づくりは、パソコンならぬワープを使用している。ワープロ派でもある。余計なことだが、知の巨人片山杜秀氏もワープロ派である。
もはや、令和は、「平家に非ずんば人に非ず」ではないが、「デジタルに非ずんば情報弱者、買い物弱者、つまり、生活不便者なり」そういったことを声高に叫ばれる時代に突入した。
昭和の頃、「勉強ばかりしないで、外で遊びなさい」「テレビばかり観ていないで本を読みなさい」「マンガばかり読んでいないで勉強をしなさい」、こういった言葉が、家庭内で飛び交ってもいた。こうした、子供たち、少年たちの生活の範疇は、ほとんど非デジタルの領域ともいえる行為・行動であった。つまり、アナログの生活規範で、遊びと学びとが円環状にうごめいてもいた。従って、そのアナログから息抜きする、リフレッシュする存在として、自然があった。アナログ生活の輪廻からの解脱、それが、身体を動かす“自然体験”でもあったということだ。「良く学び、よく遊べ!」この言葉の要は、アナログの輪廻から自然への解脱という含意もあったはずなのである。空き地での草野球や缶蹴りなど、また、スポーツや登山、キャンプ、山や海の中でのレジャーであった。そうである。昭和は、アナログの対立事項として自然があったのだ。任天堂やソニーのゲーム機など存在しなかった、ましてや、現今のeスポーツなど、その当時の誰が予想したであろうか?今でも、eスポーツなど、オリンピックの種目に加えるなどは言語道断だと言い張る者が多いのも、その文脈においてなのである。
これが、平成になるや、アナログの領域がどんどんデジタルに寝食されてもいった。現代の街の書店数の激減、新聞購読数の右肩下がり現象、それが具体的な現象ともいえることである。小中高の若者も、勉強の手段が、紙の教科書からアイパットへ、従来の黒板も電子黒板へ、そうした勉強にしろ、娯楽(息抜き・楽しみ)にしろ、ほぼデジタルに置き換えられてしまった。学びとしては、電子ツールで勉強し、遊び、娯楽としても、電子ツールでゲームをする、日常生活の中で、アナログというツールの介入してくる余地がほとんどなくなってしまった。近年、プロゴルフ界も、T・ウッズが中心になり、デジタル空間内のトーナメント(バーチャルゴルフリーグ TGL)まで出現した。人生ゲームなどのボードゲームは、今や絶滅危惧種である。レコードと同じ存在である。ましてや、タワマンや高層マンションはもちろん、一戸建てにしろ、アマゾンやウーバーなどで日常生活を送る家庭が大半をしめ、衣食住のインフラが、デジタルという軍門に下った感がある。<天下布武>ならぬ、<天下布“電”>である。デジタルがアナログを放逐した。まるで、明治の北海道開拓使で、本州から送り込まれた元武士が、アイヌの人(アナログ族)を絶滅の際まで追い込んだとの同じ事態が、このデジタル化社会とかぶって見えてくる。
昭和の時代、アナログに支配されていていた。学校から会社にいたるまでの生活の規範は、その息抜きとしては、自然体験というもので、本来の人間性を回復するものであった、生物として、肉体として、リフレッシュやストレス解消をしていた。精神の<生物としての健全化>である。レクレーションとかレジャーとも称されて領域である。一戸建てやマンション内で飼っているトイプードルを、近くの公園などに散歩に連れ出すようなものである。近年、小型犬の多くは、屋外に一切出さないご家庭が多いとも聞く。これは、ある意味、ペットのデジタル化ともいっていい行為である。
平成の時代になると、社会の規範ともいえる“憲法”が、アナログからデジタルへと大きく変化した、その度合いは、日本社会における戦前と戦後、それと同じくらいの激変を遂げたといいえる変革である。書籍・新聞・ワープロなどの存在がまさしくそれを表徴してもいよう。学びから仕事に至るまで、デジタル王国の軍門に下る、しかも、遊びからレジャーにいたるまでもがデジタル王国の支配をうける。昭和の頃の、子供たちの、野山を走り回ったり、空き地で野球をしたり、街中を流れる川でザリガニ取り、魚釣りなど消滅してしまった。自然という存在は、家族で、年一、二回旅行をするだけという意識の閾ないに囲い込まれた。、自然という精神の回復をするトポスが街の書店のように姿を消した。昭和に流行った“東京砂漠”や“都会のジャングル”という言葉が、今やレトロ調に懐かしく思い出されてもくる。
令和はどうであろう。自然はもちろん、アナログも日常の空間から、視界には入らず、脳裏にも浮かばない、小中高生の生活というものは、身体を通した生の体験ということが、絶滅危惧種、いや、消滅してしまったとも言える。これは、昭和っ子と令和っ子の体力測定の数値が前者が勝る、視力も前者が勝る。昭和は眼鏡っ子など珍しかった。だから、ドラえもんののび太のように、いじめられっ子は大方、マンガなどでは眼鏡をかけてもいた。こうした肉体的特徴も、非自然派の、インドア―派で、テレビゲームに興じる日常が最大の原因でもあろう。デジタル社会の負の側面である。
昭和は、アナログの世界を自然が包み覆ってもいた。アナログが“オゾン層”の役割でもあっただろう。平成後期は、アナログとデジタルの共存の前期を経て、前者を放逐したデジタル王国の時代ともなった。その過程で、自然という“オゾン層”は、破壊され、もろくもなり、その意義は、ますます、軽視されようとしている。令和は、デジタルオンリーのデジタル帝国の時代に突入した。この超長足の進歩を遂げる社会にあっては、人間性の、その精神の復元ともなる、アナログや自然という範疇が、若干ではあるが、顧みられる傾向がうかがわれるが、やはり、デジタル化が、DXという用語に、国是ならぬ、時代是のように象徴されてもいよう。学習から仕事に至るまで、時勢の必然とも思えてもくる。アナログは、今や、習近平中国社会における、自由・民権という概念、そして行動ともかぶってくる。
自然(生物としての人間の認識)、アナログ(文化)、デジタル(文明)、こうした範疇の概念を、デジタルネイチャーという狡猾な言葉を通して、人類進歩容認派の、落合陽一が、唱道している様は、大阪万博の落合陽一のパビリオンを見ると、そうなのかと理解はできるが、生理的、心理的に容認できない自分がいる。次回、このデジタル帝国の到来というものが、どういうものか、その言説の領域を広めてもいきたいと思う。(つづく)
2025年7月14日 16:59