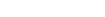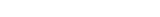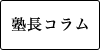カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > 就社から'就職'へ、学歴社会から学力社会へ
コラム
就社から'就職'へ、学歴社会から学力社会へ
終身雇用と年功序列社会が、だいたい終焉を迎えた今日、大卒の社会人が、3年で会社を辞める日本社会で、就職ということばが、内実、就社であった現実があらわとなりつつあります。しかし、現実には、1~2割程度の優秀、ある意味、地頭のいい、また、IQの高い学生が吐く言葉は、凡庸なる8割の学生には、「これからは就社ではなく、真の就職の時代だ!」が嫌味に響く今日この頃でもあります。一部の優秀な学生のみが、生き残れる実力社会、AI社会が、弱者である学生に「俺はそんなに優秀じゃねぇし…、何の取り柄もねぇし…」と呟かし、逆に、保身、自己防衛、つまり、形だけでも一流大学に入り、有名大企業に入って、30代、40代、50代でも、鎧ともなりえる一流(大)学歴・有名企業というブランド・スーツで、受け身に入る。‘石にかじりついても辞めるもんか魂’を持ち続ける、こうした学生の二極化現象も顕著になっています。
以上から、時代の潮目で、表面上の就職から、その幻想が弾け、実態としての真の意味での就職という通念が、ぬっくりと顔をもたげてきたのです。就職と就社とを完全に大学生に自覚を促す転機となったのが、今般の経団連主導の就活ルールの撤廃とやらです。アメリカは、企業の補充(人員)採用{※欠けた社員を補う程度で、即戦力を求められる}であるのに対し、日本は(大量)一括採用です。日本も、その潮の流れの変わり目に来てもいるのでしょう。超一流企業、一部上場大手企業には、また、東大、一橋、早慶くらいの文科省認定のスーパー・グローバル大学は、涼しい顔をしています。一方、標準国公立大学やMARCH以下の大学や、中小企業などは、危機感を募らせ、「就職問題懇談会」の座長を務める埼玉大学の山口宏樹学長などは、この就活ルールに危惧してもいます。正直、猛反発しているのです。理由はこうです。「学生の本分である学業が妨げられるおそれがある」と。これは、建前ですし、一部、本音でもあります。大学の授業と企業の面接がバッティングしたら、その学生は、企業に対して「本業の授業があります、その日は無理です。別の日にして下さい」と相手に、きっぱり異議を申しでる勇気がある学生か否かが左右してきます。“企業にしっぽを振ってお願いします的”根性ならば、その学生の資質や気質を、相手方も見抜くことでしょう。
また、正直申し上げると、公立にしても、私立にしても、面倒見がいい大学、就職課が“しっかり面倒、お世話して”くれている大学などは、猛反発している構図{※就職課が学生にアドヴァイスや戦略を与えにくくなるからでもある}からも、グローバル化の波が就活にも押し寄せてきた観が否めません。就活における弱肉強食時代の到来です。
大学も、“グローバル~”“メディア~”“総合~”“国際~”“情報~”“環境~”と当世うけする、一種、大学にもキラキラネームがあり、そうした一見時代に合わせたネーミングの大学に限り、その名が、客寄せパンダ効果の化けの皮が剥がれることを懸念もしているのが想像できます。内実の伴わない大学、そして学生が、グローバル化に不適応となりかけてもくるのでしょう。このグローバル基準の就職活動の流れに、60年以上も日本で続いてきた就活ルールが撤廃へ追いやられつつあるのです。
そもそも、キラキラネームの学部を志望する高校生は、意地悪な見方、いや、穿った見方、本音で、現場感覚から言わせてもらえば、「文学部?私、本読まないし、作家なんかほとんど知らいない、嫌だわ!」「経済学か、経済なんてやっても、そんなの学んでも、社会じゃ使いものにならないと聞いているし…。」「法学部?大学で法学学んだって、弁護士になんか絶対になれないし、行ってもしょうがないし…。」このような従来の名称を冠したアカデミックな学部への回避・消去法で、一種、リベラル・アーツ観皆無の学生を、一見「役に立つことを本学部では教えますよ」と謳うネーミングで、集客する大学が、実は、このグローバル化の波により、絶滅危惧種ともなりかけているのです。看板がはずれかけているのです。そうです、こうした大学は、ある見方をすると、大学の仮面をかぶった‘専門学校’と同じ機関であるのです。そして、その馬脚を現しかねない状況に立たされてもいるのです。その焦りが、就活ルール廃止反対姿勢にも表れているわけです。こうしたキラキラネームの大学は、欧米の基準から言えば、大学足りえていない。また、こうした大学に奨学金を借りてまで入り、卒業すると、ローンの返済で、20代後半で自己破産という憂き目にもあってしまうのです。
ですから、(大)学歴社会と従来言われてきましたが、就社から就職へ実体が変質してきているように、(大)学歴社会から学力社会へパワーシフトしてきてもいるのです。その証左が、一部の大学や知識人が指摘しているように、リベラル・アーツの再評価です。その流れで、実社会で使える日本史や世界史、また、世界の趨勢を深く読み解く宗教学、また、地政学{※最近では、中国の覇権政策から‘地経学’なるジャンルも生まれてきています}などなどです。ですから、今も、池上彰氏、半藤一利氏、出口治明氏、佐藤優氏などの新書がバカ売れしているし、少々地味でもありますが、内田樹氏や松岡正剛氏などの本も売れているのです。大学生協では、『思考の整理学』(ちくま文庫)の外山滋比古氏の書籍や京大でユニークな講座を担当されている滝本哲史氏の本などが売れているのです。キラキラネーム学部の学生には、池上彰氏以外は、疎遠な知識人たちだと思われます。表面上は、非実利的、とっつきにくいほど知的に映るからでもあるからでしょう。高校時代に、知的基盤(アカデミックへ通じる知的インフラのようなもの)が、中等教育で種付けされてもいなかったからでしょう。大学は、以上の知識人のパラダイム(物事を考えるスタイル<型>のようのもの)を独自に習得する場所でもあるのです。大学とは、本来そういう場所であったはずです。その鍛錬の場が大学という機関であることは、洋の東西を問わず自明の理であります。日本の大学が、大宅壮一の言葉からも、‘駅弁大学’から、今では、‘名ばかり大学(≒専門学校){就職予備校}’にまで墜してもいます。まるで、幕末の日本中の佐幕派の小藩(10万石以下の藩)の如き存在でもあるのです。そうした機能不全に陥っている高等教育の半数近くの大学が、財界からの圧力も受け、本来なら、大学自身で行わなければならない、また、大学で行うのが本来適してもいる、使える英語(実用英語)教育、アクティブ・ラーニング(プレゼンと前提とした真のディベート)、そして、プログラミング教育(C言語の習得)、こうしたジャンルを、高大接続教育という美辞麗句のもとに、中等教育に放り投げ、責任転嫁してきたのです。
そうです、考えてみれば明らかな事ですが、高校生の段階で、使える英語を、アクティブ・ラーニングを、そしてプログラミングを、すでに身につけていたとしたら、大学当局は一体何を教えたらいいのでしょうか?つまり、大学現場が、こうしたジャンルの、もう教えられない教育機関になっていることの証明なのです。小学校からの英語の必須化も同様です。特に、公立中学の英語の授業が機能不全、身に付かない英語教育現場に墜しているために、「だったら、手っ取り早く、小学校から英語を教えちゃえ!」と、先も読めず、短慮な判断で文科省が決定してしまったのがことの本質でしょう。育ちの悪い苗を、新緑の春からではなく、草木もやっと芽吹く晩冬から植えてしまえば、冷夏や天候不順な季節でも、見事に十分実りをつけてくれるであろうと考える、浅はかな素人農家さえしない愚挙を文科省を始めようとしているのです。
新自由主義、グローバル化、少子高齢化、AI化、こうした時代の波に押し寄せられている日本は、第二の明治維新ともいえ、知識に依る実学ではなく、勿論、これも必須アイテムですが、その必要条件だけではだめで、知性に裏打ちされた教養(リベラル・アーツ)こそ高校から大学にかけて自身の知の幹として育て上げていかねばならないのです。それが身に付いて、大学生として、十分条件たりえる人物となりえるのです。
以上、就活問題と、学生の現代気質、また、昨今の大学の変質の関係を申し上げたまでです。英精塾の生徒は、勿論、一般の高校生にも気づいてほしい時代の横顔を語ってみたまでです。
「高校時代は、小さな完成品よりも、大きな未完成品をつくることだ」(阿川弘之)
「すぐに役に立つものは、すぐに役に立たなくなる」(小泉信三)
この言葉、実は、中等教育の英語にも当てはまるのです。
以上から、時代の潮目で、表面上の就職から、その幻想が弾け、実態としての真の意味での就職という通念が、ぬっくりと顔をもたげてきたのです。就職と就社とを完全に大学生に自覚を促す転機となったのが、今般の経団連主導の就活ルールの撤廃とやらです。アメリカは、企業の補充(人員)採用{※欠けた社員を補う程度で、即戦力を求められる}であるのに対し、日本は(大量)一括採用です。日本も、その潮の流れの変わり目に来てもいるのでしょう。超一流企業、一部上場大手企業には、また、東大、一橋、早慶くらいの文科省認定のスーパー・グローバル大学は、涼しい顔をしています。一方、標準国公立大学やMARCH以下の大学や、中小企業などは、危機感を募らせ、「就職問題懇談会」の座長を務める埼玉大学の山口宏樹学長などは、この就活ルールに危惧してもいます。正直、猛反発しているのです。理由はこうです。「学生の本分である学業が妨げられるおそれがある」と。これは、建前ですし、一部、本音でもあります。大学の授業と企業の面接がバッティングしたら、その学生は、企業に対して「本業の授業があります、その日は無理です。別の日にして下さい」と相手に、きっぱり異議を申しでる勇気がある学生か否かが左右してきます。“企業にしっぽを振ってお願いします的”根性ならば、その学生の資質や気質を、相手方も見抜くことでしょう。
また、正直申し上げると、公立にしても、私立にしても、面倒見がいい大学、就職課が“しっかり面倒、お世話して”くれている大学などは、猛反発している構図{※就職課が学生にアドヴァイスや戦略を与えにくくなるからでもある}からも、グローバル化の波が就活にも押し寄せてきた観が否めません。就活における弱肉強食時代の到来です。
大学も、“グローバル~”“メディア~”“総合~”“国際~”“情報~”“環境~”と当世うけする、一種、大学にもキラキラネームがあり、そうした一見時代に合わせたネーミングの大学に限り、その名が、客寄せパンダ効果の化けの皮が剥がれることを懸念もしているのが想像できます。内実の伴わない大学、そして学生が、グローバル化に不適応となりかけてもくるのでしょう。このグローバル基準の就職活動の流れに、60年以上も日本で続いてきた就活ルールが撤廃へ追いやられつつあるのです。
そもそも、キラキラネームの学部を志望する高校生は、意地悪な見方、いや、穿った見方、本音で、現場感覚から言わせてもらえば、「文学部?私、本読まないし、作家なんかほとんど知らいない、嫌だわ!」「経済学か、経済なんてやっても、そんなの学んでも、社会じゃ使いものにならないと聞いているし…。」「法学部?大学で法学学んだって、弁護士になんか絶対になれないし、行ってもしょうがないし…。」このような従来の名称を冠したアカデミックな学部への回避・消去法で、一種、リベラル・アーツ観皆無の学生を、一見「役に立つことを本学部では教えますよ」と謳うネーミングで、集客する大学が、実は、このグローバル化の波により、絶滅危惧種ともなりかけているのです。看板がはずれかけているのです。そうです、こうした大学は、ある見方をすると、大学の仮面をかぶった‘専門学校’と同じ機関であるのです。そして、その馬脚を現しかねない状況に立たされてもいるのです。その焦りが、就活ルール廃止反対姿勢にも表れているわけです。こうしたキラキラネームの大学は、欧米の基準から言えば、大学足りえていない。また、こうした大学に奨学金を借りてまで入り、卒業すると、ローンの返済で、20代後半で自己破産という憂き目にもあってしまうのです。
ですから、(大)学歴社会と従来言われてきましたが、就社から就職へ実体が変質してきているように、(大)学歴社会から学力社会へパワーシフトしてきてもいるのです。その証左が、一部の大学や知識人が指摘しているように、リベラル・アーツの再評価です。その流れで、実社会で使える日本史や世界史、また、世界の趨勢を深く読み解く宗教学、また、地政学{※最近では、中国の覇権政策から‘地経学’なるジャンルも生まれてきています}などなどです。ですから、今も、池上彰氏、半藤一利氏、出口治明氏、佐藤優氏などの新書がバカ売れしているし、少々地味でもありますが、内田樹氏や松岡正剛氏などの本も売れているのです。大学生協では、『思考の整理学』(ちくま文庫)の外山滋比古氏の書籍や京大でユニークな講座を担当されている滝本哲史氏の本などが売れているのです。キラキラネーム学部の学生には、池上彰氏以外は、疎遠な知識人たちだと思われます。表面上は、非実利的、とっつきにくいほど知的に映るからでもあるからでしょう。高校時代に、知的基盤(アカデミックへ通じる知的インフラのようなもの)が、中等教育で種付けされてもいなかったからでしょう。大学は、以上の知識人のパラダイム(物事を考えるスタイル<型>のようのもの)を独自に習得する場所でもあるのです。大学とは、本来そういう場所であったはずです。その鍛錬の場が大学という機関であることは、洋の東西を問わず自明の理であります。日本の大学が、大宅壮一の言葉からも、‘駅弁大学’から、今では、‘名ばかり大学(≒専門学校){就職予備校}’にまで墜してもいます。まるで、幕末の日本中の佐幕派の小藩(10万石以下の藩)の如き存在でもあるのです。そうした機能不全に陥っている高等教育の半数近くの大学が、財界からの圧力も受け、本来なら、大学自身で行わなければならない、また、大学で行うのが本来適してもいる、使える英語(実用英語)教育、アクティブ・ラーニング(プレゼンと前提とした真のディベート)、そして、プログラミング教育(C言語の習得)、こうしたジャンルを、高大接続教育という美辞麗句のもとに、中等教育に放り投げ、責任転嫁してきたのです。
そうです、考えてみれば明らかな事ですが、高校生の段階で、使える英語を、アクティブ・ラーニングを、そしてプログラミングを、すでに身につけていたとしたら、大学当局は一体何を教えたらいいのでしょうか?つまり、大学現場が、こうしたジャンルの、もう教えられない教育機関になっていることの証明なのです。小学校からの英語の必須化も同様です。特に、公立中学の英語の授業が機能不全、身に付かない英語教育現場に墜しているために、「だったら、手っ取り早く、小学校から英語を教えちゃえ!」と、先も読めず、短慮な判断で文科省が決定してしまったのがことの本質でしょう。育ちの悪い苗を、新緑の春からではなく、草木もやっと芽吹く晩冬から植えてしまえば、冷夏や天候不順な季節でも、見事に十分実りをつけてくれるであろうと考える、浅はかな素人農家さえしない愚挙を文科省を始めようとしているのです。
新自由主義、グローバル化、少子高齢化、AI化、こうした時代の波に押し寄せられている日本は、第二の明治維新ともいえ、知識に依る実学ではなく、勿論、これも必須アイテムですが、その必要条件だけではだめで、知性に裏打ちされた教養(リベラル・アーツ)こそ高校から大学にかけて自身の知の幹として育て上げていかねばならないのです。それが身に付いて、大学生として、十分条件たりえる人物となりえるのです。
以上、就活問題と、学生の現代気質、また、昨今の大学の変質の関係を申し上げたまでです。英精塾の生徒は、勿論、一般の高校生にも気づいてほしい時代の横顔を語ってみたまでです。
「高校時代は、小さな完成品よりも、大きな未完成品をつくることだ」(阿川弘之)
「すぐに役に立つものは、すぐに役に立たなくなる」(小泉信三)
この言葉、実は、中等教育の英語にも当てはまるのです。
2018年10月22日 16:55