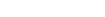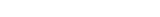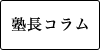カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年7月 (2)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > 永遠はearlyで生まれlateでしぼむ
コラム
永遠はearlyで生まれlateでしぼむ
「あの頃(1960~70年代)、文学というのは、永遠だと思っていた。作家も批評家もそうだったと思う。1千年先を考えた上で、いま何を書くかということを考えていたんですね。政治とか科学だけでは捉えられない、文学にしか見えないものを見ようとしていたんじゃないかな」
柄谷行人回想録より 朝日新聞2023年12月13日(水)
この柄谷の言葉を読み、自身の青春の亡霊を語る気になった。この青春の亡霊とは、院時代の教官でもあった古屋健三の『青春という亡霊』からインスピレーションを受けたともいっていい。
この文学とは、自身にとっては、一般的な意味での文学ではない。十代後半の少年から青年になりかける中学浪人時代の宅浪生にとっては、一種“宗教”また“思春期の恋”ともいっていいものだった。宗教とは、困難・苦難・不幸の最中にあって、だいたい<妙薬>ともなるが、その不運の期間を脱すると<巧妙なし薬>ともなる事例は、衆目の一致するとこでもあろうか。
齢十六から十七にかけて、両親の離婚による家庭の喪失、高校という帰属基盤からの離脱、同輩からの離別、故郷東京からの転居、すべて従来のアイデンティティー放擲の体験である。
さらに、東北の湊町における伯父宅での、遠慮を余儀なくされる居候生活といったもの、そこからの娯楽のテレビ生活からの“断食”、それまでの音楽や映画など、本来興味あるものから興味薄のものへと舵を切った。当時大ブームとなったインベーダーゲームにも興味を覚えず、アニメから漫画本の類も熱くなって読む気質も失せた。まさしく、青春の虚無への良薬を文学の中に見出そうともがいてもいた。
東京の高校を中退し、その次の年、宮城県の県立高校を再度目指すだけの、一種、“修行僧的”日常が始まった。全く無機質な日々の中、東京の高校の国語の時間に配られた、第一学習社の国語便覧なる補助教材の本をぱらぱらとめくる日々の中、近現代文学の作家たちのちょっとした評論やら経歴やら、作品紹介をつまみ読むうちに、「ああ、僕より劇的な人生を送ってもきたのか!」という感慨のもと、もっと詳しくこの明治以降の文豪とやらの実生活と名作とやらを知りたい、読みたいという渇望感から、仙台の丸善書店で、『現代日本文学大事典』(明治書院)を購入した。それが、文学というものへの馴れ初めである。
自身の内面の葛藤や苦悩、迷いなど、どこかしらに、それを癒やすとか解消するとかといった意味ではなかったと思う、それは、そうした作家や作品に、自身の同類を求める、いや、自身の人生の模索のヒントを、それとも違う、何か、自身の人格を、精神を、教養を、さらに、下世話レベルながら国語の読解力を高めてくれるのでは、と言った姑息な動機もあったやに思う。それは、英数国理社の5教科で、国語が一番足を引っ張る科目でもあったからだ。人生16年生きてきて、活字らしい本を、一冊も読んだ経験がない、これこそ、国語、いわゆる“現代文弱者”の最大の要因であったことを、この頃実感もしかけていたからだ。現代文の問題を何題も解き、ただ、ただ〇×だけをしても国語の点数なんぞは、伸びないと気づいてもいたからである。記述問題も、自己採点では伸びようもない。
活字への絶対的に接する量と時間の足りなさが、国語という科目へのコンプレックス、そして苦手意識、さらには、低得点科目という負の連鎖となっていることに気づきもしていたからである。
こうした人生上の様々な指標・海図として文学、そして、苦手科目の克服の手段としての読書、こうした両面が、ある意味、私を、文学へと誘ったことは確かである。十代後半の生きる戦略としての文学、浪人生として受験を考慮した戦術としての文学、この二重構造の精神が、文学が、実利・非実利の両面で、高校時代の私の“宗教”ともなった所以である。
中学1年の段階で、この中学生活は、“四季”と思いこむ、高校1年の入学時、この高校生活も、“四季”と思いこむ、しかし、中3で、高3で、それは、青春の幻想に過ぎぬと悟るは、人間の一日にも該当する、朝の段階では、一日が、希望に輝く、夕方には、それが希望の残照として達観される感慨と同じものである。それは、プロ野球選手の新人が、希望を、夢を抱いて、引退後の姿を思い描けない心理と同じものである。
この柄谷行人の言う文脈で、私は、大学は、文学部、それも仏文科へと進む。その後、大学4年の就活で、文学という“宗教”が永遠ではないことに、覚醒する。次の段階は、ビジネス、会社、業種というジャンルに“永遠”を抱き始めるのである。
ここで、柄谷の言葉に戻るとしよう。昭和の時代、まあ、平成前半までは、自身の信じる、自身の精進する世界、そうしたものが、いつまでも続くという淡い幻想を抱けもした。それが、アナログが社会を覆っていた時代である。これは、日本人に関してだがという断りを入れて言わせていただくと、スマートフォンという文明の利器の登場を機に、このように何かを永遠だと思う心情が、雲散霧消してしまった感が強い。
コンビの台頭が、世のモノを扱う“~商店”(通称~屋とされる業種:パン屋、酒屋、雑貨屋など)というものを絶滅させてしまい、スマホというものが、世のコトを扱うメディアから娯楽にいたる全てを一機種におさめてしまった。このスマホなる存在は、コンビニのみならず、パソコンというデジタルツールさえ放逐させん勢いである。(つづく)
柄谷行人回想録より 朝日新聞2023年12月13日(水)
この柄谷の言葉を読み、自身の青春の亡霊を語る気になった。この青春の亡霊とは、院時代の教官でもあった古屋健三の『青春という亡霊』からインスピレーションを受けたともいっていい。
この文学とは、自身にとっては、一般的な意味での文学ではない。十代後半の少年から青年になりかける中学浪人時代の宅浪生にとっては、一種“宗教”また“思春期の恋”ともいっていいものだった。宗教とは、困難・苦難・不幸の最中にあって、だいたい<妙薬>ともなるが、その不運の期間を脱すると<巧妙なし薬>ともなる事例は、衆目の一致するとこでもあろうか。
齢十六から十七にかけて、両親の離婚による家庭の喪失、高校という帰属基盤からの離脱、同輩からの離別、故郷東京からの転居、すべて従来のアイデンティティー放擲の体験である。
さらに、東北の湊町における伯父宅での、遠慮を余儀なくされる居候生活といったもの、そこからの娯楽のテレビ生活からの“断食”、それまでの音楽や映画など、本来興味あるものから興味薄のものへと舵を切った。当時大ブームとなったインベーダーゲームにも興味を覚えず、アニメから漫画本の類も熱くなって読む気質も失せた。まさしく、青春の虚無への良薬を文学の中に見出そうともがいてもいた。
東京の高校を中退し、その次の年、宮城県の県立高校を再度目指すだけの、一種、“修行僧的”日常が始まった。全く無機質な日々の中、東京の高校の国語の時間に配られた、第一学習社の国語便覧なる補助教材の本をぱらぱらとめくる日々の中、近現代文学の作家たちのちょっとした評論やら経歴やら、作品紹介をつまみ読むうちに、「ああ、僕より劇的な人生を送ってもきたのか!」という感慨のもと、もっと詳しくこの明治以降の文豪とやらの実生活と名作とやらを知りたい、読みたいという渇望感から、仙台の丸善書店で、『現代日本文学大事典』(明治書院)を購入した。それが、文学というものへの馴れ初めである。
自身の内面の葛藤や苦悩、迷いなど、どこかしらに、それを癒やすとか解消するとかといった意味ではなかったと思う、それは、そうした作家や作品に、自身の同類を求める、いや、自身の人生の模索のヒントを、それとも違う、何か、自身の人格を、精神を、教養を、さらに、下世話レベルながら国語の読解力を高めてくれるのでは、と言った姑息な動機もあったやに思う。それは、英数国理社の5教科で、国語が一番足を引っ張る科目でもあったからだ。人生16年生きてきて、活字らしい本を、一冊も読んだ経験がない、これこそ、国語、いわゆる“現代文弱者”の最大の要因であったことを、この頃実感もしかけていたからだ。現代文の問題を何題も解き、ただ、ただ〇×だけをしても国語の点数なんぞは、伸びないと気づいてもいたからである。記述問題も、自己採点では伸びようもない。
活字への絶対的に接する量と時間の足りなさが、国語という科目へのコンプレックス、そして苦手意識、さらには、低得点科目という負の連鎖となっていることに気づきもしていたからである。
こうした人生上の様々な指標・海図として文学、そして、苦手科目の克服の手段としての読書、こうした両面が、ある意味、私を、文学へと誘ったことは確かである。十代後半の生きる戦略としての文学、浪人生として受験を考慮した戦術としての文学、この二重構造の精神が、文学が、実利・非実利の両面で、高校時代の私の“宗教”ともなった所以である。
中学1年の段階で、この中学生活は、“四季”と思いこむ、高校1年の入学時、この高校生活も、“四季”と思いこむ、しかし、中3で、高3で、それは、青春の幻想に過ぎぬと悟るは、人間の一日にも該当する、朝の段階では、一日が、希望に輝く、夕方には、それが希望の残照として達観される感慨と同じものである。それは、プロ野球選手の新人が、希望を、夢を抱いて、引退後の姿を思い描けない心理と同じものである。
この柄谷行人の言う文脈で、私は、大学は、文学部、それも仏文科へと進む。その後、大学4年の就活で、文学という“宗教”が永遠ではないことに、覚醒する。次の段階は、ビジネス、会社、業種というジャンルに“永遠”を抱き始めるのである。
ここで、柄谷の言葉に戻るとしよう。昭和の時代、まあ、平成前半までは、自身の信じる、自身の精進する世界、そうしたものが、いつまでも続くという淡い幻想を抱けもした。それが、アナログが社会を覆っていた時代である。これは、日本人に関してだがという断りを入れて言わせていただくと、スマートフォンという文明の利器の登場を機に、このように何かを永遠だと思う心情が、雲散霧消してしまった感が強い。
コンビの台頭が、世のモノを扱う“~商店”(通称~屋とされる業種:パン屋、酒屋、雑貨屋など)というものを絶滅させてしまい、スマホというものが、世のコトを扱うメディアから娯楽にいたる全てを一機種におさめてしまった。このスマホなる存在は、コンビニのみならず、パソコンというデジタルツールさえ放逐させん勢いである。(つづく)
2024年3月18日 21:18