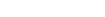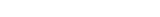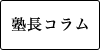カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年7月 (2)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
コラム
文化とはカルチャーでは語れない
「文化は、何も茶やピアノを習うことではない。文化とは、まっとうに生きようとする自覚的精神に裏打ちされ生き方である」(福田恆存)
「文化とは、『昨日は焦げ目のご飯だ、今日は柔らかすぎる、明日こそ美味しいご飯を炊こう』と庶民が、明日をより良く生きようとする生活の知恵なのだ」(団伊玖磨
落合陽一氏が、頻繁に用いる用語“デジタルカルチャー”というものがあります。「これからはデジタルカルチャーの時代だ」といったキャッチフレーズです。
そもそも、デジタルカルチャーとは言いますが、デジタル文化とは言いません。それが定着するのは、これから数百年後であろうと思われます。また、アナログカルチャーとも言いません。アナログ文化であります。それは、サブカルチャーやポップカルチャーとは言ってもサブ文化やポップ文化とは言わないのと同様であります。カルチャーと文化とは本義的に違うものなのです。カタカナ用語のカルチャーとは、文化などではありません。表層的文化、文化の仮面を被った文明の謂いなのです。現代(戦後)日本の手っ取り早い、若者文化を肯定する発明用語なのであります。カルチャーとは“文化”ということです。
デジタルカルチャーとは、デジタルという文明の利器で、便利、効率、安価などをベースに生活できる社会・状況くらいの意味に過ぎません。デジタルカルチャーとは、日進月歩進化、進歩、そして発展してゆく実相のことです。デジタルカルチャーとは、先日アップルのiPhone13が発売されましたが、そのスマホが、デジタルカルチャーの象徴であります。まだスマホ文化とは言いません。違和感がない方はデジタル人間の証拠であす。「スマホがあれば何でもできる、今の子どもは幸せだ」と話しているのが、堀江貴文氏であります。彼は、日ごろ「教育界は、まじめであり過ぎる」とか「勉強は要領だ」とか発言しています。確かに、受験や試験などは、そうした知の戦略ともいえる、彼のいう“ずるがしこさ”といった要領といったものも必要でしょう。しかし、教育とは、生き方の上の知識・知恵の伝授である、それも人と人とは面授面受で行うべきものであるという視点に欠けているのであります。どうも落合氏や堀江氏は、高等教育(研究≒学問)という目線で中等教育(プチ学問)や初等教育(お勉強)をお考えになっている節がなくもない。それも当然であります。彼らは、小学校や中学校時代にパソコンというデジタルというその親友の“賢さ”“有難み”を味わい、知ってしまい、生涯彼らと人生を共にしようと無意識に決意したAI社会の申し子でもあるからです。彼らには、恐らく天分としての、そこそこの地頭(開成高校・久留米大附設出身)やデジタルというものへの親和性といった資質を両面で兼ね備えた人間でもあるからです。AI内蔵のロボット犬でも十分生き物としての犬の代用が可能ではないか、そうお考えの種族でもあります。更に言わせてもらえば、毎日ホテル暮らしで、フレンチやイタリアンのグルメ食に明け暮れてもいるホリエモンも語っていることですが、「母親の手作り料理より、冷凍食品のほうがよっぽどうまい」といった文脈でもそうです。合理主義の権化の正体見たりであります。食とは、うまいまずいといった基準でするものではありません。それは、文明の尺度でのこと、食品メーカーでの試行錯誤でのことです。食とは、文化である、これを忘れてもいる。
空腹を散らすため、思考を鈍らせないため、その自身の研究に直結する頭脳の働きを邪魔しないためにも、三食のほとんどをグミというお菓子で空腹を散らし、食事を賄っている落合氏、彼らにはカルチャーという言葉は吐けるが、文化という言葉を吐く資格はありません、いや、漢字の文化なんぞは彼らの思考言語ではデリートされてもいるのです。GAFA帝国が牛耳っている世界の共通語は、日本ではカタカナが都合がいいのです。常に変化対応しやすい文字だからです。英語の一歩手前、英語本来の語義からズレる概念で、用足りやすい、重宝しやすいからです。
彼らの食という範疇での認識とやらは、ファーストフード、冷凍食品、レトルト食品、インスタント食品、これぞフードカルチャーという括りなのです。彼らには、食文化という意識が希薄であります。ホリエモンは、グルメ面してはいますが、あくまでもビジネス目線、社会的視点で、旨いまずいを語っているに過ぎません。端折っていいますが、ホリエモンには、食文化の様々な、奥底にある“コノテーション”が見えていない、いや、排除されてもるのです。
ホリエモンが主張する、寿司職人になるには、数年、十数年の修行なんて不要だ、3カ月もあれば、寿司学校で学びさえすれば、一流寿司職人になれるという文脈では、技術の継承という意味では、合理的まっとうな説である。『無駄学』(西成活裕)〔新潮選書〕の文脈では正しい論ではある。しかし、初等、中等教育においては、疑問符がつく、疑問に思わぬ親御さん限り、我が子をN高に通わせたり、スマホ学習を是としたりするものであります。
30代、20代、10代、幼児子供と低年齢化すればするほど、大の大人には睡眠といういたって不必要に思われる行為、無駄な時間が、絶対に必要なのは生物の摂理から自明であります。あのホリエモンですら、睡眠の大切を強調しているではないか、これこそが、無駄の効用とやらであります。
私は、よく引用する事例ですが、林修氏の「私の小学校時代の授業は、つまらない、なんと無駄であったか、できればその時間を返して欲しい」といった後悔の念ともとれる発言、また、中村修二氏の「日本の学校教育は、知的ゲーム、暗記ゲームのようなものだ、とっとと改革せよ」といった怨嗟のこもった批判、これらは、ある意味で、この両賢人は、自身の足元が見えていない証拠であります。他者には、鋭い理性が働くが、自身への理性の刃は鈍磨と化している<灯台下暗し識者>ともいえましょう。
林氏などは、「もし欧米のエリート初等教育でも受けていれば、もっと大成していたのに!」とか、中村氏に至っては、「アメリカの教育を受けていれば、ノーベル賞を数回受賞していたのに!」といった語気がぷんぷんと臭ってもきます。私から、言わせれば、ある意味、この“無駄”があったればこそ、今の林修がいるのであるし、中村LAバークレー校教授の地位があることを忘れてもいるのである。皮肉めいて言わせてもらえば、怪我の功名、賢者に悪妻あり、飲んだくれバカ親に賢い子あり、などなどであります。
日本食の寿司や刺身には冷凍からレトルトまでまだ不可能な領域であることが、実は日本文化こそ、世界のなかで、鎖国もどきに、文化というものが守られてもいる国なのです。「日本の常識は世界の非常識であってもいい」「日本は異常な国で構わない」(藤原正彦)
「文化なんてものは、多くの無駄の上に華開くもので、損得の計算だけで、形成されるものではない」(半藤一利)
「文化とは、『昨日は焦げ目のご飯だ、今日は柔らかすぎる、明日こそ美味しいご飯を炊こう』と庶民が、明日をより良く生きようとする生活の知恵なのだ」(団伊玖磨
落合陽一氏が、頻繁に用いる用語“デジタルカルチャー”というものがあります。「これからはデジタルカルチャーの時代だ」といったキャッチフレーズです。
そもそも、デジタルカルチャーとは言いますが、デジタル文化とは言いません。それが定着するのは、これから数百年後であろうと思われます。また、アナログカルチャーとも言いません。アナログ文化であります。それは、サブカルチャーやポップカルチャーとは言ってもサブ文化やポップ文化とは言わないのと同様であります。カルチャーと文化とは本義的に違うものなのです。カタカナ用語のカルチャーとは、文化などではありません。表層的文化、文化の仮面を被った文明の謂いなのです。現代(戦後)日本の手っ取り早い、若者文化を肯定する発明用語なのであります。カルチャーとは“文化”ということです。
デジタルカルチャーとは、デジタルという文明の利器で、便利、効率、安価などをベースに生活できる社会・状況くらいの意味に過ぎません。デジタルカルチャーとは、日進月歩進化、進歩、そして発展してゆく実相のことです。デジタルカルチャーとは、先日アップルのiPhone13が発売されましたが、そのスマホが、デジタルカルチャーの象徴であります。まだスマホ文化とは言いません。違和感がない方はデジタル人間の証拠であす。「スマホがあれば何でもできる、今の子どもは幸せだ」と話しているのが、堀江貴文氏であります。彼は、日ごろ「教育界は、まじめであり過ぎる」とか「勉強は要領だ」とか発言しています。確かに、受験や試験などは、そうした知の戦略ともいえる、彼のいう“ずるがしこさ”といった要領といったものも必要でしょう。しかし、教育とは、生き方の上の知識・知恵の伝授である、それも人と人とは面授面受で行うべきものであるという視点に欠けているのであります。どうも落合氏や堀江氏は、高等教育(研究≒学問)という目線で中等教育(プチ学問)や初等教育(お勉強)をお考えになっている節がなくもない。それも当然であります。彼らは、小学校や中学校時代にパソコンというデジタルというその親友の“賢さ”“有難み”を味わい、知ってしまい、生涯彼らと人生を共にしようと無意識に決意したAI社会の申し子でもあるからです。彼らには、恐らく天分としての、そこそこの地頭(開成高校・久留米大附設出身)やデジタルというものへの親和性といった資質を両面で兼ね備えた人間でもあるからです。AI内蔵のロボット犬でも十分生き物としての犬の代用が可能ではないか、そうお考えの種族でもあります。更に言わせてもらえば、毎日ホテル暮らしで、フレンチやイタリアンのグルメ食に明け暮れてもいるホリエモンも語っていることですが、「母親の手作り料理より、冷凍食品のほうがよっぽどうまい」といった文脈でもそうです。合理主義の権化の正体見たりであります。食とは、うまいまずいといった基準でするものではありません。それは、文明の尺度でのこと、食品メーカーでの試行錯誤でのことです。食とは、文化である、これを忘れてもいる。
空腹を散らすため、思考を鈍らせないため、その自身の研究に直結する頭脳の働きを邪魔しないためにも、三食のほとんどをグミというお菓子で空腹を散らし、食事を賄っている落合氏、彼らにはカルチャーという言葉は吐けるが、文化という言葉を吐く資格はありません、いや、漢字の文化なんぞは彼らの思考言語ではデリートされてもいるのです。GAFA帝国が牛耳っている世界の共通語は、日本ではカタカナが都合がいいのです。常に変化対応しやすい文字だからです。英語の一歩手前、英語本来の語義からズレる概念で、用足りやすい、重宝しやすいからです。
彼らの食という範疇での認識とやらは、ファーストフード、冷凍食品、レトルト食品、インスタント食品、これぞフードカルチャーという括りなのです。彼らには、食文化という意識が希薄であります。ホリエモンは、グルメ面してはいますが、あくまでもビジネス目線、社会的視点で、旨いまずいを語っているに過ぎません。端折っていいますが、ホリエモンには、食文化の様々な、奥底にある“コノテーション”が見えていない、いや、排除されてもるのです。
ホリエモンが主張する、寿司職人になるには、数年、十数年の修行なんて不要だ、3カ月もあれば、寿司学校で学びさえすれば、一流寿司職人になれるという文脈では、技術の継承という意味では、合理的まっとうな説である。『無駄学』(西成活裕)〔新潮選書〕の文脈では正しい論ではある。しかし、初等、中等教育においては、疑問符がつく、疑問に思わぬ親御さん限り、我が子をN高に通わせたり、スマホ学習を是としたりするものであります。
30代、20代、10代、幼児子供と低年齢化すればするほど、大の大人には睡眠といういたって不必要に思われる行為、無駄な時間が、絶対に必要なのは生物の摂理から自明であります。あのホリエモンですら、睡眠の大切を強調しているではないか、これこそが、無駄の効用とやらであります。
私は、よく引用する事例ですが、林修氏の「私の小学校時代の授業は、つまらない、なんと無駄であったか、できればその時間を返して欲しい」といった後悔の念ともとれる発言、また、中村修二氏の「日本の学校教育は、知的ゲーム、暗記ゲームのようなものだ、とっとと改革せよ」といった怨嗟のこもった批判、これらは、ある意味で、この両賢人は、自身の足元が見えていない証拠であります。他者には、鋭い理性が働くが、自身への理性の刃は鈍磨と化している<灯台下暗し識者>ともいえましょう。
林氏などは、「もし欧米のエリート初等教育でも受けていれば、もっと大成していたのに!」とか、中村氏に至っては、「アメリカの教育を受けていれば、ノーベル賞を数回受賞していたのに!」といった語気がぷんぷんと臭ってもきます。私から、言わせれば、ある意味、この“無駄”があったればこそ、今の林修がいるのであるし、中村LAバークレー校教授の地位があることを忘れてもいるのである。皮肉めいて言わせてもらえば、怪我の功名、賢者に悪妻あり、飲んだくれバカ親に賢い子あり、などなどであります。
日本食の寿司や刺身には冷凍からレトルトまでまだ不可能な領域であることが、実は日本文化こそ、世界のなかで、鎖国もどきに、文化というものが守られてもいる国なのです。「日本の常識は世界の非常識であってもいい」「日本は異常な国で構わない」(藤原正彦)
「文化なんてものは、多くの無駄の上に華開くもので、損得の計算だけで、形成されるものではない」(半藤一利)
2021年10月11日 16:47