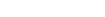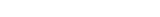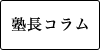カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
コラム
経験というものについて①
これまで「経験量の多寡」は、その人物の優秀さを定義する重要な尺度として用いられてきた。しかし、「社会のVUCA化」が進行することに伴って「経験の不良債権化」が進むことで「経験」への評価も大きく変わることになる。『NEWTYPE』より
※VUCAとは、V=volatile(不安定)、U=uncertain(不確実)、C=complex(複雑)、A=ambiguous(曖昧)という、今日の社会を特徴付ける4つの形容詞の頭文字を合わせた言葉です。
このような世界にあって、経験を蓄積した、蓄積した経験に依拠しようとするオールドタイプが価値を失っていく一方で、新しい環境から迅速に学習し、自分の経験をアンラーンしていくニュータイプが大きな価値を創出していくことになる。『NEWTYPE』より
『NEWTYPE ニュータイプの時代』(山口周著)ダイヤモンド社
こうした山口氏の言説というものは、何も、平成末期からのビジネス上の真理ではない。昭和の時代、元セブン&アイ会長の鈴木敏文の「発注は、店長よりもパートの主婦に任せろ」「経験の多さがモノを言った時代は“思いつきで仕事をするな”と言われたが、今や、仮説に基づいた“思いつき”のほうがむしろ重要な時代になっていることを忘れるべきではない」にしろ、平成に急成長したユニクロCEOの柳井正の「成功は一日で捨て去れ」にしろ、当然の如き、商売における成功者の鉄則でもあった。
さて、ここで語られている‘経験’というものが、この三氏によると、どうもネガティブに語られ過ぎてもいる用語に墜してしまっている感が否めない。だから、その経験という言葉を、これから数回にわたって総括してみたい。
劇的に変化する社会、長足の進歩をとげるテクノロジー、ひっくるめるとグローバル化と情報化による時代の趨勢、この中に、浮遊するビジネスには、海図はないということでもある。これは、ビジネスにおける経験則が、無力化するマイナス要因でしかないことの証明とも言える。
「変化はリスクを伴いますが、今の時代、変化しないほうがリスクが高い。」(鈴木敏文)
これは、典型的な例でもあろうが、コンビニ業界が成長著しい平成前期、他のコンビニで成功したスイーツなり、弁当やおにぎりを、自己のコンビニで真似て、二匹目のどじょう、三匹目のうなぎにありつけた懐かしい時代があった。今でも、そのビジネス流儀はあちらこちらで散見されるが、令和の時代、A社の開発商品がヒットしたからといって、B社も、C社も真似っこして、営業利益をあげられるほどお目出度い時代ではなくなってきていることが、‘経験’という、成功事例を、ビジネスモデルとして取り入れる愚かさとして山口氏は指摘してもいるのであろう。勿論、A社が成功した商品が、半年、一年とほぼ永遠に支持されるほど業界は甘くはない、いや、業界を越えて、全ての業種にあてはるビジネス定理ではある。
この‘経験’という用語をマイナスの意味で用いたものの典型として、浅学の私の知識の範疇では、次のようなものが挙げられる。
「愚者は経験に、賢者は歴史に学ぶ」(ビスマルク)
これなどは、ビジネスではなく、政治の範疇で当てはまる真実である。
戦前の大日本陸海軍である。日清・日露戦争での経験、いや、体験から抜け出せず、成功体験に則して、昭和の日本を亡国への誘った戦前の軍令部である。
バブル時、不動産投機というものに味をしめて、1990年代に、本業の小売業をなおざりにして、流通業界の雄から、消滅してしまった中内ダイエー帝国である。
こうした、成功体験(≒経験)という、一種、“アヘン”というものから脱しきれない存在というものは、政治史、経済史、日本史、世界史を紐解くまでもなく、自己の反面教師として、自覚せよという主旨でもあるのが、このビスマルクの箴言である。ここに、個人、企業、社会、そして国家レベルでそれを概観する知見を身に付けよという警告でもあろう。“成功の甘い蜜は、二度目には、苦い‘毒’ともなる”という謂いでもある。『リーダーは歴史観をみがけ』(出口治明)の新書の表題ではないが、自己の経験を脱構築する知性を、出口氏は言いたいわけでもあろう。
ところで、こうした、ビジネス上、勿論、政治経済上でも適応できるのだが、そうした文脈での‘経験’という言葉の使われ方に少々、いや、大分、違和感を感じないではいられない。それは、私に言わせれば、厳密な意味では、それは経験ではないからだ。それは、むしろ、成功体験といった方が、ふさわしい、戦術に近いものであるからだ。ここでいう、私が言いたい経験とは、むしろ戦略の領域に入る、生き残る、世代を超えた、社会全般を遍く生き残るための、そして、人格を深め、積み重なってゆく地層のような良識といったものである。それが結晶化すると、ある意味“思想”ともなる。
経験にも、社会的文脈では、上部構造の経験と下部構造の経験というものがある。また、形而上的経験と形而下的経験があるということでもある。ビジネス上の経験とは、山口氏にしろ、鈴木氏にしろ、柳井氏にしろ、後者の文脈で用いている用語、すなわち、工学部・理学部的経験の謂いに思えて仕方がないのである。日進月歩してゆく、アップデートしてゆかねばならない仕事の流儀程度のことでもある。そこで、私は、前者の文脈での経験を、これから語ってみたいと思う。その経験とは、思想家森有正が、自らの思考のコアとして用いたものである。経験というものを思想の域にまで昇華せしめた哲学者である。では、次回は、この経験というものが、ビジネスとは、また別次元で如何に大切かを語ってみたい。なぜならば、この森のいう意味での、経験というものが、実は、山口周にも、鈴木敏文にも、柳井正にも、その人間のビジネスマン以前の人格的コアを形成しているものだからである。
<余談>
自然科学上の経験、それは、‘マイナス’、社会科学上の経験、それも、“マイナス”、しかし、人文科学上の経験、それこそ、プラスとして、規定されるべき用語である。
鈴木にしろ、柳井にしろ、山口にしろ、各自のビジネス上の思想というものを身に付けておられよう。しかし、その背後に、人には言えない、さまざまな体験といった無数の出会いといったもの、それが、真の意味で、ビジネスの鉄則になる以前に、経験というものに昇華しているから、多くの人々を引き付ける金言ともなっているのである。
※VUCAとは、V=volatile(不安定)、U=uncertain(不確実)、C=complex(複雑)、A=ambiguous(曖昧)という、今日の社会を特徴付ける4つの形容詞の頭文字を合わせた言葉です。
このような世界にあって、経験を蓄積した、蓄積した経験に依拠しようとするオールドタイプが価値を失っていく一方で、新しい環境から迅速に学習し、自分の経験をアンラーンしていくニュータイプが大きな価値を創出していくことになる。『NEWTYPE』より
『NEWTYPE ニュータイプの時代』(山口周著)ダイヤモンド社
こうした山口氏の言説というものは、何も、平成末期からのビジネス上の真理ではない。昭和の時代、元セブン&アイ会長の鈴木敏文の「発注は、店長よりもパートの主婦に任せろ」「経験の多さがモノを言った時代は“思いつきで仕事をするな”と言われたが、今や、仮説に基づいた“思いつき”のほうがむしろ重要な時代になっていることを忘れるべきではない」にしろ、平成に急成長したユニクロCEOの柳井正の「成功は一日で捨て去れ」にしろ、当然の如き、商売における成功者の鉄則でもあった。
さて、ここで語られている‘経験’というものが、この三氏によると、どうもネガティブに語られ過ぎてもいる用語に墜してしまっている感が否めない。だから、その経験という言葉を、これから数回にわたって総括してみたい。
劇的に変化する社会、長足の進歩をとげるテクノロジー、ひっくるめるとグローバル化と情報化による時代の趨勢、この中に、浮遊するビジネスには、海図はないということでもある。これは、ビジネスにおける経験則が、無力化するマイナス要因でしかないことの証明とも言える。
「変化はリスクを伴いますが、今の時代、変化しないほうがリスクが高い。」(鈴木敏文)
これは、典型的な例でもあろうが、コンビニ業界が成長著しい平成前期、他のコンビニで成功したスイーツなり、弁当やおにぎりを、自己のコンビニで真似て、二匹目のどじょう、三匹目のうなぎにありつけた懐かしい時代があった。今でも、そのビジネス流儀はあちらこちらで散見されるが、令和の時代、A社の開発商品がヒットしたからといって、B社も、C社も真似っこして、営業利益をあげられるほどお目出度い時代ではなくなってきていることが、‘経験’という、成功事例を、ビジネスモデルとして取り入れる愚かさとして山口氏は指摘してもいるのであろう。勿論、A社が成功した商品が、半年、一年とほぼ永遠に支持されるほど業界は甘くはない、いや、業界を越えて、全ての業種にあてはるビジネス定理ではある。
この‘経験’という用語をマイナスの意味で用いたものの典型として、浅学の私の知識の範疇では、次のようなものが挙げられる。
「愚者は経験に、賢者は歴史に学ぶ」(ビスマルク)
これなどは、ビジネスではなく、政治の範疇で当てはまる真実である。
戦前の大日本陸海軍である。日清・日露戦争での経験、いや、体験から抜け出せず、成功体験に則して、昭和の日本を亡国への誘った戦前の軍令部である。
バブル時、不動産投機というものに味をしめて、1990年代に、本業の小売業をなおざりにして、流通業界の雄から、消滅してしまった中内ダイエー帝国である。
こうした、成功体験(≒経験)という、一種、“アヘン”というものから脱しきれない存在というものは、政治史、経済史、日本史、世界史を紐解くまでもなく、自己の反面教師として、自覚せよという主旨でもあるのが、このビスマルクの箴言である。ここに、個人、企業、社会、そして国家レベルでそれを概観する知見を身に付けよという警告でもあろう。“成功の甘い蜜は、二度目には、苦い‘毒’ともなる”という謂いでもある。『リーダーは歴史観をみがけ』(出口治明)の新書の表題ではないが、自己の経験を脱構築する知性を、出口氏は言いたいわけでもあろう。
ところで、こうした、ビジネス上、勿論、政治経済上でも適応できるのだが、そうした文脈での‘経験’という言葉の使われ方に少々、いや、大分、違和感を感じないではいられない。それは、私に言わせれば、厳密な意味では、それは経験ではないからだ。それは、むしろ、成功体験といった方が、ふさわしい、戦術に近いものであるからだ。ここでいう、私が言いたい経験とは、むしろ戦略の領域に入る、生き残る、世代を超えた、社会全般を遍く生き残るための、そして、人格を深め、積み重なってゆく地層のような良識といったものである。それが結晶化すると、ある意味“思想”ともなる。
経験にも、社会的文脈では、上部構造の経験と下部構造の経験というものがある。また、形而上的経験と形而下的経験があるということでもある。ビジネス上の経験とは、山口氏にしろ、鈴木氏にしろ、柳井氏にしろ、後者の文脈で用いている用語、すなわち、工学部・理学部的経験の謂いに思えて仕方がないのである。日進月歩してゆく、アップデートしてゆかねばならない仕事の流儀程度のことでもある。そこで、私は、前者の文脈での経験を、これから語ってみたいと思う。その経験とは、思想家森有正が、自らの思考のコアとして用いたものである。経験というものを思想の域にまで昇華せしめた哲学者である。では、次回は、この経験というものが、ビジネスとは、また別次元で如何に大切かを語ってみたい。なぜならば、この森のいう意味での、経験というものが、実は、山口周にも、鈴木敏文にも、柳井正にも、その人間のビジネスマン以前の人格的コアを形成しているものだからである。
<余談>
自然科学上の経験、それは、‘マイナス’、社会科学上の経験、それも、“マイナス”、しかし、人文科学上の経験、それこそ、プラスとして、規定されるべき用語である。
鈴木にしろ、柳井にしろ、山口にしろ、各自のビジネス上の思想というものを身に付けておられよう。しかし、その背後に、人には言えない、さまざまな体験といった無数の出会いといったもの、それが、真の意味で、ビジネスの鉄則になる以前に、経験というものに昇華しているから、多くの人々を引き付ける金言ともなっているのである。
2023年1月 9日 15:16