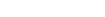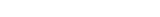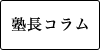カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > やさしく教えることは"シェルパ"の役割である
コラム
やさしく教えることは"シェルパ"の役割である
「少しのことにも、先達はあらまほしき事なり」『徒然草』
以下の発言は、『週刊文春』8月17日・24日号の池上彰氏の対談における一節です。ゲスト(対談相手)は、哲学者千葉雅也氏である。二つとも池上氏の発言である。実は、私にもちょっと行きすぎている思いがあります。わかりやすさが至上みたいになってしまって、わかりやすいものだけ読んでわかった気になってしまうことこそ危険だと考えて『わかりやすさの罠』(集英社新書)という本を出したくらいです。
『現代思想入門』千葉雅也著(講談社現代新書)には、「複雑なことを単純化できるのが知性なんじゃないか?」という風潮があるけれども、「世の中には、単純化したら台無しになってしまうリアリティがあり、それを尊重する必要がある」と書かれています。
例えば、ドストエフスキーの小説を例に挙げよう。『罪と罰』はわきに置くとして、『カラマーゾフの兄弟』など、世の中高生などは、一読して、その内容、ドストエフスキーの思想など読み取ることができるかどうかという問いである。恐らく、十中八九は、まず、その入門書なり、手引書、あんちょこの類の本、極端ながら、『カラマーゾフの兄弟』の漫画本の類また、映画を取っ掛かりとして、岩波文庫なりに挑むというのが、難解な書への、一般人の、‘登山ルートの入り口’でもある。
話は逸れるが、このビジネス手法で大成功を収めたのが、昭和50年代の角川春樹による、角川映画の大成功である。「観てから読むか、読んでから観るか」というコピーで大成功を収めた。大方は、‘観てから読んだ者’がほとんどだったであろう。出版界の窮余の策でもあり、映像と活字のシナジー効果で、何とか、世の活字離れを食い止めるどころか、現在の角川書店の資本を築き上げ、現在のステイタスを確立した。現在のKADOKAWA
があるのは、この角川春樹が、父、源義の硬い書店のイメージを払拭したからだ。これも、マーケティング的には、‘むずかしい’を‘やさしい’に置き換え、イメージ戦略と活字産業に成功したケーススタディでもあろうか?
一読して、その世界が了解できる者は、秀才以上の読解能力を有すものといってもいい。これは、哲学思想の面でも同じである。学校の“倫理”という授業がフックともなり、その哲学者のコアの周辺を徘徊し、その迷宮へは、大学生ともなって、踏み入れるというのが常道でもあろうか。
これは、恥ずかしい個人的経験である。16才まで、活字らしい本を一冊も読んだことがない高校1年の私は、両親の離婚を機に、高校中退し、再度、中学浪人の末、宮城県の湊町の県立高校へ入りなおした。それ以来、文学青年になり、高校時代、新潮文庫の夏目漱石の小説をほとんど読破したが、大方、その小説の主旨やあらましなど、読解力のなかった17の私は、その後、大学生になり、漱石の入門書や、漱石研究書のやさしいものを読んだあと、「ああ、そういう小説だったのか!」とその小説の本質を、数年後に認識した思い出がある。むずかしい書籍への挑戦は、それだけの読解力や知識、軽い知力がなければ、“結局は、遠回りだったなあ”!といった感慨がある。これぞ、富士山登山が、一般人には、五合目から、ヒマラヤ登山では、絶対にシェルパが必須であることと、‘難解書の登山’は同じでもあると断言できる点なのである。
また、更に、恥をさらせば、仏文科の修士論文の《フローベール論》を書いた際も、この作家の小説は、ほとんど『フローベール全集』(筑摩書房)に拠ること大であった。その引用箇所や研究書の類は、原書(フランス語のテキスト)にはあたったが、この文豪の小説は、まず、日本語訳で、論文の7~8割はお世話になった。これも、ある意味、“むずかしいをやさしく”に転用できる事例ではあるかと思う。
これは、中高生にとって、難解であるということは、未成年にとって、あの苦いビールを、CMなどで、「旨い!」と叫んでいることに等しいくらい不可解なことでもあろう。「このビールの旨さは、大人にならなければわからないんだよ!」と吐く父親の言葉ではないが、世の著名な思想や哲学は、やはり、年の功、社会的研鑽・知的経験を積まなければ、理解不能なのも当然であろうかと思う。しかし、それでは、高等教育を受ける者には、遅いのだ。せめて、その難解な思想なりを、「分かりやすく、面白く、為になったな!」と実感させるように、世の教師は、責任を負わされてもいる。それが、プラスαの教師の義務でもある。
これは、一般論だが、昭和の世代は、難しいことは、難しいなりに、自身で背伸びをして、誤解・誤訳でも、わかろうとする知的気概があった。平成後半から令和世代にかけては、自身から背伸びをして、自助努力をしてまで、難解なことを理解しようとする知的根性が無くなったといってもいい。その証拠に、現代っ子は、分からない、知らないということを恥じとは自覚していない実体を鑑みれば得心がゆくだろう。一方、私を含めて、昭和っ子は、分からない、知らないということを恥ずかしいと実感し、その場では、知ったかぶりをして、その後、その友人たちが話していた“現代思想”なるものをこっそりと勉強したものである。知的羞恥心による、“こっそり背伸びのお勉強”とやらである。ちょうど、この、昭和世代と令和世代の中間層に照準を合わせたかは知らないが、平成半ばから、ジャーナリスト池上彰氏は、スターダムにのし上がってもきた。そのバックグラウンドは、NHKの『週刊こどもニュース』のお父さん役として、政治・経済を中心に、大人の事象を子どもにもわかる視線・観点で、自身の現在のスキルを確立したものと見受けられる。これからもわかるように、大人でも、大学生でも、このように、子どもでもわかるレベルで語ることが、現在の、池上彰のジャーナリズムの本流・流儀になったようである。
この路線は、何も、政治・経済に止まらず、学校の参考書から資格系の問題集にいたるまで、“世界一わかりやすい”といったふれ込みで、また、キャッチコピーで、様々な書籍のマーケティングに見てとれよう。これに加え、SNS社会、特に、GOOGLEなどに代表されるように、図書館などでの資料の収集から、パソコンオンリー検索の時代へと面舵をきった平成から令和にかけての‘情報取集の、知的トレンド’が拍車をかけてもる。
こうしたわかりやすさの究極、末期現象が、コスパやらタイパといった流行語を挙げるまでもなく、コラムニスト武田砂鉄氏は、『わかりやすさの罪』として警鐘をならしてもいるが、耳を傾ける大衆は少数派である。理由は簡単、こうした大衆は、お金と時間、さらに、努力まで惜しんで、知識を得よう、頭をよくしょうという魂胆が熾火のように心底燻ぶっているからである。
ここで、前々回でも触れた、私なりの教育手法のことに話を戻す。
「難しいことを、易しく、易しいことを面白く、面白いことを為になると思わせ、為になると思った者を知的に教える」という、難しいから知的への“教えと学び”の円環的知的営みを生徒・学生だけでなく教師・講師にも自覚させること、これは、努力家を準秀才に、準秀才を秀才に、知的中間層の底上げをする最善手でもあると思うのだが、如何だろうか?
やさしく教えることは、知の、それは、知識の、知性の、そして教養の‘ヒマラヤ登山’に挑戦させる者にとって、シェルパの役割でもあることを、教師・講師は、強烈に自覚する必要がある。
2023年9月18日 18:13