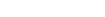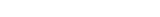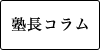カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年7月 (2)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > サントリーから学ぶべき教育というもの
コラム
サントリーから学ぶべき教育というもの
先日、テレビ朝日のガイアの夜明けという番組を観た。「“サントリー”を受け継ぐ者たち」というものである。ウィスキー部門、ワイン部門、ビール部門の人々に光を当てていた。この企業は総合酒類企業、“酒類三部門”として、総合楽器企業ヤマハ同様に、世界一ともなった。国内では、このアルコール部門以外、セサミンEなどの健康食品でも急成長し、今や、超優良企業の代表格ともいえるグローバル企業である。その同族優良企業から、サントリーホールディングスの、外部からの初めての社長が、新浪剛史で、最近某週刊誌でバッシングのターゲットともなってもいる。マスコミの妬みやっかみか?
この大企業において、個人一人、一代では、こうした食品系、特に文化を象徴するウィスキーやワインといったものは成長させることはできない。この点、GAFAMやアリババに代表されるように、十年、数十年で、ゲイツやマスクのように数十兆から百兆円の大企業となるのはとは訳が違う。マクドナルドにしろケンタッキーにしろ、飲食系では一代でビッグにはなりえても、歴史上禁酒法なるものがあったアメリカでは、酒類系のビッグ企業は考えられない。
この点、サントリーという同族経営の成功例は、学校運営や教育手法おいてとても参考になるケースである。100年先を見据えた経営、それが雄弁に物語ってもいよう。ものづくりが、自動車・家電製品といった時間や時代との戦い、いや、変化への対応力、それとはむしろ真逆の力を求められるジャンルでもあるからだ。
この関西発祥の“やってみなはれ”の企業文化を有する企業は、この番組でウィスキ―は本場イギリスに、ワインの総本山フランスに、そしてビール大国ドイツに、それぞれ肩を並べた。
先日亡くなった伊集院静の『琥珀の夢』を読むまでもなく、創業者鳥井信治郎が赤玉ポートワインから始め、ウィスキーへと乗り出し、日本の洋酒メーカーの地位を確立する。サントリーの角瓶やダルマである。二代目社長佐治敬三が、そのウィスキーを世界一の山崎というブランドで完成させる。だが、彼は、ビール部門で、キリンやアサヒに惨敗をなめるもあきらめず、ついに、ビール部門でもその一角に登り詰めるのは四代目社長佐治信忠の時である。佐治敬三がウィスキーを完成させ、ビールの種を蒔いたとも言える。プレミアムモルトである。アサヒが、スーパードライでキリンを追い抜いた樋口廣太郎が行った下剋上を、高品質で、先頭を行く二大巨頭企業に、質で並んだ、佐治敬三の悲願が成し遂げられた。
40年以上も前、佐治敬三が買収した、フランスのワインシャトーを見事立て直し、フランス人も一目置くワイナリーに近年に見事復活させた。その功労者の日本人が、山梨のサントリワイナリーで最高のワインを今や醸造している。
言わずと知れた、S・ジョブスも憧れた、日本が世界に誇れるグローバル企業SONYとこのSUNTORYは、奇遇なるかな、面白いことに似ている。余談ながら、日本でだが、SUNSARも優良企業で似てもいる。何故か、サ行(S文字)が験がいい。
SONYは、言わずと知れた、世界でもリスペクトされているグローバル企業である。このSUNTORYも然り、それに追随する勢いのあるグローバル企業になりつつある。いや、もはや、そうなってもいよう。
ソニーの盛田昭夫が語ってもいたが、「ソニーという会社は、世界のどこもやっていないこと、どこも出していない製品を作ることをモットーに、社員が、どれほど失敗に失敗を重ねてもノーとは言わずやらせてきた、その戦いの伝統が、ソニーと言うブランドでもある」『SONY ソニー自叙伝』(ワック出版部)これ、佐治敬三の名言であり社是ともいえる“やってみなはれ”と全く同じである。洋風に、月並みに言えば、チャレンジスピリットでもある。最近では、これを失敗学と大系的に呼ぶようだが、この考え、認知度と寛容度に反比例して、行う企業は激減している。バブル崩壊以後、余裕のなくなった企業とアメリカンスタンダードとも同類のグローバル化に飲み込まれてしまったこと、いわば、“失われた30年の空気”が最大の要因でもあろうか?
テスラの電気自動車、アップルのiPhone、Googleの検索機能、チャットGPTなどは、文明の範疇に入る、文明の利器に過ぎない。一方、食文化のわき役、ワインやウィスキーなるものは、文化度の指標、文化の深度を物語る。この点、イスラム文化圏は、アルコールなど生活習慣を規定するタブーがあるため、ある意味、新たな文化を生じさせにくくもしている。女性への意識がその典型でもあろうか?日本は、無宗教ともいわれる点、色々な意味で、世界中の文化をブレンドして、魅力的なる、“酒”も作れるのであろう。ここにこそ、日本食文化の豊饒性がある。
よく言われることだが、日本という国に居ながらにして、一流のフランス料理が食せる、一流の中国料理が身近にある、一流のイタリア料理店(サッカーのザッケローニ監督も驚いた味が存在する)が存在している。こんな国、世界広しといえどもない。ミシュランの名店が一倍多い都市が東京であることが何よりの証拠である。世界料理は言うまでもなく、本場インド人まで魅了する、日本のカレーライス、欧米人や韓国人も虜にするトンカツ、そして、オムライスからナポリタンにいたる洋食文化、さらに、今や、世界を席巻してしている寿司文化なるものまである。酒から食にいたるまで、日本は食文化のメッカ、総本山なのだ。
今や、GDPで中国に抜かれ3位であったと思いきや、今年、ドイツに抜かれ4位となった。近い将来、インドは当然、インドネシアやベトナムにも抜かれかねない状況にいる。
よく、政府が、国が、巷ですら、ノーベル賞受賞者を多く出すとか、ジョブスやゲイツのような人材を如何に生み出すかといった言説が流れるが、こうして天才は、教育で生まれるものでないことは、近年最も注目されている作家橘玲の『言ってはいけない 残酷すぎる真実』(新潮新書)『無理ゲー社会』(小学館新書)『運は遺伝する 橘玲・安藤寿康共著』(NHK出版新書)などを読むまでなく、到底夢物語であることは、使える英語を身に付けさせる中等教育の英語教育の現実に近いものがある。
教育で要諦とすべきは、如何に<鳥井信治郎>や<佐治敬三>を生み出すか、また、そうしたメンタルを有することが是であると認識させる教育にあると思うのだが、如何であろうか?
中国やインド、また、アメリカでも、IT長者は生まれても、<鳥井信治郎>や<佐治敬三>は、生まれてくる文化風土にはない。ここに、起業のみならず教育においても、“advantage”が日本にはあることを痛感することから、少子高齢化の、自信を失った日本の指針というものが見えてもくる。
ジョブスより佐治敬三の方が、ある意味、凄いと感じる感性・知性、それもまた教養とも呼ぶことのできる側面ではある。こうした教養なきものが、文科省を率いてもいるし、彼らが、今の教育界に、昭和の時代の日教組の如き幅を利かせてもいる。
この大企業において、個人一人、一代では、こうした食品系、特に文化を象徴するウィスキーやワインといったものは成長させることはできない。この点、GAFAMやアリババに代表されるように、十年、数十年で、ゲイツやマスクのように数十兆から百兆円の大企業となるのはとは訳が違う。マクドナルドにしろケンタッキーにしろ、飲食系では一代でビッグにはなりえても、歴史上禁酒法なるものがあったアメリカでは、酒類系のビッグ企業は考えられない。
この点、サントリーという同族経営の成功例は、学校運営や教育手法おいてとても参考になるケースである。100年先を見据えた経営、それが雄弁に物語ってもいよう。ものづくりが、自動車・家電製品といった時間や時代との戦い、いや、変化への対応力、それとはむしろ真逆の力を求められるジャンルでもあるからだ。
この関西発祥の“やってみなはれ”の企業文化を有する企業は、この番組でウィスキ―は本場イギリスに、ワインの総本山フランスに、そしてビール大国ドイツに、それぞれ肩を並べた。
先日亡くなった伊集院静の『琥珀の夢』を読むまでもなく、創業者鳥井信治郎が赤玉ポートワインから始め、ウィスキーへと乗り出し、日本の洋酒メーカーの地位を確立する。サントリーの角瓶やダルマである。二代目社長佐治敬三が、そのウィスキーを世界一の山崎というブランドで完成させる。だが、彼は、ビール部門で、キリンやアサヒに惨敗をなめるもあきらめず、ついに、ビール部門でもその一角に登り詰めるのは四代目社長佐治信忠の時である。佐治敬三がウィスキーを完成させ、ビールの種を蒔いたとも言える。プレミアムモルトである。アサヒが、スーパードライでキリンを追い抜いた樋口廣太郎が行った下剋上を、高品質で、先頭を行く二大巨頭企業に、質で並んだ、佐治敬三の悲願が成し遂げられた。
40年以上も前、佐治敬三が買収した、フランスのワインシャトーを見事立て直し、フランス人も一目置くワイナリーに近年に見事復活させた。その功労者の日本人が、山梨のサントリワイナリーで最高のワインを今や醸造している。
言わずと知れた、S・ジョブスも憧れた、日本が世界に誇れるグローバル企業SONYとこのSUNTORYは、奇遇なるかな、面白いことに似ている。余談ながら、日本でだが、SUNSARも優良企業で似てもいる。何故か、サ行(S文字)が験がいい。
SONYは、言わずと知れた、世界でもリスペクトされているグローバル企業である。このSUNTORYも然り、それに追随する勢いのあるグローバル企業になりつつある。いや、もはや、そうなってもいよう。
ソニーの盛田昭夫が語ってもいたが、「ソニーという会社は、世界のどこもやっていないこと、どこも出していない製品を作ることをモットーに、社員が、どれほど失敗に失敗を重ねてもノーとは言わずやらせてきた、その戦いの伝統が、ソニーと言うブランドでもある」『SONY ソニー自叙伝』(ワック出版部)これ、佐治敬三の名言であり社是ともいえる“やってみなはれ”と全く同じである。洋風に、月並みに言えば、チャレンジスピリットでもある。最近では、これを失敗学と大系的に呼ぶようだが、この考え、認知度と寛容度に反比例して、行う企業は激減している。バブル崩壊以後、余裕のなくなった企業とアメリカンスタンダードとも同類のグローバル化に飲み込まれてしまったこと、いわば、“失われた30年の空気”が最大の要因でもあろうか?
テスラの電気自動車、アップルのiPhone、Googleの検索機能、チャットGPTなどは、文明の範疇に入る、文明の利器に過ぎない。一方、食文化のわき役、ワインやウィスキーなるものは、文化度の指標、文化の深度を物語る。この点、イスラム文化圏は、アルコールなど生活習慣を規定するタブーがあるため、ある意味、新たな文化を生じさせにくくもしている。女性への意識がその典型でもあろうか?日本は、無宗教ともいわれる点、色々な意味で、世界中の文化をブレンドして、魅力的なる、“酒”も作れるのであろう。ここにこそ、日本食文化の豊饒性がある。
よく言われることだが、日本という国に居ながらにして、一流のフランス料理が食せる、一流の中国料理が身近にある、一流のイタリア料理店(サッカーのザッケローニ監督も驚いた味が存在する)が存在している。こんな国、世界広しといえどもない。ミシュランの名店が一倍多い都市が東京であることが何よりの証拠である。世界料理は言うまでもなく、本場インド人まで魅了する、日本のカレーライス、欧米人や韓国人も虜にするトンカツ、そして、オムライスからナポリタンにいたる洋食文化、さらに、今や、世界を席巻してしている寿司文化なるものまである。酒から食にいたるまで、日本は食文化のメッカ、総本山なのだ。
今や、GDPで中国に抜かれ3位であったと思いきや、今年、ドイツに抜かれ4位となった。近い将来、インドは当然、インドネシアやベトナムにも抜かれかねない状況にいる。
よく、政府が、国が、巷ですら、ノーベル賞受賞者を多く出すとか、ジョブスやゲイツのような人材を如何に生み出すかといった言説が流れるが、こうして天才は、教育で生まれるものでないことは、近年最も注目されている作家橘玲の『言ってはいけない 残酷すぎる真実』(新潮新書)『無理ゲー社会』(小学館新書)『運は遺伝する 橘玲・安藤寿康共著』(NHK出版新書)などを読むまでなく、到底夢物語であることは、使える英語を身に付けさせる中等教育の英語教育の現実に近いものがある。
教育で要諦とすべきは、如何に<鳥井信治郎>や<佐治敬三>を生み出すか、また、そうしたメンタルを有することが是であると認識させる教育にあると思うのだが、如何であろうか?
中国やインド、また、アメリカでも、IT長者は生まれても、<鳥井信治郎>や<佐治敬三>は、生まれてくる文化風土にはない。ここに、起業のみならず教育においても、“advantage”が日本にはあることを痛感することから、少子高齢化の、自信を失った日本の指針というものが見えてもくる。
ジョブスより佐治敬三の方が、ある意味、凄いと感じる感性・知性、それもまた教養とも呼ぶことのできる側面ではある。こうした教養なきものが、文科省を率いてもいるし、彼らが、今の教育界に、昭和の時代の日教組の如き幅を利かせてもいる。
2023年12月 4日 17:32