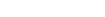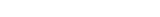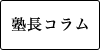カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年7月 (2)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > 表層的ビートたけし論=中退者の美学=
コラム
表層的ビートたけし論=中退者の美学=
「私が本当にやりたかったことはお笑いではありません。お笑いは二番手でした。いまでも、ノーベル賞を受賞した科学者を見ると嫉妬します。」
『弔辞』(ビートたけし)講談社
ビートたけしは、明治大学理工学部を、きちんと授業に出て、その単位を取り、あと数コマとれば卒業できるというところで、中退する。そのきっかけは、私の知る限りわからないが、恐らくは、教育熱心な畏母の、また、優秀な兄の、それぞれ間接的影響やもしれないが、このまま、理系の道、研究者にしろ、工業製品を作るメーカーなんぞのサラリーマンにしろ、何か茫漠とした虚無感、何らかの非刺激的な人生、どこかしらまったりとした日常、こうした人生行路の前途に、無意識的な嫌気、拒否感というものが、彼をそうさせたのかもしれない。浅草で芸人の卵としてフランス座に赴く前は、畏母さきさんに無断で中退し、様々なアルバイト生活を長年経験している。この時期に、映画監督若松孝二や作家中上健次などにも出会ってもいる。その後の映画監督や小説家の北野武を暗示してもいる。
80年代初期、ツービートで一世を風靡する、その後、漫才ブームがしぼみ、色々な漫才師が消えてゆく中で、ビートたけしは、フジテレビの『おれたちひょうきん族』で、TBSの怪物番組『8時だよ!全員集合』を下剋上した。また、深夜番組のオールナイトニッポンで若者のカリスマにもなる。この頃である、彼を慕い、有楽町のニッポン放送の入り口で出待ちし、「弟子にしてください」と芋づる式に弟子が増えていった、いわゆる、たけし軍団(そのまんま東など)の誕生である。こうした弟子の連中を食わせてもゆく意味でもあった、彼自身の企画・構成の『ビートたけしのスポーツ大将』(テレビ朝日)・『風雲たけし城』(TBS)といった名物番組が生まれた。前者の路線は、野球やサッカーを“演じる”とんねるずに、後者は、ガキ使の路線としてダウンタウンにバラエティー番組として継承されてもゆく。その企画発想力には、瞠目する。
80年代後半は、日本テレビの『天才・たけしの元気がでるテレビ』{※この番組で、テリー伊藤が頭角を現す!}『スーパージョッキー』{※アシスタントとして、“生意気”蓮舫が知名度を上げる!}など、ビートたけしの人気が国民的にもなり、一種、「他の芸人とは、ちっと違うんじゃないか」といった資質、つまり“天才”の匂いを、大衆が嗅ぎ始めた頃でもある。この嗅覚、実は、日本人よりフランス人の方が断然鋭い点は、彼への評価が、勲章授与などによっても証明されていよう。こうした最中に、あのフライデー事件が起こる。この事件で、北野武は、ある意味、全てを失った。その謹慎の間、弟子のガダルカナル・タカの実家がある伊豆湯ヶ島の旅館で、マスコミから長らく姿を隠す、隠棲生活を長きにわたり送る。その間に、理由は色々あるが、興味本位で小中の教科書“国数(算)理社”を取り寄せ、全てを“読猟”する。「これって(勉強って)、おもしれじゃん!これを、番組企画で取り入れたら、超受ける!」そう確信したそうである。事実、この時の彼の実感は、池上彰と佐藤優の共著『人生に必要な教養は中学教科書ですべて身につく』(中央公論社)で30年後に証明されてもいる。いわば、学びの面白さへの覚醒である。教養とは、この文脈で言えば、<知への渇望>ともいえるようなものなのだ。
謹慎が解けた後、ビートたけしは、この企画をフジテレビとフリーになって大成功したアナ逸見政孝に持ち込み、それが、あの有名な『たけし・逸見の平成教育委員会』ともなり、その後題名は変わるが、1991年から1997年まで続くのである。この番組からたけしが下りたのは、かの有名な、たけしも終わったと称された、顔面神経麻痺ともなった“バイク事故”である。この事件について、たけしは、ぽろっと、「弟子のスクーターに乗っていて、スピードを上げて、猛スピードでこのまま死んだら…、と考えているうちに、こうなっちまった…」この、彼自身でもなんともいえない心境の裏側には、富も名声も得てしまったあと、当然、映画監督としての地歩も築きつつあった頃でもあり、「俺に、何か言ってくれる奴がもう誰もいなくなってしまった!」という、ニヒリズムのようなものが、引きがねだったように思われる。
このバイク事故から、一応、回復して、彼が手掛けた番組は、テレビ東京の『誰でもピカソ』である。彼のアート感覚、芸術家的感性を生かした番組である。たけしの、玄人はだしの画家としても名高い面目躍如である。この番組は、1997年から数年続く。因みに、この97年、『HANA-BI』がヴェネチア国際映画祭のグランプリを獲得する。彼が、お笑いの次に、映画でも“天下”をとった年でもある。
2006年から2013年まで、フジテレビの深夜番組『たけしのコマ(ネチ)大数学科』をたけしは企画する。大学生までの、自己の理系の道へ復讐、数学愛への未練、密かに秘めた理系科目への矜持、こうしたものが、この番組から伝わってもきた。還暦を前にした、北野武の、青春への回帰ともいえる番組である。
ざっと、北野武のテレビ番組を概観すると、彼の、人生の“もし~・~たら”が垣間見えてもくる。ここにも、彼の、趣味の、得意分野の多彩さがうかがい知れる。更に、前回引用した言葉、“人生とは厳粛なる趣味”の公理が、ものの見事に、北野武(畏母に扇動された学生)⇒ツービート(漫才師)⇒ビートたけし(ピン芸人)⇒北野武(マルチタレント:多くの才能を持つという意味である)と変遷する人生で、円環的弧を描いていることが首肯できる。気障(きざ)な言い回しでもあるが、彼は別れた彼女、一緒になれなかった彼女、そうした女性を、心の中で愛し続けた男、それを、仕事の肥やしとしたのかもしれない、それを、ある意味“出汁”に、自身のキャリアを積み上げてもきたやもしれぬ。それは、サザンの桑田佳祐が、自身の“コンプレックス”で、名曲を書くパッションにも似ていよう。また、『源氏物語』の光源氏の恋愛遍歴の魅力とダブってきてしまうのは、私の妄想であろうか?いや、彼の歌う『浅草キッド』の通奏低音ともいえる、夢見し者のエレジーがそれを否定してくれる。それを、強力なるさびしさ、さびしさのたくましさとも言い得る気質なのである。彼の新書『さみしさの研究』にその片鱗が垣間見えもする。
彼の人生を集約するような彼の本の題名を列記すれば、以下のようになろう。
『人生に期待するな』『新しい道徳』『さみしさの研究』『アナログ』『ニッポンが壊れる』
これらの表題のメッセージ性というものを深読みすれば、彼の深層心理の何かが感じ取れもする。
私が、ここで言いたいのは、大学を中退して、ツービートとしての漫才師として世の脚光を浴びるまでの、“闇歴史”、いわゆる、“潜伏期間”というものが、彼のその後を規定しもした。当然、少年時代からの教育・経験もあろう、それらを含めて、独自に、<知の狼>であり続けたのが、たけしの20代でもあったということである。
日曜日の名物番組『たけしのTVタックル』の司会者阿川佐和子の畏父である、作家阿川弘之のことばである。
「高校時代は、小さな完成品より、大きな未完成品を作る時代である」
この謂いになぞられるならば、恐らくは、北野武は、芸人デビューするまで、様々なる大中小の未完成品を作っていたとも言いうる。その未完成品を、80年代以降、漫才ブームが萎んだ後に、それを自己流に、それぞれ完成させてもいった、その成功品が、数々の名物番組であり、小説であり、もっとも大成した映画でもあったといえるのではないか、その意味で、たけしが手掛けた数々の仕事は、ある意味、<厳粛なる趣味>の完成形でもあった。
こうした意味で、大学中退者ビートだけしから学ぶべきは、好きなことだけをしろといったホリエモン的学習態度ではなく、敢えて好きでないことも無視するなということである。いわゆる、英国社(日本史のみ)だけではなく、英国社(日本史・世界史・地理・政経など)に、オマケと言ったら語弊もあるが、数理(物理・化学・生物など)をも苦手であっても、受験科目にはなくても、学んでおこうという、分からなくても何とか知っておこう、理解しよう、そういった学びの気概、知の貪欲さ、こういったものの代名詞、それが、北野武の正体、<知の狼>であってきた証明でもある。あてどないフランス座のエレベーターボーイ北野武、そうした厳粛なる趣味を耕してもいった姿、それこそが、影のプロフィールだったやもしれない。こうした、キャラの芽を摘んでいるのが、まさしく、デジタル社会、効率主義、実用主義でもある。だから、そういう意味で、そうした環境にある現況に対して、小説『アナログ』を暗示的批判をこめて書いたのが本音のところでもあったろう。
自伝的エッセイ『たけしくん、ハイ!』の頃のたけしは、実際のところ、算数(数学)と図工(美術)が得意だった。また、プロ野球の名選手星野仙一、田淵幸一、山本浩二、東尾修、山田久志と同世代でもあったことから、長嶋に憧れた野球少年でもあった。因みに、そうした学生選手がドラフトにかかったのは、1968年、たけしが大学を中退する頃とダブる、何かの因縁めいたにおいがしてならない。大学中退以後、理系の道へは、未練を残しながらも封印し、文系のジャンルを耕してもいった。餓えた知が、あらゆるものを闇雲に吸収してもいったのだろう、その過程で、お笑いというジャンルが、自身の天分の一つとして気づいたのであろう。しかし、あの理系への憧憬は、心の内奥に仕舞われたままであった。魔が差した、不本意ながら、大学時代の、小学生から知り合いだった彼女と別れたようなこと、それが、明治大学工学部の中退だったのかもしれない。その彼女とは、光源氏の最初の女性、藤壺のようなものだった。その後、様々な女性と浮名を流し(たけしは何でも知ってるじゃんといった評判)、成長してもゆくのは、北野武からビートたけしへ、ビートたけしから北野武への帰還の過程の姿だったのやもしれない。このたけしの知への愛は、光源氏の女性への愛とダブっても見えてきてしまう。そして、紫式部は、物語の中で光源氏には、語らせてはいないが、「私が一番愛した女性は、実は、藤壺であった」と。この、吐露こそが、あの『弔辞』の中の一文の真意でもあろう。こうした、女性への愛は、一般常識でもあろう、しかし、哲学“philosophy”という言葉の語源とは、「知を愛する」という意味である。この意味で、北野武は、大学中退という、理系の女性への横恋慕をずっと引きずり続けながらも、自身の<愛知>を満たす営みを50年以上も続けてもきたのであろう。その人生行路で、“藤壺”{科学者}の姪でもある“紫の上”という、映画監督にも巡りあったとも言えなくもない。
「彼は科学者にもなれたろう、軍人にもなれたろう、小説家にもなれたろう、然し彼は彼以外のものにはなれなかった。これは驚く可き事実である。」
『様々なる意匠』(小林秀雄)
『弔辞』(ビートたけし)講談社
ビートたけしは、明治大学理工学部を、きちんと授業に出て、その単位を取り、あと数コマとれば卒業できるというところで、中退する。そのきっかけは、私の知る限りわからないが、恐らくは、教育熱心な畏母の、また、優秀な兄の、それぞれ間接的影響やもしれないが、このまま、理系の道、研究者にしろ、工業製品を作るメーカーなんぞのサラリーマンにしろ、何か茫漠とした虚無感、何らかの非刺激的な人生、どこかしらまったりとした日常、こうした人生行路の前途に、無意識的な嫌気、拒否感というものが、彼をそうさせたのかもしれない。浅草で芸人の卵としてフランス座に赴く前は、畏母さきさんに無断で中退し、様々なアルバイト生活を長年経験している。この時期に、映画監督若松孝二や作家中上健次などにも出会ってもいる。その後の映画監督や小説家の北野武を暗示してもいる。
80年代初期、ツービートで一世を風靡する、その後、漫才ブームがしぼみ、色々な漫才師が消えてゆく中で、ビートたけしは、フジテレビの『おれたちひょうきん族』で、TBSの怪物番組『8時だよ!全員集合』を下剋上した。また、深夜番組のオールナイトニッポンで若者のカリスマにもなる。この頃である、彼を慕い、有楽町のニッポン放送の入り口で出待ちし、「弟子にしてください」と芋づる式に弟子が増えていった、いわゆる、たけし軍団(そのまんま東など)の誕生である。こうした弟子の連中を食わせてもゆく意味でもあった、彼自身の企画・構成の『ビートたけしのスポーツ大将』(テレビ朝日)・『風雲たけし城』(TBS)といった名物番組が生まれた。前者の路線は、野球やサッカーを“演じる”とんねるずに、後者は、ガキ使の路線としてダウンタウンにバラエティー番組として継承されてもゆく。その企画発想力には、瞠目する。
80年代後半は、日本テレビの『天才・たけしの元気がでるテレビ』{※この番組で、テリー伊藤が頭角を現す!}『スーパージョッキー』{※アシスタントとして、“生意気”蓮舫が知名度を上げる!}など、ビートたけしの人気が国民的にもなり、一種、「他の芸人とは、ちっと違うんじゃないか」といった資質、つまり“天才”の匂いを、大衆が嗅ぎ始めた頃でもある。この嗅覚、実は、日本人よりフランス人の方が断然鋭い点は、彼への評価が、勲章授与などによっても証明されていよう。こうした最中に、あのフライデー事件が起こる。この事件で、北野武は、ある意味、全てを失った。その謹慎の間、弟子のガダルカナル・タカの実家がある伊豆湯ヶ島の旅館で、マスコミから長らく姿を隠す、隠棲生活を長きにわたり送る。その間に、理由は色々あるが、興味本位で小中の教科書“国数(算)理社”を取り寄せ、全てを“読猟”する。「これって(勉強って)、おもしれじゃん!これを、番組企画で取り入れたら、超受ける!」そう確信したそうである。事実、この時の彼の実感は、池上彰と佐藤優の共著『人生に必要な教養は中学教科書ですべて身につく』(中央公論社)で30年後に証明されてもいる。いわば、学びの面白さへの覚醒である。教養とは、この文脈で言えば、<知への渇望>ともいえるようなものなのだ。
謹慎が解けた後、ビートたけしは、この企画をフジテレビとフリーになって大成功したアナ逸見政孝に持ち込み、それが、あの有名な『たけし・逸見の平成教育委員会』ともなり、その後題名は変わるが、1991年から1997年まで続くのである。この番組からたけしが下りたのは、かの有名な、たけしも終わったと称された、顔面神経麻痺ともなった“バイク事故”である。この事件について、たけしは、ぽろっと、「弟子のスクーターに乗っていて、スピードを上げて、猛スピードでこのまま死んだら…、と考えているうちに、こうなっちまった…」この、彼自身でもなんともいえない心境の裏側には、富も名声も得てしまったあと、当然、映画監督としての地歩も築きつつあった頃でもあり、「俺に、何か言ってくれる奴がもう誰もいなくなってしまった!」という、ニヒリズムのようなものが、引きがねだったように思われる。
このバイク事故から、一応、回復して、彼が手掛けた番組は、テレビ東京の『誰でもピカソ』である。彼のアート感覚、芸術家的感性を生かした番組である。たけしの、玄人はだしの画家としても名高い面目躍如である。この番組は、1997年から数年続く。因みに、この97年、『HANA-BI』がヴェネチア国際映画祭のグランプリを獲得する。彼が、お笑いの次に、映画でも“天下”をとった年でもある。
2006年から2013年まで、フジテレビの深夜番組『たけしのコマ(ネチ)大数学科』をたけしは企画する。大学生までの、自己の理系の道へ復讐、数学愛への未練、密かに秘めた理系科目への矜持、こうしたものが、この番組から伝わってもきた。還暦を前にした、北野武の、青春への回帰ともいえる番組である。
ざっと、北野武のテレビ番組を概観すると、彼の、人生の“もし~・~たら”が垣間見えてもくる。ここにも、彼の、趣味の、得意分野の多彩さがうかがい知れる。更に、前回引用した言葉、“人生とは厳粛なる趣味”の公理が、ものの見事に、北野武(畏母に扇動された学生)⇒ツービート(漫才師)⇒ビートたけし(ピン芸人)⇒北野武(マルチタレント:多くの才能を持つという意味である)と変遷する人生で、円環的弧を描いていることが首肯できる。気障(きざ)な言い回しでもあるが、彼は別れた彼女、一緒になれなかった彼女、そうした女性を、心の中で愛し続けた男、それを、仕事の肥やしとしたのかもしれない、それを、ある意味“出汁”に、自身のキャリアを積み上げてもきたやもしれぬ。それは、サザンの桑田佳祐が、自身の“コンプレックス”で、名曲を書くパッションにも似ていよう。また、『源氏物語』の光源氏の恋愛遍歴の魅力とダブってきてしまうのは、私の妄想であろうか?いや、彼の歌う『浅草キッド』の通奏低音ともいえる、夢見し者のエレジーがそれを否定してくれる。それを、強力なるさびしさ、さびしさのたくましさとも言い得る気質なのである。彼の新書『さみしさの研究』にその片鱗が垣間見えもする。
彼の人生を集約するような彼の本の題名を列記すれば、以下のようになろう。
『人生に期待するな』『新しい道徳』『さみしさの研究』『アナログ』『ニッポンが壊れる』
これらの表題のメッセージ性というものを深読みすれば、彼の深層心理の何かが感じ取れもする。
私が、ここで言いたいのは、大学を中退して、ツービートとしての漫才師として世の脚光を浴びるまでの、“闇歴史”、いわゆる、“潜伏期間”というものが、彼のその後を規定しもした。当然、少年時代からの教育・経験もあろう、それらを含めて、独自に、<知の狼>であり続けたのが、たけしの20代でもあったということである。
日曜日の名物番組『たけしのTVタックル』の司会者阿川佐和子の畏父である、作家阿川弘之のことばである。
「高校時代は、小さな完成品より、大きな未完成品を作る時代である」
この謂いになぞられるならば、恐らくは、北野武は、芸人デビューするまで、様々なる大中小の未完成品を作っていたとも言いうる。その未完成品を、80年代以降、漫才ブームが萎んだ後に、それを自己流に、それぞれ完成させてもいった、その成功品が、数々の名物番組であり、小説であり、もっとも大成した映画でもあったといえるのではないか、その意味で、たけしが手掛けた数々の仕事は、ある意味、<厳粛なる趣味>の完成形でもあった。
こうした意味で、大学中退者ビートだけしから学ぶべきは、好きなことだけをしろといったホリエモン的学習態度ではなく、敢えて好きでないことも無視するなということである。いわゆる、英国社(日本史のみ)だけではなく、英国社(日本史・世界史・地理・政経など)に、オマケと言ったら語弊もあるが、数理(物理・化学・生物など)をも苦手であっても、受験科目にはなくても、学んでおこうという、分からなくても何とか知っておこう、理解しよう、そういった学びの気概、知の貪欲さ、こういったものの代名詞、それが、北野武の正体、<知の狼>であってきた証明でもある。あてどないフランス座のエレベーターボーイ北野武、そうした厳粛なる趣味を耕してもいった姿、それこそが、影のプロフィールだったやもしれない。こうした、キャラの芽を摘んでいるのが、まさしく、デジタル社会、効率主義、実用主義でもある。だから、そういう意味で、そうした環境にある現況に対して、小説『アナログ』を暗示的批判をこめて書いたのが本音のところでもあったろう。
自伝的エッセイ『たけしくん、ハイ!』の頃のたけしは、実際のところ、算数(数学)と図工(美術)が得意だった。また、プロ野球の名選手星野仙一、田淵幸一、山本浩二、東尾修、山田久志と同世代でもあったことから、長嶋に憧れた野球少年でもあった。因みに、そうした学生選手がドラフトにかかったのは、1968年、たけしが大学を中退する頃とダブる、何かの因縁めいたにおいがしてならない。大学中退以後、理系の道へは、未練を残しながらも封印し、文系のジャンルを耕してもいった。餓えた知が、あらゆるものを闇雲に吸収してもいったのだろう、その過程で、お笑いというジャンルが、自身の天分の一つとして気づいたのであろう。しかし、あの理系への憧憬は、心の内奥に仕舞われたままであった。魔が差した、不本意ながら、大学時代の、小学生から知り合いだった彼女と別れたようなこと、それが、明治大学工学部の中退だったのかもしれない。その彼女とは、光源氏の最初の女性、藤壺のようなものだった。その後、様々な女性と浮名を流し(たけしは何でも知ってるじゃんといった評判)、成長してもゆくのは、北野武からビートたけしへ、ビートたけしから北野武への帰還の過程の姿だったのやもしれない。このたけしの知への愛は、光源氏の女性への愛とダブっても見えてきてしまう。そして、紫式部は、物語の中で光源氏には、語らせてはいないが、「私が一番愛した女性は、実は、藤壺であった」と。この、吐露こそが、あの『弔辞』の中の一文の真意でもあろう。こうした、女性への愛は、一般常識でもあろう、しかし、哲学“philosophy”という言葉の語源とは、「知を愛する」という意味である。この意味で、北野武は、大学中退という、理系の女性への横恋慕をずっと引きずり続けながらも、自身の<愛知>を満たす営みを50年以上も続けてもきたのであろう。その人生行路で、“藤壺”{科学者}の姪でもある“紫の上”という、映画監督にも巡りあったとも言えなくもない。
「彼は科学者にもなれたろう、軍人にもなれたろう、小説家にもなれたろう、然し彼は彼以外のものにはなれなかった。これは驚く可き事実である。」
『様々なる意匠』(小林秀雄)
2024年11月 4日 16:33