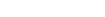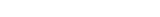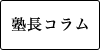カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
HOME > コラム > 余は如何にして帰宅部となりしか(後半)
コラム
余は如何にして帰宅部となりしか(後半)
高校時代、私が帰宅部となった動機である。これこそが、帰宅部として、令和時代の教育的文脈からすると、最もうなずける、大義名分的、そして、Z世代にも、理解してもらえるものかと思う。
私は、両親の離婚を機に、東京の高校を1学期途中で中退した。その契機に関して、その後の8か月ほどの中学浪人時代の詳細は、この場で省くとして、この東北の片田舎での宅浪時代というものが、17才以降の私の個性、また、表層的人格、知的な趣向をも決定したともいっていい。そのことを考慮の上で、高校時代の、「余は如何にして帰宅部となりしか」の後半を読んでいただけば幸いである。
まず、私の母校である県立石巻高校に関してである。県北では、一応の進学校である。週刊朝日の名編集長扇谷正造、俳優中村雅俊、芥川作家辺見庸などを輩出した旧制中学の流れを汲む普通科の学校でもある。東北屈指の湊町にあることもあり、校風はバンカラ、漁師〔※遠洋漁業の船乗りも含む〕の息子がクラスには数名はいた。農家の息子もちらほらいた。驚いたことに、クラスには、1人か2人は、私同様、中学浪人している者がいたという事実であった。東北新幹線などなき時代、東京と地方の文化的な格差や色合いなど明々白々の昭和である。生徒も、あたり前ながら、非都会的気質の者が多かった。スポーツではラグビーが強かった。気仙沼や古川といった学区違いの秀才は、仙台は遠いこともあったのだろう、この石巻市に下宿している者も多かった。
これは、地方・田舎の都会化の顕れともなっている事例などで一つ挙げておく。
ちょうど私が高校1年の後半であっただろうか、具体的には、述べないが、この高校の独特のしきたりというものがあった。応援練習〔上級生による一種、イジメ的慣習である〕、過激な(?!)体育祭、独特の(?!)文化祭などにかかわらざるをえない立場上、嫌で嫌で堪らず、いよいよ担任のW先生へ、母同行で、退学の相談にまで伺った。大検ルートで、さっさと、大学へ進む進路を手にするべきか否かという迷いからである。しかし、その場で、母子家庭、また、宅浪生活で、孤独とも再び向きあうこれからなどを考えて、様々な前途の光景を思い描いては、その場では思いとどまった。東京からやってきた、それも、少々、趣味など洗練され(?!)、おぼっちゃん系(?!)の高校に通っていた私には、衝撃的なものの連続であった。デリカシーがない、やぼったい、あらくれといた性質とも、思春期には、感じられる学校の校風に、胸くそが悪くなった、嫌悪感すら覚えた。江戸っ子気質の夏目漱石が、英語教師として旧制松山中学に赴任していった際、その文化的風土の対照性から『坊ちゃん』を書きたくなった、書かせた、書かざるを得なかったと考えるのはまんざら嘘でもないことは、想像がつく。まだ、東北新幹線などない時代、特急ひばりで上野―仙台間が4時間半もかかった頃である。地方と都会の様々な文化的格差というものが、都落ちした者からすと、心のトラウマともなりうる。菅原道真の大宰府左遷は、こんなレベルではなかったであろうし、歴代天皇で、地方へ流罪ともなった帝などの心中はどれほどのものであったことであろう、今になって、それが痛いほどわかる。それほど、昭和40~50年代は、文化風土、学校のカラー、高校生のキャラなど今では、想像できないほど対照的でもあった。いや、感受性が敏感な(?!)17才の私にはそう感じられた。
この、都会っ子〔※厳密には、東京の下町っ子である〕の17の私と、荒々しい校風で、なじめぬ、理不尽ともいえる慣習(?!)のギャップを、担任のW先生に、自校の問題点として列挙した数点、この、嫌で嫌でたまらない問題点(?!)というものを、その後、教育実習で、約10年後、母校を訪問してみて、分かったのである。「露木君が、あの頃、お母様を連れて、本校に、退学するか否かで悩まれて訪れた際、君が、吐露した本校の問題点とやらが、近年、自校の生徒が、不登校や退学、休学する大きな原因ともなっていて、それを、改善しなくてはと教員たちの議題の的ともなり、露木君が、嫌がっていた本校の色々な慣習を、改めたり、止めたりしたんだよ」このように、まだ勤務されていたW先生から知らされたのである。ああ、東北新幹線もすでに開通し、中央の大手量販店イトーヨーカドーやジャスコ(イオン)も進出してきている時代である。地元密着系のエンドーチェーンというスーパーも消滅し、仙台を基盤とする、石巻にもあった百貨店丸光デパートも姿を消した。地方の都会化である。その影響は、少年少女の気質にも波及する。そうだったんだ。昭和の後半の高校生のキャラ、平成の前半の高校生のキャラ、経済的背景を付け加えれば、バブルの夜明け前とバブル崩壊以後の日本社会において、全く変わってしまったのである。いわば、私が、その予兆ともなる、キャラの変貌する“カナリア”(“悪”の予兆者)のような存在だったわけである。
17才の私は、このように、宮城県の教育風土、石巻の学校文化色、田舎の生徒の気質など、様々な要因が後押して、学校が息苦しかった。ヘルマン・ヘッセの『車輪の下』ではないが、入学してみて、その学校の空気が余りに予想や期待と違い過ぎていた。また、一般の高校生にもさもありなん的、入学してみたらこんなに勉強がちがちの学校だったのか!など感受性の強い時期の、外部と内部の感性の齟齬から生じる、不適応、疎外感、これに悩まされる者は多い。それがもとで、不登校、ひきこもり、不良など、通常の、平凡なルートを外れる例は枚挙にいとまがない。
私もその口であったが、その一歩手前で留まった。それは、子供の頃のヤンチャ気質に裏打ちされた楽観主義、そして、宅浪時代に身についた読書習慣から派生した文学志向気質、言い換えると、文学青年の萌芽、それが、私を再度高校中退から思いとどまらせた。飛躍にも聞こえるやかもしれないが、それが引きがねともなり、その代償ともいえるのが、私の理系離れ、数学興味薄、数学苦手、数学嫌い、そして、数学放棄とあいなったのである。その原因と結果を語るとなると、大変な脱線にもなるので、この点は、深く言及しないが、それが、学校の授業への興味薄への引き金ともなり、そして、学校は単に卒業するだけの、目的通過点に過ぎ存在となれ果ててもいった。部活動など濃い人間関係をともなう活動・行為など論外、友人関係など薄っぺらくても構わない、授業が終わると、即、自転車で、自宅へ帰るという、そして、勉強ではなく本を友とする日常が始まるである。
したがって、私の高校時代は、そうならざるをえない、そうなるのが宿命ともいえる、帰宅部でもあった。本当であれば、軟式野球部にでも入り、思い切り野球でもやりたかった。数回、校庭のわきで、その軟式野球部の練習を見つめては、「あのピッチャー、俺より球が遅い、もし、俺が入ったら、エースだな!」と自慢れ心をこみ上げながら、そう思いながらも、学校の図書館へと足を向けたものである。その頃、自宅近くの石巻漁港の広い空き地のコンクリートの壁に軟式ボールを週数回、暮色の落ちかかる漁港に逗留している大型漁船を横目に、毎回100球近く投げ込んでは、運動不足と野球への未練や鬱憤を晴らしてもいた。その当時、スピードガンなるものが、市内のゲームセンターにあり、時速130キロは投げられた地肩の強い、投手くずれ、アウトロウの隠れ野球少年でもあった。ここで、人は、「どうしてその時、軟式野球部に入らかったのか?入ればよかったじゃん!」と呟くことであろう。いやいや、その当時の心境は、複雑で、重松清ばりの青春小説にでもしなければ、理解、納得されもしないことであろう。わかる人だけ、お分かりくださればいいのである。
この喩えは、弊著『ポップスの規矩』でも言及した覚えがあるが、京都への就学旅行の際、新横浜駅に集合、そして全員で、数車両貸し切りで関西へ向かう。しかし、私は、訳あって遅刻してしまい、その新幹線に乗りそこない、その後から来る新幹線に、一人ぽつんと、ビジネスマンなどが乗車している車内で、目的地に向かったような心境、その2時間余りが、私の高校時代とも言えなくもない。就学旅行とは、その電車やバスの‘車内のわいわいがやがや’が楽しいわけで、その旅行の端緒がくじかれると興ざめする、その心境が、軽い疎外感ともなり、それが、私を高校時代の帰宅部へと誘導した感が強い。
ついでながら、疎外感というものが、ある意味、“笑み”を奪うというエピソ―ドである。 三島由紀夫のエピソ―ドであるが、「彼は、顔は笑っていても目は笑っていなかった」とも評された。恐らく、彼は同年代の友人が大東亜戦争で徴兵され、戦火に散っていったことを、ひいき目に、負い目にも感じていたという“色眼鏡(先入観)”を持って、三島の周囲の知識人の目には、そう映っていたのであろうか?いや、事実、そうだったのかもしれない。
私は、両親の離婚を機に、東京の高校を1学期途中で中退した。その契機に関して、その後の8か月ほどの中学浪人時代の詳細は、この場で省くとして、この東北の片田舎での宅浪時代というものが、17才以降の私の個性、また、表層的人格、知的な趣向をも決定したともいっていい。そのことを考慮の上で、高校時代の、「余は如何にして帰宅部となりしか」の後半を読んでいただけば幸いである。
まず、私の母校である県立石巻高校に関してである。県北では、一応の進学校である。週刊朝日の名編集長扇谷正造、俳優中村雅俊、芥川作家辺見庸などを輩出した旧制中学の流れを汲む普通科の学校でもある。東北屈指の湊町にあることもあり、校風はバンカラ、漁師〔※遠洋漁業の船乗りも含む〕の息子がクラスには数名はいた。農家の息子もちらほらいた。驚いたことに、クラスには、1人か2人は、私同様、中学浪人している者がいたという事実であった。東北新幹線などなき時代、東京と地方の文化的な格差や色合いなど明々白々の昭和である。生徒も、あたり前ながら、非都会的気質の者が多かった。スポーツではラグビーが強かった。気仙沼や古川といった学区違いの秀才は、仙台は遠いこともあったのだろう、この石巻市に下宿している者も多かった。
これは、地方・田舎の都会化の顕れともなっている事例などで一つ挙げておく。
ちょうど私が高校1年の後半であっただろうか、具体的には、述べないが、この高校の独特のしきたりというものがあった。応援練習〔上級生による一種、イジメ的慣習である〕、過激な(?!)体育祭、独特の(?!)文化祭などにかかわらざるをえない立場上、嫌で嫌で堪らず、いよいよ担任のW先生へ、母同行で、退学の相談にまで伺った。大検ルートで、さっさと、大学へ進む進路を手にするべきか否かという迷いからである。しかし、その場で、母子家庭、また、宅浪生活で、孤独とも再び向きあうこれからなどを考えて、様々な前途の光景を思い描いては、その場では思いとどまった。東京からやってきた、それも、少々、趣味など洗練され(?!)、おぼっちゃん系(?!)の高校に通っていた私には、衝撃的なものの連続であった。デリカシーがない、やぼったい、あらくれといた性質とも、思春期には、感じられる学校の校風に、胸くそが悪くなった、嫌悪感すら覚えた。江戸っ子気質の夏目漱石が、英語教師として旧制松山中学に赴任していった際、その文化的風土の対照性から『坊ちゃん』を書きたくなった、書かせた、書かざるを得なかったと考えるのはまんざら嘘でもないことは、想像がつく。まだ、東北新幹線などない時代、特急ひばりで上野―仙台間が4時間半もかかった頃である。地方と都会の様々な文化的格差というものが、都落ちした者からすと、心のトラウマともなりうる。菅原道真の大宰府左遷は、こんなレベルではなかったであろうし、歴代天皇で、地方へ流罪ともなった帝などの心中はどれほどのものであったことであろう、今になって、それが痛いほどわかる。それほど、昭和40~50年代は、文化風土、学校のカラー、高校生のキャラなど今では、想像できないほど対照的でもあった。いや、感受性が敏感な(?!)17才の私にはそう感じられた。
この、都会っ子〔※厳密には、東京の下町っ子である〕の17の私と、荒々しい校風で、なじめぬ、理不尽ともいえる慣習(?!)のギャップを、担任のW先生に、自校の問題点として列挙した数点、この、嫌で嫌でたまらない問題点(?!)というものを、その後、教育実習で、約10年後、母校を訪問してみて、分かったのである。「露木君が、あの頃、お母様を連れて、本校に、退学するか否かで悩まれて訪れた際、君が、吐露した本校の問題点とやらが、近年、自校の生徒が、不登校や退学、休学する大きな原因ともなっていて、それを、改善しなくてはと教員たちの議題の的ともなり、露木君が、嫌がっていた本校の色々な慣習を、改めたり、止めたりしたんだよ」このように、まだ勤務されていたW先生から知らされたのである。ああ、東北新幹線もすでに開通し、中央の大手量販店イトーヨーカドーやジャスコ(イオン)も進出してきている時代である。地元密着系のエンドーチェーンというスーパーも消滅し、仙台を基盤とする、石巻にもあった百貨店丸光デパートも姿を消した。地方の都会化である。その影響は、少年少女の気質にも波及する。そうだったんだ。昭和の後半の高校生のキャラ、平成の前半の高校生のキャラ、経済的背景を付け加えれば、バブルの夜明け前とバブル崩壊以後の日本社会において、全く変わってしまったのである。いわば、私が、その予兆ともなる、キャラの変貌する“カナリア”(“悪”の予兆者)のような存在だったわけである。
17才の私は、このように、宮城県の教育風土、石巻の学校文化色、田舎の生徒の気質など、様々な要因が後押して、学校が息苦しかった。ヘルマン・ヘッセの『車輪の下』ではないが、入学してみて、その学校の空気が余りに予想や期待と違い過ぎていた。また、一般の高校生にもさもありなん的、入学してみたらこんなに勉強がちがちの学校だったのか!など感受性の強い時期の、外部と内部の感性の齟齬から生じる、不適応、疎外感、これに悩まされる者は多い。それがもとで、不登校、ひきこもり、不良など、通常の、平凡なルートを外れる例は枚挙にいとまがない。
私もその口であったが、その一歩手前で留まった。それは、子供の頃のヤンチャ気質に裏打ちされた楽観主義、そして、宅浪時代に身についた読書習慣から派生した文学志向気質、言い換えると、文学青年の萌芽、それが、私を再度高校中退から思いとどまらせた。飛躍にも聞こえるやかもしれないが、それが引きがねともなり、その代償ともいえるのが、私の理系離れ、数学興味薄、数学苦手、数学嫌い、そして、数学放棄とあいなったのである。その原因と結果を語るとなると、大変な脱線にもなるので、この点は、深く言及しないが、それが、学校の授業への興味薄への引き金ともなり、そして、学校は単に卒業するだけの、目的通過点に過ぎ存在となれ果ててもいった。部活動など濃い人間関係をともなう活動・行為など論外、友人関係など薄っぺらくても構わない、授業が終わると、即、自転車で、自宅へ帰るという、そして、勉強ではなく本を友とする日常が始まるである。
したがって、私の高校時代は、そうならざるをえない、そうなるのが宿命ともいえる、帰宅部でもあった。本当であれば、軟式野球部にでも入り、思い切り野球でもやりたかった。数回、校庭のわきで、その軟式野球部の練習を見つめては、「あのピッチャー、俺より球が遅い、もし、俺が入ったら、エースだな!」と自慢れ心をこみ上げながら、そう思いながらも、学校の図書館へと足を向けたものである。その頃、自宅近くの石巻漁港の広い空き地のコンクリートの壁に軟式ボールを週数回、暮色の落ちかかる漁港に逗留している大型漁船を横目に、毎回100球近く投げ込んでは、運動不足と野球への未練や鬱憤を晴らしてもいた。その当時、スピードガンなるものが、市内のゲームセンターにあり、時速130キロは投げられた地肩の強い、投手くずれ、アウトロウの隠れ野球少年でもあった。ここで、人は、「どうしてその時、軟式野球部に入らかったのか?入ればよかったじゃん!」と呟くことであろう。いやいや、その当時の心境は、複雑で、重松清ばりの青春小説にでもしなければ、理解、納得されもしないことであろう。わかる人だけ、お分かりくださればいいのである。
この喩えは、弊著『ポップスの規矩』でも言及した覚えがあるが、京都への就学旅行の際、新横浜駅に集合、そして全員で、数車両貸し切りで関西へ向かう。しかし、私は、訳あって遅刻してしまい、その新幹線に乗りそこない、その後から来る新幹線に、一人ぽつんと、ビジネスマンなどが乗車している車内で、目的地に向かったような心境、その2時間余りが、私の高校時代とも言えなくもない。就学旅行とは、その電車やバスの‘車内のわいわいがやがや’が楽しいわけで、その旅行の端緒がくじかれると興ざめする、その心境が、軽い疎外感ともなり、それが、私を高校時代の帰宅部へと誘導した感が強い。
ついでながら、疎外感というものが、ある意味、“笑み”を奪うというエピソ―ドである。 三島由紀夫のエピソ―ドであるが、「彼は、顔は笑っていても目は笑っていなかった」とも評された。恐らく、彼は同年代の友人が大東亜戦争で徴兵され、戦火に散っていったことを、ひいき目に、負い目にも感じていたという“色眼鏡(先入観)”を持って、三島の周囲の知識人の目には、そう映っていたのであろうか?いや、事実、そうだったのかもしれない。
2022年10月31日 16:41