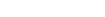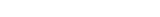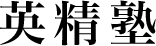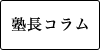カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (3)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
コラム 4ページ目
2025/07/07
水泳の授業は必要?不要?~人生の危機管理~
近年、猛暑の夏で、従来では考えられない学校の授業での現象をニュースで知った。超高温のため、学校の体育の授業で、水泳が中止となるケースが頻繁に起こっているという。素人的、昭和世代の水泳授業経験者からす...
2025/06/30
教育から経済にわたり、徳から金へシフト!?
「学校で学んだことは、社会で役に立つのか?」といった幼稚な問いが、時代のあぶくのように、定期的に、澎湃と、メデャアや教育界でよく浮上する。これは、特に、高校英語に関しては、際立ってもいる。数学や理科...
2025/06/23
受験科目と自身の長所と短所
人間には、当然ながら、長所と短所とが必ずあるものである。人格面でいえば、後者を如何に直すか、克服するか、それが優先されもする。躾という側面である。後者は、社会や組織といった人間関係の最大の障害ともな...
2025/06/16
スペシャリストかゼネラリストか?~高校生ヴァージョン~
ここで、一つ命題をあげてみよう。「高校生は、広く浅くのゼネラリストは不向きである」というものだ。この文脈で、国公立受験より、私立受験の方が、思春期の高校生には、当然ともいえる、文科省・学校当局の価値...
2025/06/09
日本人は揺れ幅が激しいのは英語教育も同じ!
日本人は、極端に、何かにつけて振れ幅が大きい。行動や思考が、白から黒へ、青から赤へ、極端すぎるのである。ゆえに、江戸時代頃からだろうか、賢者は、昔から、日本人に中庸を説くのである。 明治維新によ...
2025/06/02
推薦制度とZ世代気質の親和性
弊塾の教え子、特に女子に多いのだが、世界史や日本史選択の高3生で、推薦でMARCHレベル以上の大学に行きたいモチベーションがある者に限り、歴史そのものに関心がない。でも、内申の評定を、4から5にもっ...
2025/05/26
英語の授業は古典の授業化している
これは、推薦で大学進学する生徒の激増とも大きくリンクするのだが、平成後半から、令和にかけて、弊塾の授業から、また、入塾の面談から、現代の高校生の英語の授業の古典化現象が目に浮かんでくる、非常にリアル...
2025/05/19
消費税10%と共通テストは亡国への一里塚
経済学者は、世を、自らの学問を眼鏡に経済を概観する。法学者は、時代を、同様に、法制度や人権を通して分析、そして状況を裁断する。文学者、いや、作家は、自らの嗅覚を通して、時代を描く、時に、問題点を剔抉...
2025/05/12
高校時代は、小さな完成品よりも、大きな未完成品を作る時代だ
「高校時代は、小さな完成品よりも、大きな未完成品を作る時代だ」(阿川弘之) この言葉ほど、現代の高校生、そして、世の風潮、そして、文科省を含めた教育界において忘れさられている、いや、本来がそう...
2025/05/06
⑪質か量か?~最終回~
初等教育、いわゆる、小学校時代は、思春期前の従順な気質も預かってか、量と数で、徹底的に帰納法で、教え叩き込む。勿論、当世風の考える授業やアクティブラーニングなど、二の次で構わない。中学受験をする、そ...
<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。