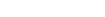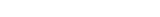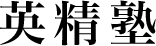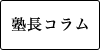カテゴリ
- おすすめの参考書
- 保護者の方へ (10)
- 2020年問題 (3)
- おすすめの教養書
月別 アーカイブ
- 2026年2月 (2)
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (5)
- 2025年8月 (3)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (5)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (4)
- 2024年7月 (5)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (5)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (10)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (8)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (7)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (5)
- 2020年3月 (5)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (5)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (7)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (4)
最近のエントリー
コラム 2ページ目
2025/11/24
"バカの壁"とは、国語や英語が苦手とする心根である
“バカの壁”とは、本も読まずして、国語ができるようになりたいと思う心根のことだ! つまり、興味や関心がない、時に、嫌いでさえある領域を武器にしようとするお目出度い部族の特性の...
2025/11/17
規律という<型>から自由という<個性>が生まれる
権利と義務、当然ながら社会人として、国民として持つべき分別とやらである。前者に比重がかかる人間を、進歩派・革新派と呼び、後者を主張する人間を、保守派・守旧派とも呼ぶ。一般常識人は、この二つの比重の塩...
2025/11/10
"衣食足りて礼節を知る"&"小人閑居して不善をなす"
成功すると慢心になる、現状維持の守りに入る。自由を手に入れると放縦になる、分をわきまえなくなる。豊さを手に入れると、ものごとを上から目線ともなり、貧困の世界に疎遠ともなる。豊臣秀吉の晩年である。これ...
2025/11/03
成功の反対は失敗?自由の反対は不自由?
「成功の反対は、失敗ではなく妥協である」この言葉は、吉本興業の名プロデューサー木村政雄のものです。この名言には、人間の本性、人間の弱さ、人間のファジーさ、こうした側面が、映し出されてもいます。 ...
2025/10/27
便利・快適という自由は、真の自由を奪う
戦争と平和 対にしてよく語られるが、通常は平和の時代の中に、雨後の筍の如きに事故や災害として、不幸が起こると一般人は考えやすい。晴天が長く、時々雨が降るように考える。一方、東洋的、特に仏教的文脈でな...
2025/10/21
自由と規律~母語と外国語~
どんな言語にも、英語にしろ仏語にしろ、当然、日本語にしろ、外国語の要素のない言語などない、そういってことばが多様化してきた。この意味するところは、言語というものは、それぞれ他の言語の影響を受け、また...
2025/10/13
<自由と規律>のバランスに欠けた令和
今の天皇陛下が、独身で、英国留学されていた頃、昭和の時代である。浩宮殿下が、メディアの質問か何かで、「何か、お好きな書は、ございますか?」と質問をされた際、『自由と規律』(池田潔)という岩波新書を挙...
2025/10/06
科目の因果は廻る~国語と英語~
「風が吹けば桶屋が儲かる」的言説とも捉えられかねないが、一応は、自身の経験に基づく教育的私見を語ってみたい。 最近、算盤ブームが再来しているとテレ朝のワイドスクランブルという番組で報じていた。そ...
2025/09/29
学校当局者の責務~英数国を通して~
これまで、特に、英数国という中等教育の要となる教科が、英語が中間子となり、左右の数学と国語と連結しているとか、また、五輪ならぬ、三輪の如く、論理性をコアに、英語の成績を伸ばせば(正しく指導するという...
2025/09/22
数英国は、"三(っの)輪"の関係だ
前回、英語という科目は、中等教育において、特に、中学の段階で、数学と国語の中間子的役割を果たすと申しあげました。それは、もっと、具体的に、今回は、語ってみようかと思います。 世界で、最も有名なシン...
<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。